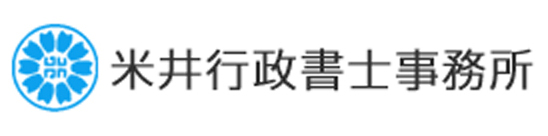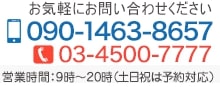【在留資格】興行
2011年10月07日(金)10:49 PM
【本邦において行うことができる活動】
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動
【該当例】
俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など
【在留期間】
1年、6月、3月又は15日
【立証資料】
1.在留資格決定の場合
(1)演劇、演芸、歌謡、舞踏又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合
ア.経歴書及び活動に係る経歴書を証する文書
イ.基準省令の表の法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動の項の
登記事項証明書、損益計算書の写しその他の契約機関の概要を明らかにする資料
ウ.興行を行う施設の概要を明らかにする資料
エ.興行に係る契約書の写し
オ.活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
カ.基準省令の興行の項の下欄第一号ロに規定する興行契約に基づいて演劇等の興行に
係る活動を行おうとするときは、次に掲げる資料
①契約機関の経営者及び常勤の職員の名簿
②契約機関の経営者及び常勤の職員が基準省令の興行のの項の下欄第一号ロのいずれ
にも該当しないことを契約機関が申し立てる書面
③契約機関が過去三年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留
する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていることを証する文書
キ.基準省令の興行の項の下欄第一号ハに規定する施設を運営する機関の次に掲げる資料
①登記事項証明書、損益計算書の写しその他の運営機関の概要を明らかにする資料
②運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員の名簿
③運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が基準省令の
興行の項の下欄第一号のいずれにも該当しないことを運営機関が申し立てる書面
(2)基準省令の興行の項の下欄第二号イからホまでのいずれかに該当する場合
前号イ及びハからホまでに掲げるもののほか、招へい機関の登記事項証明書、
損益計算書の写しその他の招へい機関の概要を明らかにする資料
(3)演劇等の興行に係る活動を行おうとする場合
ア.経歴書並びに活動に係る経歴及び資格を証する公的機関が発行した文書職歴等
の経歴を証する文書及び公的機関が発行する資格証明書がある場合はその写し
イ.招へい機関の概要を明らかにする資料
①登記事項証明書(発行後三ヶ月以内のもの)
②直近の損益計算書の写し
③従業員名簿
ウ.興行を行う施設の概要を明らかにするもの
①営業許可書の写し
②施設の図面
③施設の写真
④従業員リスト
⑤登記事項証明書(登記簿謄本)※発行後三ヶ月以内のもの
⑥損益計算書
⑦確定申告書控の写し
エ.招へい機関が興行を請け負っているときは請負契約書の写し
オ.次のいずれかの一又は複数の文書で活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの
①雇用契約書の写し
②出演承諾書の写し
③①又は②に準ずる文書
カ.その他参考となるもの
①公演日程表
②公演内容を知らせる広告・チラシ等
(4) 興行の形態以外の形態で行われる芸能活動を行おうとする場合
興行の形態以外の形態で行われる芸能活動を行おうとする場合
ア.芸能活動上の業績を証する資料
所属機関の発行する資格証明書又は経歴証明書、レコードジャケット、ポスター、
雑誌、新聞の切り抜き等で芸能活動上の業績を証するもの
イ.次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間及び報酬を証するもの
①雇用契約書の写し
②請負契約書の写し
③①又は②に準ずる文書
ウ.次のいずれかの一又は複数の文書で、受入れ機関の概要を明らかにする資料
①登記事項証明書(登記簿謄本)※発行後三ヶ月以内のもの
②損益計算書
③案内書
④①ないし③に準ずる文書
2.在留期間更新の場合
(1)次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容及び期間を証するもの
ア.在職証明書
イ.雇用契約書んp写し
ウ.ア又はイに準ずる文書
(2)興行に係る契約書の写し
(3)次のいずれかで、収入及び納税額に関する証明書
ア.住民税又は所得税の納税証明書
イ.源泉徴収票
ウ.確定申告書控の写し
エ.アないしウに準ずる文書
(4)その他参考となる資料として、前回の申請時から出演先施設に変更が生じた場合は、
変更後の出演先施設にについての概要を明らかにするもの
【ポイント】
①興業とは、特定の施設において公衆に対して映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は
見世物を見せ又は聞かせることをいう。
②「興業に係る活動」には, 出演者はもちろん当該興業に必要な活動を行なう者、
例えば、サーカスの動物飼育員、スポーツ選手のトレーナー等としての活動も該当する。
③これらの活動は、芸術上の活動であっても「芸術」の在留資格ではなく、「興行」の
在留資格に該当する。
【引用】
出入国管理のしおり
ひと目でわかる外国人の入国・在留案内
・・・【在留資格について】はこちらをクリックしてください>>
【在留資格】技能
2011年10月07日(金)10:47 PM
【本邦において行うことができる活動】
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を
要する業務に従事する活動
【該当例】
外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人、建築技術者、
外国製品の製造・修理、動物の調教、ソムリエ、石油・地熱等掘削調査
【在留期間】
5年、3年、1年、3月
※在留期間3月の場合、在留カードは発行されません。
【立証資料】
1.在留資格決定の場合
(1)招へい機関の概要を明らかにする資料
ア.登記事項証明書(発行後三ヶ月以内のもの)
イ.直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後一年間の事業計画書)
ウ.案内書
エ.外国人社員リスト(国籍、氏名、生年月日、性別、在留資格、在留期間を明記したもの)
※公刊物等で招へい機関の概要が明らかになる場合は必要ありません
(2)経歴書並びに活動に係る経歴及び資格を証する公的機関が発行した文書
ア.申請人の履歴書
イ.公的機関が発行する資格証明書がある場合は、当該証明書の写し
ウ.所属機関からの在職証明書で、関連する業務に従事した期間を証するもの
(3)次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの
ア.招へい機関との雇用契約書の写し
イ.招へい機関からの辞令の写し
ウ.招へい機関からの採用通知書の写し
エ.アないしウに準ずる文書
2.在留期間更新の場合
(1)次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間及び地位を証するもの
ア.在職証明書
イ.雇用契約書の写し
ウ.ア又はイに準ずる文書
(2)次のいずれかで、年間の収入及び納税額に関する証明書
ア.住民税又は所得税の納税証明書
イ.源泉徴収票
ウ.確定申告書控の写し
エ.アないしウに準ずる文書
【ポイント】
①「本邦の公私の機関」には、我が国の政府関係機関、地方公共団体関係機関、
公社、公団、会社、公益法人等のほか、本邦にある外国の政府関係機関、外国の
地方公共団体関係機関、国際機関、外国法人の支店・支社等も含まれる。
②「契約」には、雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれるが特定の機関との
継続的なものでなければならない。
③国・公立の機関以外の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、当該機関の
事業が適正に行なわれるものであり、かつ、安定性及び継続性の認められるもので
なければならない。
【引用】
出入国管理のしおり
ひと目でわかる外国人の入国・在留案内
・・・【在留資格について】はこちらをクリックしてください>>
【在留資格】技能実習
2011年10月07日(金)10:44 PM
【本邦において行うことができる活動】
1号
イ
本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める
事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員がこれらの本邦の
公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う
技能等の修得をする活動(これらの職員がこれらの本邦の公私の機関の本部にある事業所に
受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得をする活動を含む)
ロ
法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の
修得及び当該団体の策定した計画に基づき、当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の
機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動
2号
イ
1号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が
指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する
業務に従事する活動
ロ
1号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が
指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に
従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下に
当該業務に従事するものに限る)
【該当例】
技能実習生
【在留期間】
1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
【立証資料】
1.在留資格決定の場合
(1)法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動を行なおうとする場合
イ.技能実習の内容、必要性、実施場所、期間及び到達目標を明らかにする技能実習計画書
ロ.本邦入国後に行なう講習の期間中の待遇を明らかにする文書
ハ.帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することを証する文書
ニ.基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる
活動の項の下欄第五イに規定する送出し機関の概要を明らかにする資料
ホ.基準省令の技能実習第一号イの項の下欄第五号に規定する実習実施機関の
登記事項証明書、損益計算書の写し、常勤の職員の数を明らかにする文書及び
技能実習生名簿
ヘ.外国の所属機関と本邦の実習実施機関の関係を示す文書
ト.外国の所属機関における職務内容及び勤務期間を証する文書
チ.送出し機関及び実習実施機関と当該外国人の間に締結された技能実習実施に
係る契約書の写し
リ.実習実施機関における労働条件を当該外国人が理解したことを証する文書
ヌ.基準省令の技能実習第一号イの項の下欄第九号に規定する技能実習指導員の
当該技能自実習において修得しようとする技能等に係る経歴を証する文書
ル.本邦外において講習又は外部講習を受けた場合は、当該講習又は外部講習の内容、
実施機関、実施場所及び期間を証する文書
(2)法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動を行なおうとする場合
前号イからホまで及びチからルまでに掲げるもののほか、次に掲げる資料
イ.職業を証する文書
ロ.国籍若しくは住所を有する国の国若しくは地方公共団体の機関又はこれらに準ずる
機関から推薦を受けていることを証する文書
ハ.基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる
活動の項の下欄第六号に規定する監理団体の登記事項証明書、定款、技能実習生
受入れに係る規約、損益計算書の写し、常勤の職員の数を明らかにする文書及び
技能実習生名簿
ニ.監理団体と送出し機関との間に締結された技能実習実施に係る契約書の写し
ホ.監理団体が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄
に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号イからヘまでのいずれかに該当
する場合は、当該監理団体が技能実習の運営に関し我が国の国若しくは地方公共団体
又は独立行政法人則法からの資金その他の援助及び指導を受けていることを
明らかにする文書
ヘ.監理団体が監理に要する費用を徴収する場合は、当該費用の負担者、金額及び
使途を明らかにする文書
ト.基準省令の技能実習第一号ロの項の下欄第六号ニに規定する斡旋機関がある
場合は、その概要を明らかにする資料及び常勤職員名簿
(3)法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イに掲げる活動を行なおうとする
場合、第一号イ、ハ及びチからヌまでに掲げるもののほか、次に掲げる資料
イ.基礎二級の技能検定その他これに準ずる検定又は試験に合格している証する文書の写し
ロ.技能実習の進捗状況を明らかにする文書
ハ.年間収入及び納税額に関する証明書
ニ.実習実施機関が受入れている技能実習生名簿
(4)法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号ロにに掲げる活動を行なおうと
する場合、第一号イ、ハ及びチからヌまでに掲げる資料、前号イからニまでに掲げる
資料並びに監理団体が受入れている技能実習生名簿
2.在留期間更新の場合
(1)法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ又は第二号イに掲げる活動を
行なおうとする場合
イ.技能実習の内容、実施場所、期間、進捗状況及び到達目標を明らかにする
技能実習計画書
ロ.実習実施機関と当該外国人の間に締結された技能実習実施に係る契約書の写し
ハ.実習実施機関における労働条件を当該外国人が理解したことを証する文書
ニ.年間の収入及び納税額に関する証明書
ホ.実習実施機関が受入れている技能実習生名簿
(2)法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロ又は第二号ロに掲げる活動を
行なおうとする場合、前号に掲げる資料及び監理団体が受入れている技能実習生名簿
【引用】
出入国管理のしおり
ひと目でわかる外国人の入国・在留案内
・・・【在留資格について】はこちらをクリックしてください>>
【在留資格】文化活動
2011年10月07日(金)10:42 PM
【本邦において行うことができる活動】
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について
専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(在留資格の留学、
研修活動に掲げる活動を除く)
【該当例】
日本文化の研究者等
【在留期間】
1年又は6月
【立証資料】
1.在留資格決定の場合
(1)学術上若しくは芸術上の活動を行い、又は我が国特有の文化若しくは技芸について
専門的な研究を行おうとする場合
ア.活動の内容及び期間並びに当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
①申請人又は受入れ機関が作成した活動内容及びその期間を明らかにする文書
②申請人が当該活動を行おうとする機関の案内書等でその概要を明らかにするもの
イ 次の文書で、学歴、職歴及び活動に係る経歴を証する文書
①卒業証明書又は卒業証明書の写し
②申請人の履歴書
③在職証明書
④次のいずれかの一又は複数の文書で学術上又は芸術上の業績を明らかにするもの
・関係団体からの推薦状
・過去の活動に関する報道
・入賞、入選等の実績
・過去の論文、作品等の目録
ウ.在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
①申請人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料
・給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
・申請人名義の銀行等における預金残高証明書
・上記に準ずる文書
②申請人以外の者が申請人の経費を支弁する場合は、経費支弁者に係る次のいずれか
で、申請人の経費を支弁することができることを証する資料
・住民税又は所得税の納税証明書(総所得が記載されたもの)
・源泉徴収票
・確定申告書控の写し
・上記に準ずる文書
(2)専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合
(1)に掲げるもののほか、当該専門家の経歴及び業績を明らかにする資料
ア.(1)に掲げるもの
イ.当該専門家の経歴書
ウ.次のいずれかの一又は複数の文書で、当該専門家の業績を明らかにするもの
①免許書の写し
②論文、作品集等
③①又は②に準ずる文書
2.在留期間更新の場合
(1)活動内容及び期間並びに当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
申請人若しくは受入れ機関又は指導を行っている専門家が作成した活動の内容、
機関を明らかにする文書
(2)在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
ア.申請人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの一又は複数の資料
①給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する明細書
②申請人名義の銀行等における預金残高証明書
③①又は②に準ずる文書
イ.申請人以外の者が申請人の経費を支弁する場合は、経費支弁者に係る次の
いずれかで、申請人の経費を支弁することができることを証するもの
①住民税又は所得税の納税証明書(総所得が記載されたもの)
②源泉徴収票
③確定申告書控の写し
④①ないし③に準ずる文書
【ポイント】
①外国の大学の教授、助教授、講師等や外国の研究機関から派遣された者が本邦に
おいて報酬を受けないで行なう調査・研究活動、大学院において教授等の指導の下に
無報酬で研究を行なう研究生の活動等当該活動に基づいて収入を得るものではない
学術上の活動が全て含まれる。
②「専門家の指導を受けてこれを修得する」とは、我が国特有の文化又は技芸に精通した
専門家から個人指導を受けて修得することをいう。
なお、、教育機関に在籍して修得する場合は、留学又は就学の在留資格を決定する。
【引用】
出入国管理のしおり
ひと目でわかる外国人の入国・在留案内
・・・【在留資格について】はこちらをクリックしてください>>
【在留資格】短期滞在
2011年10月07日(金)10:40 PM
【本邦において行うことができる活動】
本邦に短期滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、
業務連絡その他これらに類似する活動
【該当例】
観光客、友人や親族の訪問、会議参加者、競技会参加者など
【在留期間】
90日、30日又は15日以内
【立証資料】
1.在留資格決定の場合
(1)本邦から出国するための航空機等の切符又はこれに代わる運送業者の発行する保証書
(2)本邦以外の国に入国することができる当該外国人の有効な旅券
(3)在留中の一切の経費の支払能力を明らかにする資料
ア.申請人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料
①申請人名義の銀行等における預金残高証明書
②我が国において支弁可能な資産を有することを証する文書
③①又は②に準ずる文書
イ.申請人以外の者が申請人の経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の
いずれかで、申請人の経費を支弁することができることを証するもの
①住民税又は所得税の納税証明書
②源泉徴収票
③確定申告書控の写し
④①ないし③に準ずる文書
【引用】
出入国のしおり
ひと目でわかる外国人の入国・在留案内
・・・【在留資格について】はこちらをクリックしてください>>
【在留資格】留学
2011年10月07日(金)10:37 PM
【本邦において行うことができる活動】
本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)若しくは特別支援学校の
高等部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編成に関してこれらに準ずる期間において
教育を受ける活動
【該当例】
大学、短期大学、高等専門学校及び高等学校等の学生
【在留期間】
4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月、3月
※3月の在留期間の場合、在留カードの発行はありません。
【立証資料】
原則として次のとおりですが、在籍管理が適切でない教育機関の学生等については、
その他の書類の提出が必要となる場合があります。
1.在留資格決定の場合
(1)教育を受けようとする機関の入学許可書の写し
(2)在留中の一切の経費の支払能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費を
支弁する場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った
経緯を明らかにする文書
(3)申請人が研究生又は聴講生として教育を受けようとする場合には、当該機関からの
研究内容又は科目及び時間数を証する文書
(4)申請人が基準省令の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項
の下欄第一号ハに該当する活動を行う場合は、卒業証明書及び経歴を明らかに
する文書
2.在留期間更新の場合
(1)教育を受けている機関からの在学証明書及び成績証明書
(2)研究生の場合は、上記の(1)に加えて研究内容を聴講生の場合は、聴講科目及び
時間数を記載した履習届写し等の文書で、大学の学部等の機関において発行されたもの
(3)在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁
する場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った
経緯を明らかにする文書
ア.申請人が学費・生活費を支弁する場合
①奨学金の支給証明書
②本人名義の銀行等における預金残高証明書又は預金通帳の写し
③送金証明書
イ.申請人以外の者が学費・生活費を支弁する場合
①経費支弁者作成の経費支弁書
②経費支弁者に係る次のいずれかの一又は複数の文書で、申請人の学費・生活費を
支弁することを証するもの
・経費支弁者の課税証明書
・源泉徴収票
・確定申告書控の写し
・経費支弁者名義の預金残高証明書
ポイント
大学は、大学の別科及び専攻科、短期大学、大学院、付属の研究所等が含まれる。
【引用】
出入国のしおり
ひと目でわかる外国人の入国・在留案内
・・・【在留資格について】はこちらをクリックしてください>>
【在留資格】研修
2011年10月07日(金)10:35 PM
【本邦において行うことができる活動】
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動(在留資格の
【技能実習】1号及び【留学】に掲げる活動を除く )
【該当例】
研修生
【在留期間】
1年又は6月
【立証資料】
1.在留資格決定の場合
(1)研修内容等を明らかにする資料
①研修の内容、必要性、実施場所、期間及び待遇を明らかにする研修計画書
②招へい理由書
③研修実施予定表
④研修生処遇概要書
(2)帰国後本邦において修得した技能、技術及び知識を要する業務に従事することを
証する文書
次のいずれかの文書で、帰国後本邦において修得した技能、技術及び知識を有する
業務に従事することを記載したもの
ア.派遣機関作成の現在の本人の地位・職種に関する記載のある復職予定証明書
イ.派遣機関作成の帰国後の本人の地位・職種に関する記載のある研修生派遣状
(3)職歴を証する文書
申請人の履歴書
(4)基準省令の表の法別法第一の四の表の研修の項の下欄第四号に規定する
研修指導員の当該研修において修得しようとする技能等に係る職歴を証する文書
(5)送出し機関の概要を明らかにする資料
ア.案内書
イ.登記事項証明書(登記簿謄本)
ウ.実務研修を含む場合は、ア及びイに加えて次のいずれかの文書
①派遣機関が受入れ機関の合併企業又は現地法人である場合は、合併企業又は
現地法人の設立に関する公的機関の承認書の写し又は出資率及び出資額が明記
された財務大臣あて対外直接投資に係る外貨証券取得に関する届出書の写し
②派遣機関と受入れ機関との関係が取引である場合は、信用状及び船荷証券の写し
(6)基準省令の研修の項の下欄第四号に規定する受入れ機関の登記事項証明書
及び損益計算書の写し
2.在留期間更新の場合
研修の内容、実施場所、期間、進捗状況及び待遇を証する文書
【ポイント】
①研修手当の額は、渡航費、滞在費等の実費の支払の範囲を超えてはならない。
また、実質的に労働の対価としての意味を持つものであってはならない。
(注)名目は研修手当であっても、実質は労働の対価としての意味を持つものであれば
「報酬」となり、その活動は資格外活動となる。
②「受け入れられて」とは、受入れ機関による積極的な承認、受入れ体制がが存在する
ことを意味する。いかなる機関が受入れ機関であるかは、実際に研修を実施する責任を
負っているか否かにより判断される。
具体的には、研修施設や研修を指導する者の所属、研修手当の支給主体等により
判断される。 なお、受入れ機関は単数に限らず、研修の各段階により変わる場合もある。
③「技能、技術又は知識の修得」とは、実際に役立つような能力の修得をいう。
【引用】
出入国管理のしおり
ひと目でわかる外国人の入国・在留案内
・・・【在留資格について】はこちらをクリックしてください>>
【在留資格】家族滞在
2011年10月07日(金)9:58 PM
【本邦において行うことができる活動】
在留資格をもって在留する者(技能実習を除く)又は留学の在留資格をもって在留する者の扶養を
受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
【該当例】
在留外国人が扶養する配偶者・子
【在留期間】
3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
【立証資料】
1.在留資格 決定の場合
(1)次のいずれかの一又は複数の文書で、扶養者との身分関係を証するもの
ア.戸籍謄本
イ.婚姻届受理証明書
ウ.婚姻証明書
エ.出生証明書
オ.アないしエに準ずる文書
(2)扶養者の外国人登録証明書又は旅券の写し
(3)扶養者の職業及び収入を証する文書
ア.扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
①次のいずれかで、扶養者の職業を記載したもの
・在職証明書
・営業許可書の写し等
②次のいずれかで、扶養者の年間収入及び納税額に関する証明書
・住民税又は所得税の納税証明書
・源泉徴収票
・確定申告書控の写し
・上記に準ずる文書
イ.扶養者が上記ア以外の活動を行っている場合は、次のいずれかで、申請人の
生活費用を支弁することができることを証するもの
①扶養者名義の預金残高証明書
②給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
③①又は②に準ずる文書
2.在留期間更新の場合
(1)次のいずれかの一又は複数で扶養者との身分関係を証する文書
ア.戸籍謄本
イ.婚姻届受理証明書
ウ.婚姻証明書
エ.出生証明書
オ.アないしエに準ずる文書
(2)扶養者の外国人登録証明書又は旅券の写し
(3)扶養者の職業及び収入を証する文書
ア.扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
①次のいずれかで、扶養者の職業を記載したもの
・在職証明書
・営業許可書の写し等
②次のいずれかで、扶養者の年間収入及び納税額を証するもの
・住民税又は所得税の納税証明書
・源泉徴収票
・確定申告書控の写し
・上記に準ずる文書
イ.扶養者が前記ア以外の活動を行っている場合は、次のいずれかで申請人の生活費用を
支弁することができることを証するもの
①扶養者名義の預金残高証明書
②給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
③①又は②に準ずる文書
【ポイント】
①「日常的な活動」には、教育機関において教育を受ける活動等も含まれるが、収入を
伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれない。
②配偶者には、内縁の者は含まれない。
③子には、成年に達した者及び養子も含まれる。
【引用】
出入国管理のしおり
ひと目でわかる外国人の入国・在留案内
・・・【在留資格について】はこちらをクリックしてください>>
【在留資格】特定活動
2011年10月07日(金)9:56 PM
【本邦において行うことができる活動】
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
【該当例】
高度研究者、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー等、経済連携協定に基づく
外国人看護師・介護福祉士候補
【在留期間】
5年、4年、3年、2年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
【立証資料】
1.在留資格決定の場合
(1)法別第一の五の表の下欄に掲げる活動を行おうとする場合
イ.当該外国人と契約を結んだ本邦の機関の概要を明らかにする資料
ロ.当該外国人と契約を結んだ本邦の機関の事業内容を明らかにする資料及び研究、
研究の指導又は教育と関連する事業を自ら経営する活動を行おうとする場合には、
当該事業の内容を明らかにする資料
ハ.卒業証明書及び職歴その他の経歴を証する文書
ニ.活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
(2)法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を行おうとする場合
イ.当該外国人と契約を結んだ本邦の機関の概要を明らかにする資料、及び当該機関が
労働派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
第二十三条第一項に規定する派遣元事業者である場合には、同法第三十一条に
規定する派遣先の概要を明らかにする資料
ロ.当該外国人と契約を結んだ本邦の機関の事業内容を明らかにする資料、及び
当該機関が労働者派遣法第二十三条第一項に規定する派遣元事業主である場合
には、同法第三十一条に規定する派遣先の事業内容を明らかにする資料
ハ.卒業証明書及び職歴その他の経歴を証する文書
ニ.活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
(3)法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を行おうとする場合
イ.扶養者との身分関係を証する文書
ロ.扶養者の外国人登録証明書又は旅券の写し
ハ.扶養者の職業及び収入に関する証明書
(4)法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動であって収入を伴う事業を運営する活動
又は報酬を受ける活動を行おうとする場合
活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬の
記載のあるもの
①雇用契約書の写し
②転勤命令書の写し
③受入れ機関からの辞令の写し
④①ないし③に準ずる文書
(5)その他の場合
ア.在留中の活動を明らかにする文書
申請人が作成した在留中の活動を明らかにするもの
イ.在留中の一切の経費を支弁することができることを証するもの
(ア)申請人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの文書で申請人が経費を支弁
できることを証するもの
①申請人名義の銀行等における預金残高証明書等我が国において支払可能な資産を
有することを証するもの
②前記に準ずる文書
(イ)申請人以外の者が申請人の経費を支弁する場合は、次のいずれかの一又は複数の
文書で申請人の経費を支弁することができることを証するもの
①住民税又は所得税の納税証明書
②源泉徴収票
③確定申告書控の写し
④①ないし③に準ずる文書
2.在留期間更新の場合
(1)法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を行おうとする場合
イ.活動の内容、期間及び地位を証する文書
ロ.年間の収入及び納税額に関する証明書
ハ.研究、研究の指導又は教育と関連する事業を自ら経営する活動を行っている場合
には、当該事業に係る事業所の損益計算書の写し
(2) 法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を行おうとする場合
イ.活動の内容、期間及び地位を証する文書
ロ.年間の収入及び納税額に関する証明書
(3)法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を行おうとする場合
イ.扶養者との身分関係を証する文書
ロ.扶養者の外国人登録証明書又は旅券の写し
ハ.扶養者の職業及び収入に関する証明書
(4)法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を行おうとする場合、年間の収入及び
納税額に関する証明書又は在留中の一切の経費を支弁することができることを
証する文書
ア.申請人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの文書で申請人が経費を支弁
できることを証するもの
①申請人名義の銀行等における預金残高証明書等我が国において支払可能な
資産を有することを証するもの
②前記に準ずる文書
イ.申請人以外の者が申請人の経費を支弁する場合は、次のいずれかの一又は複数の
文書で、申請人の経費を支弁することができることを証するもの
①住民税又は所得税の納税証明書
②源泉徴収票
③確定申告書控の写し
④①ないし③に準ずる文書
【引用】
出入国管理のしおり
ひと目でわかる外国人の入国・在留案内
・・・【在留資格について】はこちらをクリックしてください>>
【在留資格】人文知識・国際業務
2011年10月07日(金)9:53 PM
【本邦において行うことができる活動】
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の
分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を
必要とする業務に従事する活動
【該当例】
通訳、デザイナー、私企業の語学教師、WEBデザイナー等
【在留期間】
5年、3年、1年、3月
※3月の在留期間の場合、在留カードは発行されません。
【立証資料】
1.在留資格決定の場合
(1)招へい機関の概要を明らかにする資料
ア.登記事項証明書(発行後三ヶ月以内のもの)
イ.直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後一年間の事業計画書)
ウ.案内書(公刊物等で招へい機関の概要が明らかになる場合は必要ありません)
(2)卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証する文書
ア.卒業証明書又は卒業証明書の写し
イ.申請人の履歴書
ウ.次のいずれかの文書
①従事しようとする業務に必要な知識に係る科目を専攻した大学等の卒業証明書又は
これと同等以上の教育を受けたことを証するもの
②在職証明書等で、関連する業務に従事した期間(10年以上)を証するもの
③外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合
は、所属機関又は所属していた機関からの在職証明書で、関連する業務に三年以上
実務経験を有することを証するもの
(3)次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの
ア.招へい機関との雇用契約書の写し
イ.招へい機関からの辞令の写し
ウ.招へい機関からの採用通知書の写し
エ.アないしウに準ずる文書
2.在留期間更新の場合
(1)次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間及び地位を証するもの
ア.在職証明書
イ.雇用契約書の写し
ウ.辞令の写し
エ.アないしウに準ずる文書
(2)次のいずれかで、年間の収入及び納税額に関する証明書
ア.住民税又は所得税の納税証明書
イ.源泉徴収票
ウ.確定申告書控の写し
エ.アないしウに準ずる文書
【ポイント】
①「本邦の公私の機関」には、我が国の政府関係機関、地方公共団体関係機関、公社、
公団、会社、公益法人等のほか、本邦にある外国の政府関係機関、外国の
地方公共団体関係機関、国際機関、外国法人の支店・支社等も含まれる。
個人経営であっても、外国人が在留活動を行なうことができるに足る施設及び陣容を
有していればよい。
②「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」とは、学術上の素養を背景とする
一定水準以上の業務がであることを示すものであり、上記の人文科学の分野の
いずれかに属する知識がなければできない業務であることを意味する。
単に人文科学の分野に関連することだけでは足りない。
③「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」とは、いわゆる
外国人特有の感性、すなわち、外国に特有な文化に根ざす一般の日本人が有しない
思考方法や感受性を必要とする業務を意味する。
本人が外国人であるというだけでは足りず、当該外国人の持っている思考又は感受性が
日本文化の中では育まれないようなものであり、かつ、それがなければできない業務を意味する。
④「契約」には、雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれるが特定の特定の機関との
継続的なものでなければならない。
⑤国・公立の機関以外の機関との契約の基づいて業務に従事する場合は、当該機関の
事業が適正に行なわれるものであり、かつ、安定性及び継続性の認められるもので
なければならない。
⑥本邦の専修学校の専門課程を修了し、「専門士」の称号を有している者について、
その者の行なおうとする活動が「人文知識・国際業務」の在留資格に該当し、
就職先の職務内容と専修学校における修得内容に関連性があれば、当該在留資格
の変更が許可される。
【引用】
出入国管理のしおり
ひと目でわかる外国人の入国・在留案内
・・・【在留資格について】はこちらをクリックしてください>>
- ご相談について
- ご依頼までの流れ
- 当事務所に依頼するメリット
- 会社設立業務
- 建設業許可申請
- 宅建業免許申請
- 離婚協議書作成業務
- ビザ申請を依頼するメリット
- 用語集
- 提携事務所
- リンク集
- サイトマップ
- トップページ
- お問い合わせ
過去のブログを検索
携帯サイト
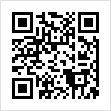
携帯電話をご利用の方は
QRコードを読み取って
モバイルサイトをご覧になれます。

当サイトは、
情報を安全に提供して頂くために、
「高度なセキュリティ」と「信頼性」で
定評のあるRapidSSLを利用しております。
プライバシーポリシー