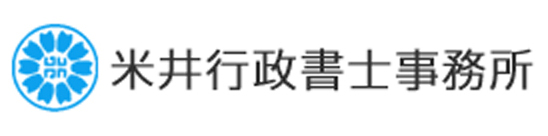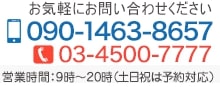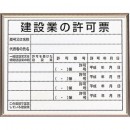帰化申請について
2013年04月29日(月)2:24 PM
◎帰化の条件
1.引き続き5年以上日本に住所を有すること
帰化申請するときまでに、引き続き5年以上日本に住所を有する者。
※生活の基盤になっていない居所は該当しません。
※就労ビザに変更している場合は、3年以上の就労経験が必要になります。
ただし、以下のような場合は上記の条件は免除されます。
(1)日本国民であった者の子で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者。
(2)日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは
母が日本で生れた者。
(3)引き続き10年以上日本に居所を有する者。
※就労経験が1年以上必要です。
(4)日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、
現に日本に住所を有する者。
(5)日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上
日本に住所を有する者。
(6)日本国民の子で日本に住所を有する者。(養子は除く)
(7)日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時に本国法に
より未成年であった者。
(8)日本の国籍を失った者で日本に住所を有する者。(日本に帰化した後、日本国籍を
失った者は除く)
(9)日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上
日本に住所を有する者。
※1回の出国期間が3ヶ月以上、または年間で半年程度の出国期間があると「引続き」と
みなされない可能性が高いかと思います。
2.20歳以上で本国法によって能力を有すること
帰化申請者は20歳以上であり、かつ本国法によって能力を有していなくてはなりません。
※両親と一緒に申請する場合は、20歳未満でも大丈夫です。
3.素行が善良であること
・税金を支払っていること
・年金を支払っていること
・交通違反がないこと(軽微な違反が数回程度なら大丈夫です)
4.自己又は生計を一にする配偶者その他親族の資産又は技能によって生計を営む事が
できること
安定した職業で安定的な収入があることを意味します。
貯金額は多いに越したことはありませんが、少なくても問題ありません。
5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
無国籍者か日本の国籍を取得することによって、それまで有していた国籍を失う者で
なければなりません。
6.日本国憲法施工の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で
破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党
その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
憲法や政府を暴力で破壊することを主張する政党や団体を結成したり、これに加入した
ことがない者でなければなりません。
帰化申請の流れ
STEP1:最寄りの法務局で相談
帰化申請の管轄は出入国在留管理局ではなく法務局になります。
法務局で相談することにより、帰化申請の要件を満たしているか、必要な書類は何かを教えて
くれます。なお、法務局へは電話で予約してから行くようにして下さい。
STEP2:必要書類の収集・作成
役所で取得するものや、本国から取り寄せるものがありますので時間と手間がかかります。
本国から取り寄せた書類で英語以外の言語の場合は日本語訳が必要です。
※翻訳者は誰でも可。(翻訳した書類に翻訳者の署名が必要です)
STEP3:住所地を管轄する法務局に書類を申請
申請者の住所地を管轄する法務局、地方法務局に書類を提出します。
書類の提出は必ず本人が出頭して行わなければなりません。
STEP4:面接
書類提出後、帰化申請者への面接があります。
提出した書類の内容を中心に質問されます。特に申請動機・生活状況・家族関係・前科・
交通違反・仕事関係について詳しく聞かれます。面接時の虚偽申告は絶対に止めましょう。
STEP5:結果通知
申請してから 結果が出るまでは概ね1年程度です。
許可されたら官報に掲載されます。その後、法務局から呼び出しがあり、法務局長より
「帰化者の身分証明書」が交付されます。必ず帰化後の氏名、本籍、生年月日等の
記載を確認して下さい。
許可後、在留カードの返納、帰化届の提出は必ず行って下さい。
万が一、不許可になった場合は面談を申し込んで不許可理由を聞いてみるのも手です。
最近の帰化許可申請者の推移はこちらをご覧下さい ⇒ 帰化許可申請者の推移
帰化に必要な書類の例
【作成する書類】
1.帰化許可申請書
2.帰化の動機書
3.履歴書
4.宣誓書
5.親族の概要を記載した書面
6.生計の概要を記載した書面
7.事業の概要を記載した書面
8.自宅勤務先等付近の略図
【官公署から取り寄せる書類】
1.本国法によって能力を有することの証明書
2.在勤証明書、給与証明書、卒業証明書、中退証明書、在学証明書
3.国籍を有する書面
4.身分関係を証する書面
5.納税証明書
6.法定代理人の資格を証する書面
7.登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
8.預貯金の残高証明書、有価証券保有証明書、不動産登記簿謄本
9.運転記録証明書
【その他の書類】
1.決算書(貸借対照表、損益計算書等)
2.確定申告書の写し
3.運転免許証などの写し
弊所の報酬額(税込)
弊所の報酬額は以下のとおりです。
お客様の状況により、価格が変動する場合がありますので、ご了承下さい。
| 帰化申請書類作成代行料 | 165,000円 |
| 1名追加につき | +55,000円 |
| 収入印紙代(行政書士業務委任契約書貼付用) | 200円 |
※別途、費用がかかる場合があります。
お問合せについて
お問合せに料金は一切かかりませんので、帰化申請について
ご不明な点がございましたら、以下の方法にてどうぞお気軽に
お問合せ下さい。
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)
TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com

LINE

WeChat
関連リンク
パスポートの認証(現在行っていません)
2013年04月16日(火)11:51 AM
■パスポートの認証とは?
海外口座の開設、海外のビザ を取得するときなどにパスポートの
を取得するときなどにパスポートの
コピーが原本と相違ないという事を行政書士や弁護士等の一定の
身分の者が書面にして証明する手続きで、通常は英語で作成され
ます。(こちらの業務は現在行っていません)
■パスポート認証の流れ
1.お問合せ
お電話・お問合せフォーム・メールにてお問合せ下さい。
TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657
お問合せフォーム
E-mail:yonei@yonei-office.com
2.必要書類の郵送
当事務所まで必要書類を送って下さい。
【書類送付先】
〒131-0032
東京都墨田区東向島3-10-9-403
米井行政書士事務所 行政書士 米井清二
【必要書類】
①パスポートのコピー(A4カラー)
②身分証明書のコピー(2点以上)
※運転免許証・健康保健証・住基カード・年金手帳など各種証明書
※一点は必ず写真付きの証明書を送って下さい。
3.報酬額のお支払
お振込み・現金書留で代金をお支払ください。
報酬額は1通5,500円です。
【振込先】
三菱東京UFJ銀行 新宿支店 普通預金
【現金書留送付先】
〒131-0032
東京都墨田区東向島3-10-9-403
米井行政書士事務所 行政書士 米井清二
4.パスポートの認証
認証書面に署名、押印して郵送にてお渡し致します。
お問合せについて
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。
TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com
関連リンク
出入国在留管理局の管轄一覧
2013年03月08日(金)1:18 PM
【東京出入国在留管理局の管轄】
| 名称 | 在留関係諸申請※1 | 在留資格認定証明書交付申請※2 |
|
東京出入国 |
東京都・千葉県・神奈川県・
埼玉県・茨城県・栃木県・ 群馬県・山梨県・新潟県・ 長野県 |
東京都・千葉県・神奈川県・ |
| 新宿出張所 | 手続は行なっていません。 | 手続は行なっていません。 |
| 立川主張所 | 東京都・山梨県・神奈川県 相模原市 |
東京都・山梨県・神奈川県 相模原市 |
| 千葉出張所 | 千葉県・茨城県 | 千葉県・茨城県 |
| 松戸出張所 | 千葉県・茨城県 | 千葉県・茨城県 |
| 水戸出張所 | 茨城県・栃木県 | 茨城県・栃木県 |
| さいたま出張所 | 埼玉県 | 埼玉県 |
| 宇都宮出張所 | 栃木県・茨城県・群馬県 | 栃木県・茨城県・群馬県 |
| 高崎出張所 | 群馬県・栃木県・埼玉県・ 新潟県・長野県 |
群馬県・栃木県・埼玉県・ 新潟県・長野県 |
| 長野出張所 | 長野県・新潟県 | 長野県・新潟県 |
| 新潟出張所 | 新潟県 | 新潟県 |
| 甲府出張所 | 山梨県・長野県 | 山梨県・長野県 |
| 成田空港支局 | 手続は行なっていません。 | 手続は行なっていません。 |
| 羽田空港支局 | 手続は行なっていません。 | 手続は行なっていません。 |
| 横浜支局 | 神奈川県 | 神奈川県 |
| 川崎出張所 | 神奈川県・東京都町田市・ 狛江市・多摩市・稲城市 |
神奈川県・東京都町田市・ 狛江市・多摩市・稲城市 |
【札幌出入国在留管理局の管轄】
| 名称 | 在留関係諸申請※1 | 在留資格認定証明書交付申請※2 |
| 札幌出入国 在留管理局 |
北海道 | 北海道 |
| 小樽港出張所 | 北海道 | 北海道 |
| 函館港出張所 | 北海道 | 北海道 |
| 釧路港出張所 | 北海道 | 北海道 |
| 千歳苫小牧出張所 | 北海道 | 北海道 |
| 稚内出張所 | 北海道 | 北海道 |
【仙台出入国在留管理局の管轄】
| 名称 | 在留関係諸申請※1 | 在留資格認定証明書交付申請※2 |
| 仙台出入国 在留管理局 |
青森県・岩手県・宮城県・
秋田県・山形県・福島県
|
青森県・岩手県・宮城県・
秋田県・山形県・福島県
|
| 仙台空港出張所 | 手続きは行っておりません。 | 手続きは行っておりません。 |
| 酒田港出張所 | 山形県・秋田県 | 山形県・秋田県 |
| 盛岡出張所 | 岩手県・青森県・秋田県 | 岩手県・青森県・秋田県 |
| 秋田出張所 | 秋田県・青森県・岩手県・ 山形県 |
秋田県・青森県・岩手県・ 山形県 |
| 青森出張所 | 青森県・秋田県・岩手県 | 青森県・秋田県・岩手県 |
【名古屋出入国在留管理局の管轄】
| 名称 |
在留関係諸申請※1 |
在留資格認定証明書交付申請※2 |
| 名古屋出入国 在留管理局 |
富山県・石川県・福井県・
岐阜県・静岡県・愛知県・
三重県 |
富山県・石川県・福井県・
岐阜県・静岡県・愛知県・
三重県 |
| 豊橋港出張所 | 愛知県 | 愛知県 |
| 四日市港出張所 | 三重県 | 三重県 |
| 浜松出張所 | 静岡県 | 静岡県 |
| 静岡主張所 | 静岡県 | 静岡県 |
| 福井出張所 | 福井県・石川県 | 福井県・石川県 |
| 富山出張所 | 富山県・岐阜県 | 富山県・岐阜県 |
| 金沢出張所 | 石川県・富山県 | 石川県・富山県 |
| 岐阜出張所 | 岐阜県 | 岐阜県 |
| 中部空港支局 | 手続きは行っておりません。 | 手続きは行っておりません。 |
【大阪出入国在留管理局の管轄】
| 名称 | 在留関係諸申請※1 | 在留資格認定証明書交付申請※2 |
| 大阪出入国 在留管理局 |
滋賀県・京都府・大阪府・
兵庫県・奈良県・和歌山県
|
滋賀県・京都府・大阪府・
兵庫県・奈良県・和歌山県
|
| 京都出張所 | 京都府・滋賀県 | 京都府・滋賀県 |
| 舞鶴港出張所 | 京都府・兵庫県 | 京都府・兵庫県 |
| 奈良主張所 | 奈良県・和歌山県 | 奈良県・和歌山県 |
| 和歌山出張所 | 和歌山県・奈良県 | 和歌山県・奈良県 |
| 大津出張所 | 滋賀県・京都府 | 滋賀県・京都府 |
| 関西空港支局 | 手続きは行っておりません。 | 手続きは行っておりません。 |
| 神戸支局 | 兵庫県 | 兵庫県 |
| 姫路港出張所 | 兵庫県 | 兵庫県 |
【広島出入国在留管理局の管轄】
| 名称 | 在留関係諸申請※1 | 在留資格認定証明書交付申請※2 |
| 広島出入国 在留管理局 |
鳥取県・島根県・岡山県・
広島県・山口県
|
鳥取県・島根県・岡山県・
広島県・山口県
|
| 福山出張所 | 広島県・岡山県 | 広島県・岡山県 |
| 下関出張所 | 山口県・島根県 | 山口県・島根県 |
| 周南出張所 | 山口県・島根県・広島県 | 山口県・島根県・広島県 |
| 広島空港出張所 | 手続きは行っておりません。 | 手続きは行っておりません。 |
| 岡山出張所 | 岡山県・鳥取県 | 岡山県・鳥取県 |
| 境港出張所 | 鳥取県・島根県 | 鳥取県・島根県 |
| 松江出張所 | 島根県・鳥取県 | 島根県・鳥取県 |
【高松出入国在留管理局の管轄】
| 名称 | 在留関係諸申請※1 | 在留資格認定証明書交付申請※2 |
|
在留管理局 |
徳島県・香川県・愛媛県・
高知県
|
徳島県・香川県・愛媛県・
高知県
|
| 松山出張所 | 愛媛県・高知県 | 愛媛県・高知県 |
| 小松島出張所 | 徳島県・香川県・高知県 | 徳島県・香川県・高知県 |
| 高知港出張所 | 高知県・徳島県 | 高知県・徳島県 |
【福岡出入国在留管理局の管轄】
| 名称 | 在留関係諸申請※1 | 在留資格認定証明書交付申請※2 |
|
在留管理局 |
福岡県・佐賀県・長崎県・
熊本県・大分県・宮崎県・
鹿児島県・沖縄県 |
福岡県・佐賀県・長崎県・
熊本県・大分県・宮崎県・
鹿児島県・沖縄県 |
| 博多港出張所 | 手続きは行っておりません。 | 手続きは行っておりません。 |
| 福岡空港出張所 | 手続きは行っておりません。 | 手続きは行っておりません。 |
| 北九州出張所 | 福岡県・大分県 | 福岡県・大分県 |
| 佐賀出張所 | 佐賀県・福岡県・長崎県 | 佐賀県・福岡県・長崎県 |
| 長崎出張所 | 長崎県・佐賀県 | 長崎県・佐賀県 |
| 対馬出張所 | 長崎県 | 長崎県 |
| 大分出張所 | 大分県・熊本県・宮崎県 | 大分県・熊本県・宮崎県 |
| 鹿児島出張所 | 鹿児島県・熊本県・宮崎県 | 鹿児島県・熊本県・宮崎県 |
| 宮崎出張所 | 宮崎県・熊本県 | 宮崎県・熊本県 |
【那覇支局の管轄】
| 名称 | 在留関係諸申請※1 | 在留資格認定証明書交付申請※2 |
| 那覇支局 | 沖縄県 | 沖縄県 |
| 那覇空港出張所 | 手続きは行っておりません。 | 手続きは行っておりません。 |
| 嘉手納出張所 | 沖縄県 | 沖縄県 |
| 宮古島出張所 | 沖縄県宮古島市・宮古郡 | 沖縄県宮古島市・宮古郡 |
| 石垣港出張所 | 沖縄県石垣市・八重郡 | 沖縄県石垣市・八重郡 |
※1 「在留関係諸申請」について
原則として、申請人である外国人の住所地を管轄する地方局又は支局若しくは分担する
出張所において手続できます。
※2 「在留資格認定証明書交付申請」について
原則として申請代理人となる受入れ機関の所在地や親族の住所地を管轄する地方局
又は支局。なお、一部の在留資格については、在留資格認定証明書交付申請を
取り扱っていない出張所がありますので、ご注意ください。
※3 ご不明な点がある場合は、最寄の地方入国管理局、支局又は出張所にお問合せ下さい。
お問合せについて
お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せ下さい!
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)
TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com

LINE

WeChat
関連リンク
イーストコア曳舟商店会
2013年02月24日(日)7:52 PM
| Cafe Sucre | 自家焙煎珈琲専門店 |
| リスクサーベイ | あなたのライフステージにあった保険のかけ方を 提案いたします。 |
建設業許可取得後の手続
2013年01月25日(金)3:27 PM
許可を取得した後も以下のように様々な手続が必要となりますので、
忘れないように手続をして頂き、ご不明な点がございましたら、
当事務所までお気軽にご相談下さい。
1.決算報告届
建設業許可を受けている事業者は、毎年事業年度終了後
4か月以内に 決算報告に関する
決算報告に関する
届出書を提出することが義務付けられています。
この届出は税務署に届けた決算報告書とは別の物で、
建設業法に基づいたものでなくてはなりません。
<注意>
①届出書の提出がない場合、罰則規定があります。
②期日の到来している決算報告の届出がされていない場合は、更新申請、般特新規申請、
業種追加申請はできません。
【届出書類】
①変更届出書(決算報告の表紙)
②工事経歴書
③直前3年の各事業年度における工事施工金額
④財務諸表
⑤事業報告書(書式自由)
⑥納税証明書
【法人】法人事業税納税(課税)証明書(都税事務所発行)
【個人】個人事業税納税(課税)証明書(都税事務所発行)
⑦使用人数の届出書(変更があった場合のみ)
⑧使用人の一覧表(変更があった場合のみ)
⑨定款(変更があった場合のみ)
2.更新申請
許可の有効期限は5年間です。
有効期限後も引続き建設業を営む場合は、許可の満了する日の2ヵ月前から30日前までに更新
の申請をしなければなりません。
※許可更新に必要な書類はこちらをご覧ください。
3.業種追加
既に許可を貰っている業種以外の許可を貰う場合の手続です。
業種追加に必用な書類は新規に建設業許可を取得する場合とほぼ同じです。
建設業許可は、それぞれ独立した許可となっていますので、業種追加することにより、今まで
持っていた許可と新しく取得した許可の更新日がずれてしまいます。
そのような場合は、更新日を一本化することができます。
※業種追加に必要な書類はこちらをご覧ください。
4.変更・廃業届け
許可を受けた後、下記届出事項に変更があった場合は、その届出期間内に届出書を提出
しなければなりません。なお、届出書が提出されていない場合、罰則規定がありますので、
必ず提出するようにしてください。
【変更届】
| 届出事項 | 提出方法 | 届出期間 |
| 商号の変更 | 郵送可 | 変更後30日以内 |
| 営業所の名称変更 | 郵送可 | 変更後30日以内 |
| 営業所の所在地・電話番号・郵便番号の変更 | 郵送可 | 変更後30日以内 |
| 営業所の新設・廃止 | 郵送不可 | 変更後30日以内 |
| 営業所の業種追加・業種廃止 | 郵送不可 | 変更後30日以内 |
| 資本金額の変更 | 郵送可 | 変更後30日以内 |
| 役員・代表者(申請人)の変更 | 郵送可 | 変更後30日以内 |
| 支配人の変更 | 郵送不可 | 変更後30日以内 |
| 建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更 | 郵送不可 | 変更後2週間以内 |
| 経営業務の管理責任者の変更 | 郵送不可 | 変更後2週間以内 |
| 専任技術者の変更 | 郵送不可 | 変更後2週間以内 |
| 国家資格者等・管理技術者の変更 | 郵送可 | 速やかに提出 |
※変更届に必要な書類はこちらをご覧ください。
【廃業届】
| 届出事項 | 提出方法 | 届出期間 |
| 全部廃業 | 郵送可 | 廃業後30日以内 |
| 一部廃業 | 郵送不可 | 廃業後30日以内 |
※廃業届に必要な書類はこちらをご覧ください。
5.住宅瑕疵担保履行法に基づく届出
請負人として発注者(宅地建物取引業は除く)に新築住宅を引渡す建設業者は、住宅品質確保
法に基づく10年間の瑕疵担保責任履行のための資力確保措置(保証金の供託又は保険への加入)
を講じることが義務つけられています。
また、その措置の状況について年2回の基準日(毎年3月31日、9月30日)から3週間以内に
許可行政庁である東京都への届出が必要です。
届出を行なわない場合、新たな新築住宅の請負締結が禁止されるほか、履行法に基づく罰則、
建設業法に基づく監督処分の対象になります。
各種手続の申請手数料と当事務所の報酬額
建設業許可取得後に必要な手続の申請手数料と当事務所への報酬額は以下の通りです。
| 業務名 | 申請手数料 | 報酬額 |
| 決算報告届 | - | 38,500円~ |
| 更新届(知事)一般 | 50,000円 | 77,000円~ |
| 更新届(知事)特定 | 50,000円 | 88,000円~ |
| 更新届(大臣)一般 | 50,000円 | 110,000円~ |
| 更新届(大臣)特定 | 50,000円 | 132,000円~ |
| 業種追加届(知事)一般 | 50,000円 | 77,000円~ |
| 業種追加届(知事)特定 | 50,000円 | 77,000円~ |
| 業種追加届(大臣)一般 | 50,000円 | 110,000円~ |
| 業種追加届(大臣)特定 | 50,000円 | 110,000円~ |
| 変更届(役員) | - | 22,000円~ |
| 変更届(経営業務の管理責任者・専任技術者) | - | 55,000円~ |
※お客様の状況により、上記金額よりも安くなるケースや高くなるケースがございます。
※別途実費(申請時の交通費等)がかかります。
まずはお気軽にお問合せください
当事務所では建設業許可を取得する際の書類作成、
申請書類の提出代行、それらに伴うご相談を承っております。
お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法で
お気軽にお問合せください!
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。
TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com
関連リンク
経営審査事項とは
2013年01月16日(水)3:42 PM
公共工事(国や地方公共団体が発注する工事)を発注者から直接請負う場合、経営審査事項を
必ず受けなければなりません。
公共工事とは以下のような施設などを作る工事と規定されています。
| 1 | 上下水道、港湾施設、飛行場、砂防用工作物、ダム、堤防、道路、鉄道など |
| 2 | 学校、研究所、消防施設、試験場など |
| 3 | 電気事業用施設、ガス事業用施設 |
| 4 | 公営住宅、公団住宅 |
上記、公共工事の契約は、ほとんど入札制度となっています。
また、公共工事は税金で運営されているため、民間工事以上に適正な施行の確保のため、
2つの条件が要求されます。
条件1:技術者や財務基盤、工事実績などに関して一定基準を充たすこと。
条件2:公共工事を発注する国や都道府県市町村などが独自で工事成績や工事経歴を点数化
して、受注できる工事の範囲を決めることです。
点数によって「S・A・B・C・D」などと格付けされます。
経営審査事項の流れと審査項目
経営審査事項の大まかな流れは以下の通りです。
1.経営状況分析審査
建設業業者 ⇒ 登録経営状況分析機関
2.経営状況分析結果通知書の送付
登録経営状況分析機関 ⇒ 建設業者
3.経営事項審査申請
建設業業者 ⇒ 国土交通大臣または都道府県知事
4.経営規模等評価結果通知書および総合評定値通知書
国土交通大臣または都道府県知事 ⇒ 建設業業者
審査項目は以下の6つに大別されます。
【X1】工事種類別年間平均改正工事高の評点
【X2】自己資本の額並びに建段業に従事する職員数の評点
【Y】経営規模の評点
【Z】建設業の種類別技術職員数
【W】その他の審査項目の評点
【P】総合評定値
まずはお気軽にお問合せください
当事務所では建設業許可を取得する際の書類作成、
申請書類の提出代行、それらに伴うご相談を承っております。
お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法で
お気軽にお問合せください!
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。
TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com
関連リンク
建設業許可取得に必要な書類
2012年12月30日(日)6:19 PM
新規で建設業許可を取得する場合に必要な書類は以下の通りとなっています(東京都の場合)。
(1)建設業許可申請書類、添付書類一覧(別とじ書類は(2)参照)
| 綴込順 | 様式番号 | 提出書類 | 新規 | 摘要 |
| 1 | 様式第一号 | 建設業許可申請書 | ◎ | |
| 2 | 許可通知書の写し | 〇 | 許可換え新規申請時 | |
| 別紙二 | 営業所一覧表 | ◎ | ||
| 別紙三 | 収入印紙等貼り付け用紙 | ◎ | 大臣許可のみ必要 | |
| 3 | 二号 | 工事経歴書(直前1年分) | ◎ | 実績なしでも作成 |
| 4 | 三号 | 直前3年の各事業年度に おける工事施工金額 |
◎ | 実績なしでも作成 |
| 5 | 四号 | 使用人数 | ◎ | |
| 6 | 六号 | 誓約書 | ◎ | |
| 7 | 七号 | 経営業務の管理責任者 証明書 |
◎ | 証明者別に作成 |
| 8 | 八号 | 専任技術者証明書 | ◎ | |
| 9 | 修業(卒業)証明書の写し | 〇 | ||
| 資格認定証明書の写し | 〇 | |||
| 九号 | 実務経験証明書 | 〇 | 証明者別に作成 | |
| 十号 | 指導監督実務経験証明書 | 〇 | 特定建設業のみ | |
| 10 | 十一号の二 |
国家資格者等・監理技術者
一覧表 |
〇 | |
| 11 | 定款 | ◎ | 法人のみ | |
| 12 | 十五、十六 十七、十七号 の二十七号 の三 |
財務諸表(法人用) | ◎ | 新規設立会社の場合は 開始貸借対照表 |
| 十八、十九号 | 財務諸表(個人用) | ◎ | 新規開業の場合は残高 証明書 |
|
| 13 | 登記事項証明書 | ◎ | 発行後3か月以内のもの | |
| 14 | 二十号 | 営業の沿革 | ◎ | |
| 15 | 二十号の二 | 所属建設業団体 | ◎ | 該当なしでも作成 |
| 16 | 納税証明書(法人)知事 | ◎ | 法人事業税 | |
| 納税証明書(法人)大臣 | ◎ | 法人税 | ||
| 納税証明書(個人)知事 | ◎ | 個人事業税 | ||
| 納税証明書(法人大臣) | ◎ | 申告所得税 | ||
| 17 | 二十号の三 | 健康保険の加入状況 | ◎ | 証明資料が必要です |
| 18 | 二十号の四 | 主要取引金融機関名 | ◎ | 該当なしでも作成 |
(2)建設業許可申請書類、添付書類一覧(別とじ用)
| 綴込順 | 様式番号 | 提出書類 | 新規 | 摘要 |
| 1 | 別とじ表紙 | ◎ | ||
| 2 | 役員の一覧表 | ◎ | 法人のみ | |
| 3 | 十一号 |
建設業法施行令第3条に
規定する使用人の一覧表 |
〇 | 支配人を置いた場合 及び従たる営業所を 記入したもののみ必要 |
| 4 | 十二号 | 許可申請者の略歴書 | ◎ | 監査役は不用 |
| 5 | 十三号 |
建設業法施行令第3条に
規定する使用人の略歴書 |
〇 | 支配人を置いた場合 及び従たる営業所を 記入したもののみ必要 |
| 6 | 十四号 | 株主(出資者)調書 | ◎ | 法人のみ 該当なしでも作成 |
(3)確認資料等
| 綴込順 | 関連する様式 | 提出書類 | 新規 | 摘要 |
| 1 | 預金残高証明書 | 〇 | 自己資本が500万円 未満の場合 |
|
| 2 | 印鑑証明書 | 〇 | 自己証明する場合 | |
| 3 | 様式第七号関係 | 経営業務の管理責任者 の確認資料 |
◎ | 詳しくはお問合せ下さい |
| 4 | 八号、十号関係 |
専任技術者の確認資料
(指導監督的実務経験 確認資料含む) |
◎ | 詳しくはお問合せ下さい |
| 5 | 営業所の確認資料 | ◎ | 詳しくはお問合せ下さい | |
| 6 | 十一号関係 | 建設業法施行令第3条 に規定する使用人の 確認資料 |
◎ | 詳しくはお問合せ下さい |
| 7 | 十一号の二関係 | 国家資格者等・監理技術 者の確認資料 |
〇 | 詳しくはお問合せ下さい |
| 8 | 登記されていないことの 証明書 |
◎ | 役員全員、個人事業主、 建設業法施行令第3条に 規定する使用人について 提出 |
|
| 9 | 身分証明書 (区市町村長の証明書) |
◎ | 役員全員、個人事業主、 建設業法施行令第3条に 規定する使用人について 提出 |
|
| 役員等氏名一覧表 | ◎ |
◎印 : 必ず提出する書類
〇印 : 必要に応じて提出する書類
まずはお気軽にお問合せください
当事務所では建設業許可を取得する際の書類作成、
申請書類の提出代行、それらに伴うご相談を承っております。
お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて、
どうぞお気軽にお問合せください!
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。
TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com
関連リンク
弁理士
公認会計士
2012年10月08日(月)11:41 AM
◆公認会計士◆中小企業診断士◆税理士の資格を持つ所長が全面サポート!
社長ご自身による創業計画書と資金繰り表の作成を支援いたします。
エース会計事務所 公認会計士・税理士 会社設立道場 東京都中央区
東京駅前・中央区八重洲の会計事務所です。
お受けしています。
スピーディで優しい会社の設立登記と、節税を尽くして、
確定申告が自慢の事務所です。社長一人の会社から上場会社まで、
させて頂きます。
その他のビザ手続き
2012年09月09日(日)10:50 AM
■ビザの更新
定められた在留期間を超えて日本に滞在を希望する場合、「在留期間更新許可申請」を入国
管理局にしなくてはなりません。
この手続きは、ビザの有効期限の3か月前からできますので、余裕を持って早めに手続きを
するようにしてください。
※ビザの有効期限までに在留期間更新の許可が下りてないとけないという訳ではなく、有効
期限までに申請し、受理されれば結果がでるまで、もしくは有効期限日の翌日から2か月の
どちらか早い方まで滞在することができます(許可が下りればそのまま滞在できます)。
【手続きの流れ】
STEP1:必要書類の収集、申請書等の作成
申請人または行政書士等が必要書類の収集及び申請書等の作成
⇓
STEP2:入国管理局へ申請書類の提出
居住地を管轄する入国管理局へ申請書等の書類を提出します。
⇓
STEP3:結果の通知
標準審査期間は2週間~1か月です。
⇓
STEP4:結果通知
許可の場合は、パスポート・在留カード・許可通知ハガキ・申請手数料納付書
(4,000円の収入印紙を貼付)を持って許可を受けます。
【必要書類の例】
1.在留期間更新申請書 1通
2.写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
3.パスポート及び在留カード
4.身元保証書
不法滞在(オーバーステイ)について
不法滞在(オーバーステイ)とは、在留期間を過ぎて日本に滞在することや、入国許可を持た
ずに日本に入国することをいいます。
原則的に不法滞在の場合、退去強制となりますが、特別な理由がある場合、法務大臣が特別
に在留を許可する在留特別許可という制度があります。
なお、不法滞在で本国に退去強制になった場合、一定期間は日本に再上陸できなくなります。
一定期間が過ぎれば再上陸できる条件は整いますが、必ずしも入国を保証するものではあり
ません。
【入国拒否期間】
| 強制送還歴がなく、摘発などにより強制送還された者 | 5年間 |
| 過去に強制送還がある者 | 10年間 |
| 出国命令により出国した者 | 1年間 |
【不法滞在の罰則】
罰金の併科
■無許可資格外活動の罪
1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは200万円以下の罰金、又は懲役若しくは禁錮と
罰金の併科
■不法就労助長の罪
【在留特別許可に必要な書類の例】
1.陳述書
2.申告者のパスポート
3.外国人登録証明書(持っている場合)
4.身分証明書(持っている場合)
5.婚姻を証明する書類
6.配偶者の戸籍謄本
7.配偶者の住民票
8.配偶者の源泉徴収表
9.自宅の賃貸契約書(賃貸の場合)
10.自宅の登記簿(持ち家の場合)
11.写真(縦5㎝×横5㎝)
12.お二人のスナップ写真
13.残高証明書等、資産状況を証明する書類
14.その他の資料
(出生証明書、日本人配偶者の履歴書、自宅周辺の地図など)
上記は最低限必要な書類です。審査の過程で別途書類が必要になる場合があります。
不法滞在(オーバーステイ)について詳しくはこちらをご覧下さい。
高度専門職ビザ
高度人材認定による優遇制度とは、経済成長や新たな需要と雇用の創造に資することが期待される高度な能力や資質を有する外国人(高度人材)の受入れを促進するため、ポイントの合計が一定点数(70点以上)に達した者を「高度人材外国人」とし、出入国管理上の優遇措置を講ずる制度です。
【高度人材認定の優遇措置】
(1)複合的な在留活動の許容
(2)5年の在留期間の付与
(3)永住許可要件の緩和
※概ね5年で許可の対象となり、4年6か月~申請ができるようになります。
(4)入国・在留手続きの優先処理
(5)高度人材配偶者の就労
(6)一定条件下での両親の帯同許可
(7)一定条件下での家事使用人の許容
■申請手数料:4,000円(許可時にかかります)
■標準審査期間:原則1週間
高度人材認定について詳しくはこちらをご覧下さい。
当事務所の報酬額
当事務所の報酬額(税抜)、実費額は以下の通りです。
【報酬額】
| ビザの更新 | 38,500円~ |
| 在留特別許可(不法滞在の場合) | 330,000円~ |
| 高度専門職 | 88,000円~ |
【実費額】
| 申請手数料(ビザの延長・高度専門職) | 4,000円 |
| 申請手数料(就労資格証明書) | 900円 |
※上記以外に実費がかかる場合があります。
お問合せについて
お問合せに料金は一切かかりませんので、ビザについてご不明な点が
ございましたら、以下の方法でどうぞお気軽にお問合せ下さい!
- ご相談について
- ご依頼までの流れ
- 当事務所に依頼するメリット
- 会社設立業務
- 建設業許可申請
- 宅建業免許申請
- 離婚協議書作成業務
- ビザ申請を依頼するメリット
- 用語集
- 提携事務所
- リンク集
- サイトマップ
- トップページ
- お問い合わせ
過去のブログを検索
携帯サイト
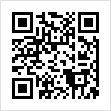
携帯電話をご利用の方は
QRコードを読み取って
モバイルサイトをご覧になれます。

当サイトは、
情報を安全に提供して頂くために、
「高度なセキュリティ」と「信頼性」で
定評のあるRapidSSLを利用しております。
プライバシーポリシー