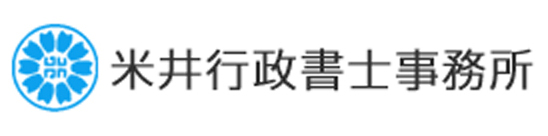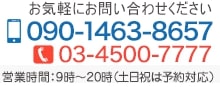韓国人との結婚手続き
2014年02月22日(土)4:43 PM
韓国人の方と結婚する場合、日本側で先に婚姻手続きをする方法と、韓国側で先に手続きを
先にする方法の二通りがあります。 まずは日本で先に婚姻手続きをする方法についてご説明
致します。
日本で先に婚姻手続きをする場合
1.日本の役所に婚姻届を提出
【日本での婚姻に必要な書類の例】
婚姻届(成人二名の証人が必要です)
日本人の戸籍謄本(本籍地以外に婚姻届を提出する場合)
パスポート
在留カード
基本事項証明書(日本語訳文が必要です)翻訳者の住所、署名、押印が必要です。
家族関係証明書(日本語訳文が必要です)翻訳者の住所、署名、押印が必要です。
婚姻関係証明書(日本語訳文が必要です)翻訳者の住所、署名、押印が必要です。
※上記は一例です。届出をする役所によって書類が変わる場合がありますので、
必ず届出予定の役所にご確認下さい。
2.日本で婚姻が成立後、在日韓国大使館や韓国の役所で日本での婚姻を届出
【韓国での婚姻に必要な書類の例】
韓国の婚姻届
日本人の方の戸籍謄本(婚姻の事実記載済み)又は婚姻届受理証明書と韓国語訳文
(翻訳者の住所、署名、押印が必要です)
日本人の方の住民票と韓国語訳文(翻訳者の住所、署名、押印が必要です)
韓国人の方の基本証明書
韓国人の方の家族関係証明書
韓国人の方の婚姻関係証明書
韓国人の方の公的身分証明書(パスポートを全コピー)
※上記は一例です。届出をする役所によって書類が変わる場合がありますので、
必ず届出予定の役所にご確認下さい。
韓国で先に婚姻手続きをする場合
1.韓国の役所において婚姻届を提出
【必要書類の例】
日本人の方の婚姻要件具備証明書
日本人の方の住民票
日本人の方の戸籍謄本2通(1通はコピー可)
日本人の方の印鑑
日本人の方のパスポート
韓国人の方の婚姻証明書
韓国人の方の基本証明書
韓国人の方の家族関係証明書
韓国人の方の印鑑
韓国人の方のパスポート
※日本語のものは韓国語への訳文が必要です。
※上記はあくまでも例なので、必ず届出先機関に確認して下さい。
2.日本の役所又は在韓国日本大使館に婚姻届を提出
韓国での婚姻が成立後、日本の役所又は在韓国日本大使館に婚姻届を提出します。
【必要書類の例】
婚姻届1通
韓国での婚姻の事実が記載された韓国人の方の婚姻関係証明書とその
和訳文 各1通
日本人の方の戸籍謄本 1通(本籍地以外の場合)
日本人の方の公的身分証明書
日本人の方の印鑑
韓国人の方のパスポート
※上記はあくまでも例なので、必ず届出先機関に確認して下さい。
ビザ申請に必要な書類
下記の書類はあくまでも例です。審査の過程で下記書類以外にも必要となる場合が
ございますので、ご了承下さい。
1.外国から配偶者を呼ぶ場合
(1)在留資格認定証明書交付申請書 1通
(2)写真(縦4cm×横3cm) 1葉
(3)配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通
(4)申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
(5)配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
(6)配偶者(日本人)の身元保証書 1通
(7)配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
(8)質問書 1通
(9)スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)2~3葉
(10)392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒
2.現在、日本に在留している外国人の方がビザを変更する場合
(1)在留資格変更許可申請書 1通
(2)写真(縦4cm×横3cm) 1葉
(3)配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通
(4)申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
(5)配偶者(日本人)の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
(6)配偶者(日本人)の方の身元保証書 1通
(7)配偶者(日本人)の方の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
(8)質問書 1通
(9)スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)2~3葉
(10)パスポート 提示
(11)在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
その他の事項
■審査期間
外国から配偶者を呼ぶ場合:約1か月~3か月。
日本在住の方と結婚してビザを変更する場合:約2週間~1か月となります。
なお、あくまでも目安の期間となっております。
■申請手数料
外国から配偶者を呼ぶ場合:無料
日本在住の方と結婚してビザを変更する場合:4,000円
※入国管理局に支払う申請手数料です。
■注意点
*ビザの変更申請中に日本から出国すると、変更手続きは無効となります。
*短期滞在ビザ(観光ビザ)で配偶者が日本滞在中に在留資格認定証明書交付申請をする
事は可能です。 その場合、配偶者の日本出入国は可能です。
弊所の報酬額(税抜)
下記金額は目安です。お客様の状況により金額に変動がある場合がございますので、
お問合せ下さい。
| 業務内容 | 金額 |
| 外国から配偶者を呼ぶ場合 | 80,000円 |
| 結婚ビザに変更する場合(現在日本滞在中の方) | 80,000円 |
| 申請書類のチェック及びアドバイス | 40,000円 |
※別途、実費がかかります。
お問合せについて
お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せ下さい!
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。
TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com
毒物劇物販売業登録
2014年02月18日(火)4:15 PM
毒物や劇物を製造・輸入・販売するには届出が必要になり、毒物、劇物を製造・輸入する
には厚生労働大臣へ届出、販売をするには保健所等への届出が必要になります。
当事務所では面倒な毒物劇物販売業登録を専門家が代行致します。
毒物・劇物とは?
「毒物」
毒物及び劇物取締法(以下、「法」という。)別表第一、同法指定令第一条に掲げる物で、
薬事法に規定される医薬品及び医薬部外品以外のものをいいます。
「劇物」
法別表第二、指定令第ニ条に掲げる物で、薬事法に規定される医薬品及び医薬部外品以外
のものをいいます。
「特定毒物」
毒物で、法別表第三、指定令第三条に掲げるものをいいます。
毒物劇物営業者とは?
毒物劇物営業者とは以下の登録を受けた者の事を言います。
・毒物劇物販売業者
| 営業内容 | 業種 | 制限 | 申請先 |
| 毒物又は劇物の販売 授与又はその為の貯蔵 |
一般販売業 | 販売の品目制限なし | 保健所長 |
| 毒物又は劇物の販売 授与又はその為の貯蔵 |
農業用品目販売業 | 毒物及び劇物取締法規則第4条 の2に規定する別表第一に掲げ るもののみ取り扱う場合 |
保健所長 |
| 毒物又は劇物の販売 授与又はその為の貯蔵 |
特定品目販売業 | 毒物及び劇物取締法規則第4条 の3に規定する別表第二に掲げ るもののみ取り扱う場合 |
保健所長 |
・毒物劇物製造者
| 営業内容 | 業種 | 申請先 |
| 毒物又は劇物の製造(合成、混合、希釈、 小分け等)製造した毒物又は劇物の毒物 劇物営業者に対する販売 |
原体の製造を行う業者 | 関東信越厚生局長 |
| 毒物又は劇物の製造(合成、混合、希釈、 小分け等)製造した毒物又は劇物の毒物 劇物営業者に対する販売 |
原体の小分け、製剤の 製造を行う業者 |
都道府県知事 |
・毒物劇物輸入業者
| 業務内容 | 業種 | 申請先 |
| 毒物又は劇物の輸入 輸入した毒物又は劇物の毒物劇物営業者 に対する販売 |
原体のみ又は原体と製剤 の輸入業者 |
関東信越厚生局長 |
| 毒物又は劇物の輸入 輸入した毒物又は劇物の毒物劇物営業者 に対する販売 |
製剤のみを輸入する業者 | 都道府県知事 |
※原体・製剤とは
原体とは、原則として化学的純品を指すものですが、製造過程等において生じる不純物を
含むもの、あるいは純度に影響のない程度に香りをつけ又は着色したものは原体と解さ
れます。
製剤とは、毒物又は劇物の効果的利用を図るため、希釈、混合等一定の加工を施されているものをいいます。
ただし、単なる粉砕、成型等原体の組成に影響しない物理的方法により製品化されて
いるものは製剤とはみなさず、原体と判断します。
新規毒物劇物販売業登録について
毒物劇物販売業登録が必要な事例、手続きの流れ、必要書類は以下の場合です。
■登録が必要な場合
1.新規に毒物劇物を販売する場合
2.法人の合併・分割などで、開設者が変わる場合
3.店舗が移転し、所在地が変わる場合(単なる住居表示の変更を除く)
4.有効期間が切れ、更新申請を行わなかった場合
5.店舗を全面改築する場合
■手続きの流れ
STEP1:営業所を管轄する保健所へ構造設備等の事前相談
↓
STEP2:申請及び受付
↓
STEP3:立入調査
↓
STEP4:内容調査
↓
STEP5:登録
■毒物劇物販売業新規登録申請に必要な書類例
| 書類名 | 提出部数 | 備考 |
| 登録申請書 | 1部 | |
| 登録手数料 | 管轄地による | 多摩地区及び諸島の場合16,900円 その他の地区は管轄する保健所に問合せ。 |
| 営業所の平面図 | 1部 | 伝票操作のみを行う販売業者で現物を保管 しない場合は不要 |
| 営業所の概要図 | 1部 | |
| 営業所付近の 見取り図 |
1部 | |
| 登記簿謄本 (法人のみ) |
1部 | 法人の目的の中に、毒物劇物の販売業務に 該当するものがあること。又、6か月以内に 発行されたものであること。 |
| 取扱責任者設置届 | 1部 | 資格は、法第8条第1項の第何号に該当 するかを記載します。 第1号:薬剤師 第2号:応用化学修了者 第3号:試験合格者 (一般、農業用、特定品目の区別も記載) |
| 資格証明書 (毒物劇物取扱責任者) |
1部 | 薬剤師:薬剤師免許証の写し(本証を持参) 応用化学修了者:卒業証明書又は卒業証書 の写し(本証を持参) (規定学部学科以外のときは、単位 履修証明書) 試験合格者:合格証の写し(本証を持参) |
| 証書 (毒物劇物取扱責任者) |
1部 | 雇用関係を証明する証書 |
| 診断書 (毒物劇物取扱責任者) |
1部 | 診断年月日から3か月以内のもの |
| 宣誓書 (毒物劇物取扱責任者) |
1部 | 取扱責任者が宣誓します。 |
※上記はあくまでも例です。詳しくは管轄の保健所にお問合せ下さい。
当事務所の報酬額
お客様の状況により、金額が変動する場合がございますので、ご了承下さい。
| 業務名 | 金額 | 備考 |
| 毒物劇物販売業者登録 | 108,000円 | |
| 収入印紙代 | 200円 | 当事務所と契約書を取り交わす際に 必要となります。 |
お問合せ
お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法でお気軽に
お問合せください!
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは時間お問合せ可能です。
TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com
お問合せフォーム
関連リンク
ベトナムビザの取得
2014年02月08日(土)10:46 PM
外国人がベトナムで働くほとんどの場合、ビザと労働許可証が必要になります。
ビザはベトナムに入国・滞在するために必要な証明書で、日本人の場合14日を超えて滞在
する場合、ビザの取得が必要になります。
一方、労働許可証は外国人がベトナムでの就労を認める許可証で、ベトナムで働く全ての
外国人に取得義務があります。(労働許可証の取得代行は行なっておりません。)
ベトナムビザについて
日本人の場合、14日までの滞在はビザは必要ありません。(観光又は商用)
ビザには1回限り有効な「シングル」、複数回入国可能な「マルチ」ビザがあり、期間は
最長で12か月となっております。
現時点で日本で取得できる商用ビザの最長期間は3か月です。
【主なビザの種類】
A1:党、国会、大統領、政府、大臣、人民委員会などが招聘するミッションの正式なメンバー
と同行する家族、使用人
A2:外国の代表機関のメンバー、同行する家族、使用人
A3:外国の代表機関で 働く者、および当該機関のメンバーを訪問する者
B1:最高人民検察院、最高人民裁判所、中央省庁、同格の政府機関で働く者
B2:政府機関が許可書を発給した投資案件を実施する者
B3:ベトナム資本の企業で働く者
B4:外国の組織、企業などの駐在員事務所、支店で働く者
C1:観光で入国する者
C2:他の目的で入国する者
● 一時在留許可証(テンポラリー・レジデンス・カード)
1年以上ベトナムに滞在する外国人は、一時在留許可証を取得することができます。
一時在留許可証の有効期間は最長3年ですが、労働許可証取得対象者は、労働許可証の
期限内での取得となります。
なお、一時在留許可証の有効期間中はビザの取得が免除されます。
ビザ取得に必要な書類
1.申請書 1部
ベトナム大使館のHP、もしくはベトナム大使館で貰うことができます。
また、当サイトからもダウンロード可能です。
2.パスポート
申請時に3か月以上の残存期間が必要です。
3.写真 1葉
縦4㎝×横3㎝
4.在留カード(外国籍の方)
5.申請代金及び報酬額
報酬額は当事務所に依頼したときのみです。
ベトナムビザ取得の流れ
下記は当事務所に依頼した場合です。
一般的な取得手続きとは異なりますのでご了承下さい。
STEP1:お問合せ
下記問合せ方法にて、お問合せ下さい。
TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com
お問合せフォーム
STEP2:申請書の作成(お客様)
申請書をダウンロードして頂き、お客様の方でご記入下さい。
費用はかかりますが、申請書をこちらで作成する事も可能ですので、ご相談下さい。
※申請書については、「駐日ベトナム社会主義共和国大使館」のページをご覧下さい。
STEP3:必要書類のご郵送
申請書、パスポートをご郵送下さい。
なお、パスポートにカバーをつけてる人は外してお送り下さい。
STEP4:代金のお振込み
当事務所の指定する口座に代金をお振込み下さい。
お支払い及び申請書等の到着を確認してから業務に着手致します。
※お振込先口座は、ご依頼を頂いた段階でお知らせ致します。
STEP5:ベトナム大使館へビザの申請
原則、ビザは即日発行されます。(発行まで時間がかなりかかります)
なお、後日郵送で受取る事も可能です。
ビザを取得したらお客様にメールかお電話でご連絡致します。
STEP6:ビザ及びパスポートをお客様に郵送
ビザを取得した日、もしくは取得日の翌日にレターパックにてお客様に
ご郵送致します。
ベトナムビザ取得料金
下記金額には、ベトナムビザ取得費用及び当事務所の報酬額を含んでいます。
| ビザの種類 | 有効期間 | 金額 |
| シングル(観光) | 30日 | 22,000円 |
| 90日 | 33,000円 | |
| シングル(ビジネス) | 30日 | 33,000円 |
| 90日 | 55,000円 | |
| マルチ(ビジネス) | 90日 | 88,000円 |
※別途、取得時交通費及び書類郵送代がかかります。
※業務依頼後のキャンセルはできませんので、ご了承下さい。
労働許可証について
ベトナムの法律に基づき設立された企業、機関、組織で働く外国人労働者は、労働許可証
(ワークパーミット)を取得しなければなりません。
ただし、下記に該当する場合は、労働許可証の取得を免除されます。
(a) 3ヶ月未満の期限で働くために、ベトナムへ入国する外国人
(b) 2人以上有限会社の出資者である外国人
(c) 1人有限会社の所有者である外国人
(d) 株式会社の取締役会の役員である外国人
(e) 役務を提供するために入国する外国人(i)
(f) ベトナム国内において就労するベトナム人または外国人専門家が、修理、対応できない
事業、生産に影響を与える恐れがあり、緊急を要する技術的事象の解決を目的に入国
する外国人(3ヶ月以上の場合は、3ヶ月を終えた時点で労働許可証の申請が必要)
(g) ベトナム司法省より弁護士業の資格を受けた外国人弁護士
(h) 外国の非政府組織(NGO)の駐在員事務所、プロジェクト事務所の代表者を委任された
外国人
(i) 世界貿易機関(WTO)加盟時に公約した、経営、情報、建設、流通、教育、環境、金融、
医療、観光、文化・娯楽、運輸の11のサービス分野に属する企業で、社内異動で赴任する
外国人
(j) ベトナムと外国の担当機関との間で締結した、政府開発援助(ODA)に関する国際条約の
規定または合意に基づき、ODA資金を使用するプログラム、プロジェクトの研究、建設、
審査決定、追跡評価、管理、実施の業務のため、専門的及び技術的な問題について相談
サービスを提供する、またはその他の任務を実行するためにベトナムに入国する外国人
(k) 法律の規定に基づき、ベトナムで報道、プレス活動の許可書を外務省より発給された
外国人
(l) 首相府の規定に基づくその他の場合
※労働許可証の取得代行は取り扱っておりません。
お問合せ
お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せ下さい!
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)
TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com
お問合せフォーム
化粧品・医薬部外品業の許可更新
2014年02月05日(水)3:57 PM
化粧品業(製造・製造販売業)、医薬部外品(製造・製造販売業)の許可をお持ちの方は
5年ごとに許可の更新が必要になります。
許可期限までに更新手続きをしないと営業を続ける事ができなくなりますので、期限内に
必ず許可更新をするようにして下さい。
当事務所では、お忙しい事業主様に代わり行政書士が責任を持って許可更新を代行致します
ので、どうぞお気軽にお問合せ下さい。
許可更新手続きについて
化粧品業及び医薬部外品業の許可更新手続に必要な書類の提出は、概ね有効期限の約2か月前
です。(2か月以上前に申請しても受付けてもらえます)
申請書等の提出部数は1部(別途、申請者控1部の計2部作成)となっております。
申請は原則FD申請(専用ソフトでの申請)となっておりますが、書面での申請も可能です。
■化粧品・医薬部外品・医薬品製造販売業の許可更新に必要な書類
1.申請書(FD申請様式又は書面申請様式)
2.製造販売業許可証(原本)
■化粧品・医薬部外品・医薬品製造業許可更新に必要な書類
1.申請書(FD申請様式又は書面申請様式)
2.製造業許可証(原本)
3.製造所の平面図
作業室、貯蔵室、試験検査室等の場所、室名を明記し、その寸法を記載して下さい。
また、製造管理者の座席等を明示して下さい。
4.製造所の配置図
同一フロア内に複数の事業所がある場合、同一地番内に複数の建物がある場合。
5.保管庫等の立体図
貯蔵設備として棚やロッカーを使用している場合は、その寸法を記載。
6.製造設備器具一覧表
7.試験検査器具一覧表
8.他の検査機関の利用概要
9.他の試験検査機関との契約書の写し又は利用証明書(原本)
上記書類の3・4・5は前回提出したものと同じである場合、省略することが可能です。
なお、上記書類を省略する場合は、窓口で前回の申請書(又は届出書)の控の提示が
必要になります。
※上記書類は東京都の場合です。
申請手数料及び申請場所
東京都の場合、申請手数料等は以下の通りとなっています。
| 化粧品 | 製造販売業 | 46,100円 | |
| 製造業 | 一般 | 25,600円 | |
| 包装等 | 23,600円 | ||
| 医薬部外品 | 製造販売業 | 指定部外品 | 112,800円 |
| その他 | 46,100円 | ||
| 製造業 | 無菌 | 25,600円 | |
| 一般 | 25,600円 | ||
| 包装等 | 23,600円 | ||
| 医薬品 | 製造販売業 | 第1種 | 135,000円 |
| 第2種 | 112,800円 | ||
| 製造業 | 無菌 | 49,600円 | |
| 一般 | 49,600円 | ||
| 包装等 | 23,600円 | ||
| 体外診(一般) | 49,600円 | ||
| 体外診(包装等) | 23,600円 |
■申請受付時間及び場所
月曜日から金曜日の午前9時~11時30分まで。
(土・日・祝祭日はお休みです。)
【申請先】
東京都新宿区百人町3-24-1 本館1階
健康安全研究センター 広域監視部 薬事監視指導課 医薬品審査係
TEL:03-5937-1029
当事務所の報酬額
下記報酬額は、必要書類が全て揃っている場合の金額です。
お客様の状況により金額が変動する場合がございますので、ご了承下さい。
| 化粧品 | 製造販売業 | 64,800円 |
| 製造業 | 64,800円 | |
| 各種変更届 | 32,400円 | |
| 医薬部外品 | 製造販売業 | 64,800円 |
| 製造業 | 64,800円 | |
| 各種変更届 | 32,400円 | |
| 医薬品 | 製造販売業 | 64,800円 |
| 製造業 | 64,800円 | |
| 各種変更届 | 32,400円 | |
| 相談料(1時間)面談 | 5,400円 | |
| 相談料(メール)1往復 | 2,160円 | |
※別途、申請手数料及び申請時の交通費がかかりますので、ご注意下さい。
※初回相談は無料です。
お問合せ
お問合せに料金は一切かかりませんので、許可更新で
ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問合せ
 ください!
ください!
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。
関連リンク
離婚公正証書の作成手数料
2013年12月29日(日)9:32 PM
離婚公正証書の作成手数料は、目的価格により下記のように定められています。
作成手数料は、離婚公正証書作成当日に持参して公証人に支払います。
| 目的価額 | 手数料額 |
| 100万円まで | 5,000円 |
| 200万円まで | 7,000円 |
| 500万円まで | 11,000円 |
| 1,000万円まで | 17,000円 |
| 3,000万円まで | 23,000円 |
| 5,000万円まで | 29,000円 |
| 1億円まで | 43,000円 |
| 1億円を超え3億円まで | 43,000円に5,000万円ごとに13,000円を加算 |
| 3億円を超え10億円まで | 95,000円に5,000万円ごとに11,000円を加算 |
| 10億円を超える場合 | 249,000円に5,000万円ごとに8,000円を加算 |
【注意点】
(1)手数料は目的価格ごとにかかります。
例えば、慰謝料が100万円、養育費が800万円だった場合、手数料は慰謝料で5,000円、
養育費で17,000円の計22,000円となります。
(2)養育費は10年分だけ目的価格に算入されます。
月50,000円の場合、50,000円×12か月×10年=6,000,000円が目的価格になります。
(3)手数料は必ず公証人に確認しましょう。
お問合せについて
お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法でお気軽に
お問合せください!
年中無休で9時~21時まで受付しています。
※紛争性のある案件は取り扱えませんので、ご了承下さい。
TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com
関連リンク
知的資産経営
2013年11月28日(木)10:29 PM
知的資産という言葉をご存じでしょうか?
知的資産とは、著作権などの知的財産権も含みますが、一般的には企業のノウハウやビジネス
モデル、経営理念、人材、技術力、許認可などの社会的信用度や組織力など、企業がこれまで
培ってきた「強み」など、目には見えない無形の資産のことをいいます。
近年は融資の際にこの「知的資産」が重視される傾向にあります。
知的資産経営のメリット
知的資産経営は、中小企業活性化の切り札として経済産業省が強力に推進する経営手法の
一つです。
1.知的資産の配分を最適化し、有効利用することで、業績の向上に結びつける。
2.企業価値を高め他社との差別化ができる。
3.自社の知的資産の有効活用なので、新しいコストをかける必要がない。
4.どのような業種にも活用できる。
5.事業許可を取得するまで、取得後の事業展開に活用できる。
6.地域資源の活用による地域活性化ができる。
7.新設の会社やNPO法人などの事業展開に活用できる。
知的資産経営をはじめるには?
知的資産の実践には、経営者の方などの頭の中にある「知的資産」を書き出してみる事が
大切です。文書化するには、力を入れているサービスや製品について、業務の流れから
知的資産を見ていくのも1つの方法です。
(1)サービスや製品の特徴は何か?
(2)その特徴は他社にはない技術やノウハウにより作りだされるのか?
(3)その技術やノウハウはどのようなシステムから編み出されてきたのか?
上記のように色々な角度から知的資産を確認していきましょう。
文書化するメリット
1.文書化することによって、はじめて分かることが多い。
2.経営者や担当者の頭の中を整理することができる。
3.各種の知的資産がいかに関連して製品やサービスを生み出しているかを目で見る事で、
今後の経営戦略の立案等に役立つ。
4.自社を正しく評価してもらうためにもっとアピールすべき点がわかる。
5.当たり前と思っていた、ちょっとした「こだわり」や「工夫」などが大きな知的資産で
あったなど、新たな発見につながる。
6.強みの強化や弱みの克服を検討できる。
7.流出してからは遅い企業秘密の保護ができる。
知的資産報告書・経営レポートの作成
企業は自社の良い所をアピールすることが必要です。
「知的資産経営報告書」等は知的資産経営を可視化していくための一つのツールです。
自社の培ってきた「強み」や「弱み」を客観的に表現することにより「気づき」のツールと
して役立つとともに、その公表によって、新たな評価を受けることから、新規得意先の
開拓や資金調達、新規の事業展開などに役立てることができます。
「知的資産経営報告書」等では、今後の事業展開を明らかにするため、過去~現在~将来に
向けて知的資産経営をストーリーとして「見える化」することが重要です。
また、行政等が公表している各種の指標と自社の状況との比較を織り交ぜるなどして、客観性
のあるものを作成します。 また、外部の支援者を利用するのも1つの方法です。
知的資産経営報告書・経営レポート作成のメリット
(1)誰にでも理解できる内容の報告書を公表することで、企業は正しい評価を受ける。
(2)融資、資金調達に役立てることができる。
(3)新規の事業展開や取引の拡大に役立てることができる。
(4)海外進出の検討に自社の現状を把握できる。
(5)優秀な人材の確保ができる。
(6)従業員が会社の方針を理解して仕事に取り組むことで、職場に活気がでる。
(7)事業承継に役立てることができる
当事務所の報酬額
当事務所の報酬額及び実費は下記の通りです。
お客様の状況により、下記金額より安くなったり、高くなったりする場合がございます。
| 業務内容等 | 金額 |
| 知的資産経営報告書の作成 | 250,000円 |
| 相談業務(30分あたり) | 5,000円 |
※別途、交通費を頂く場合があります。
お問合せについて
お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法でお気軽に
お問合せください!
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSは24時間お問合せ可能です。
関連リンク
NPO法人設立
2013年11月19日(火)10:43 PM
NPOとは、Non Profit Organizationの略で、非営利で社会福祉活動やボランティア活動を
行う団体を総称してNPOと呼びます。
なお、NPO法人とよく言われますが、何も法人でなければいけないということはありません。
そんなNPOですが、NPO法人を設立するメリット・デメリットは以下の通りです。
◎NPO法人設立のメリット
1.社会的信用の増加
任意団体よりも信用度が高いので、取引先なども安心です。
2.団体名による契約や登記が可能
任意団体の場合、団体名で事務所等の各種契約ができず個人の契約となります。
3.組織を永続的に継続できる
任意団体の場合、財産は代表者のもので、代表者が死亡すると親族に相続され、
財産が団体に帰属しない為、団体消滅の可能性があります。
4.経費の認められる範囲が広い
任意団体では認められない経費が認められるようになります。
5.官公署から事業委託や補助金が受けやすく、融資も可能
6.設立費用がかからない
株式会社の場合は一般的に設立費用が約240,000円(電子定款を使わない場合)、
合同会社で100,000円かかるのに対し、NPO法人は設立費用が全くかかりません。
※専門家に依頼する場合は、別途費用がかかります。
◎NPO法人設立のデメリット
1.設立までに時間がかかる
審査で約4か月程かかりますので、活動開始の5~6ヶ月前から設立手続きに
着手する必要があります。
2.活動内容に制約がある
事業内容は定款の内容に制限されます。
なお、定款変更には4ヶ月程時間がかかるので、定款に記載されていない事業は
すぐに出来ません。
3.社員が10名以上必要
社員というのは、表決権を持っている社員が10名以上という意味です。
4.毎年、事業報告等が必要
毎年事業年度初めの3ヶ月以内に、前事業年度の実績の有無に関わらず、事業報告書等に
関する書類を所轄庁に提出する必要があります。
提出書類は事業報告書等提出書、事業報告書、活動計算書、貸借対照表、計算書類の
注記、財産目録、前事業年度の年間役員名簿、前事業年度末日における社員のうち10人
以上の者の名簿となります。
また、事業年度終了後2ヶ月以内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局において
資産の総額(資産-負債)の変更登記が必要となります。
5.税務申告義務がある
税法で定められた収益事業を行っていない団体は法人税の課税対象ではないため、
税務申告はもちろん、税務署への届出も必要ありません(都道府県税事務所や市町村役場
への届け出は必要です)
6.情報公開義務がある
定款や事業報告書を公開する義務があります。
NPO法人の設立要件
NPO法人の設立要件するには以下の9項目の要件を満たす必要があります。
1.NPO活動(特定非営利活動)を行うことを主たる目的とすること
特定非営利活動とは、以下のように定義されます。
「特定非営利活動20分野(下記参照)に該当+※不特定かつ多数のものの利益の
増進に寄与することを目的とする活動」
不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することとは?
不特定かつ多数のものの利益とは、利益を受ける者が特定されない多数の人の利益、
つまり社会全体の利益を意味します。特定の個人・法人や構成員相互の利益は
「不特定かつ多数のものの利益」とはいえません。
【特定非営利活動の20分野】
(1)保険、医療または福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(4)観光の振興を図る活動
(5)農村漁村又は中山間地域の振興を図る活動
(6)学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
(7)環境の保全を図る活動
(8)災害救援活動
(9)地域安全活動
(10)人権の擁護または平和の推進を図る活動
(11)国際協力の活動
(12)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(13)子どもの健全育成を図る活動
(14)情報化社会の発展を図る活動
(15)科学技術の振興を図る活動
(16)経済活動の活性化を図る活動
(17)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(18)消費者の保護を図る活動
(19)前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の
活動
(20)前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
(東京都の場合、この活動について条例で定めていません。)
2.営利を目的としないこと
営利を目的としないこと、つまり非営利とは、活動に伴い剰余金・利益が生まれたと
しても構成員(役員・社員)に分配しないということ。
また、解散時にはその財産を国等に寄付すること。
寄付金・補助金・助成金などだけでは他者に依存することになり、法人運営の基盤が
弱くなってしまいます。
そこで、特定非営利活動にかかる事業以外の事業(その他の事業という)として収益を
上げることもできます。
ただし、収益を生じたときは、本来事業である特定非営利活動に係る事業の為に使用
しなければなりません。
3.宗教活動を主たる目的としないこと
宗教活動とは、宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教育育成すること
をいいます。
4.政治活動を主たる目的としないこと
政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの
でないこと。
5.特定公職の候補者、公職者又は政党の推進・支持・反対を目的としないこと
特定の公職とは、衆・参両議院、地方公共団体の議会の議員及び首長(知事・市町村長
など)の職のことをいいます。
NPO法人が選挙活動を行うことは認められません。
6.特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として事業を行わないこと
7.特定非営利活動に係る事業に支障が生じるほど「その他の事業」を行わないこと
その他の事業の会計については、特定非営利活動に係る事業の会計から区分して経理
する必要があり、その利益は特定非営利活動に係る事業に充てることになります。
8.社員が10名以上いること
社員とはNPO法人で働き給料を貰う人のことではなく、総会において表決権を持つ会員
のことを言います。
9.社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと
不当な条件を付さないとは、誰でも自由に社員になることができたり、辞める
ことができる事を保証することです。
10.役員法定員数(理事3人以上、監事1人以上)を満たすこと及び役員報酬を受ける
者は役員総数の3分の1以下であること。
役員報酬には、必要経費としての交通費や、理事が事務局の職員を兼務し、労働の
対価として支払われた給与などは含まれません。
報酬の額については特に規定はされていませんが、合理的な範囲を超えると剰余金・
利益の分配とみなされる場合があります。
11.役員として理事3人以上、監事1人以上置くこと
役員とは理事や監事のことです。
理事は職員や社員を兼ねることができますが、監事は社員を兼ねることができますが、
理事や職員を兼ねることはできません。
12.各役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が2人以上いないこと
また、役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の1/3を超えて
含まれないこと
役員の総数が5人以下の場合、配偶者及び三親等内の親族は1人も役員になることは
できません。
6人以上の場合は、各役員につき配偶者及び三親等内の親族を1人含むことができます。
13.役員は成年被後見人又は被保佐人など、法第20条に規定する欠格事由に該当しない
こと
法第20条については、こちらをご覧ください。
14.理事又は監事は、そおれぞれの定数の2/3以上いること
設立当時の理事又は監事は、それぞれの定数を満たしていること
欠員数が1/3を超えたときは遅滞なく欠員数を補充しなければなりません。
15.正当な会計処理をすること
16.暴力団でないこと、暴力団又はその構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から
5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと。
NPO法人設立に必要な書類
1.設立認証申請書 1部
2.定款 2部
3.役員及び役員のうち報酬を受ける者の名簿 2部
4.各役員の就任承諾書及び宣誓書の写し 1部
5.各役員の住所又は居所を証する書面(住民票など) 1部
6.社員のうち10人以上の者の名簿 1部
社員10名以上の氏名、住所を記載した書面。
7.確認書 1部
宗教活動や政治活動をしない事の確認書。
8.設主旨書 2部
9.議事録の謄本 1部
設立について意思の決定を証する議事録の謄本。
10.事業計画書 2部
設立初年度及び翌年度の事業計画書
11.収支予算書 2部
設立初年度及び翌年度の収支予算書
※設立申請時に必要な書類等は、役員(理事3名以上、監事1名以上)の住民票と印鑑だけと
なります。(登記の際は別途他の資料等が必要です。)
NPO法人設立の流れ
NPO法人設立発起人会
NPO法人設立メンバーで集まり、どのような法人にするか協議。
(定款、事業計画、収支予算書など)
↓
設立総会の開催
設立当初の社員が集まり、法人設立の意思決定を行うとともに、先の設立発起人会
で作成した定款等を決議します。
↓
設立申請書類の取寄せ及び作成
↓
設立認証の申請
所轄庁へ設立認証書類を提出します。
一度で受理されることは少なく、何回か申請に通うのが一般的です。
1つの都道府県内にのみ事務所を設ける場合は、当該お道府県の窓口、2つ以上の
都道府県に事務所を設ける場合は内閣府が窓口になります。
↓
公告・縦覧、所轄官庁による審査
設立認証書類提出後、2か月間一般に縦覧
縦覧後2か月以内に審査の結果が出ます。
よって、審査だけで約4か月かかります。
↓
認証・不認証の決定
認証の場合は認証書、不認証の場合は理由を記載された書面が交付されます。
不認証の場合、再申請は可能です。
↓
設立登記申請書類の作成・申請
設立登記申請に必要な書類を作成します。
認証書の交付があった日から2週間以内に事務所所在地を管轄する法務局に設立
登記する必要があります。
従たる事務所がある場合は、主たる事務所での登記日以後2週間以内に従たる
事務所の所在地での登記申請が必要です。
↓
NPO法人設立
法人設立後、関係官庁に各種届出が必要となります。
当事務所の報酬額等
当事務所の報酬額(税込)は下記の通りです。
なお、お客様の状況により報酬額が変動する場合があります。
| 業務名 | 報酬額 |
| NPO法人設立 | 220,000円 |
| 相談(面談)30分あたり | 3,300円 |
| 相談(メール)1往復あたり | 2,200円 |
お問合せについて
お問合せに料金は一切かかりませんので、NPO法人に
ついてご不明な点がございましたら、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せください!
フィリピン人の呼び寄せ(観光)
2013年10月12日(土)10:38 PM
短期滞在ビザとは、日本とビザの免除協定を結んでいない国の方が日本に入国する際に必要と
なるビザです。
短期滞在ビザは、観光・親族訪問・会議などで外国人を日本に呼びたい時に使います。
短期滞在ビザでは報酬を得る活動が出来ないのと、原則としてやむえない事情がある場合を
除き、ビザの延長はできません。
短期滞在ビザ取得の流れ
1.申請書類の収集・作成
申請人(来日予定の人)、日本にいる招へい人がビザ申請に必要な書類の準備・作成を
します。
↓
2.書類の送付
日本にいる招へい人が収集・作成する書類が整ったら、書類を申請人に送付します。
※念の為、送付する書類をコピーしておいて下さい。
↓
3.ビザの申請
申請人が自国で用意する書類と、日本から送られてきた書類を居住地を管轄する日本大使
館や領事館へ提出します。
※提出書類は原則発行後3ヶ月以内の物です。
※提出書類は旅券を除き原則返却されません。
↓
4.ビザの発給
何事もなければ、審査は概ね1週間程度です。
ビザが発給されたら3ヶ月以内に日本に入国します。
※滞在日数のカウントは入国日から始まります。
短期滞在ビザ取得に必要な書類の例
以下の書類は日本人と結婚しているフィリピン人が日本に両親を呼びたい場合の書類です。
あくまでも一例ですので、参考程度にご覧ください。
■日本で準備する書類
①招へい理由書 1通
②申請人名簿(ビザの申請人が複数の場合)
③招へい理由に関する資料
④戸籍謄本 1通
⑤住民票(家族全員の続柄が記載されているもの) 1通
⑥在留カードの写し 両面
⑦住民票(記載事項の省略がないもの) 1通
⑧パスポートの写し
⑨身元保証書 1通
⑩身元保証人に関する次の書類のいずれか一点(総所得の記載があるもの)
・所得証明書又は課税証明書(市区町村役場発行分)
・預金残高証明書
・確定申告書の写し(税務署の受付印があるもの)
・納税証明書
⑪滞在予定表
■申請人がフィリピンで準備するもの
①申請人のパスポート
②ビザ申請書 1通(大使館等で入手できます)
③写真 1葉(4.5㎝×4.5㎝)無帽・無背景のもの
④申請人の出生証明書(NSO発行のもの)
※申請者と日本の親族が3親等以内であることが証明できるもの
・親子、兄弟、姉妹の場合 ⇒ 申請人と奥様の出生証明書
・叔父、叔母の場合 ⇒ 申請人と奥様の出生証明書、奥様の父方又は母方の親の出生
証明書
・姪、甥の場合 ⇒ 申請人と奥様の出生証明書と申請人の該当する父方または母方どち
らかの親の出生証明書
⑤婚姻証明書(既婚者のみ) NSO発行のもの
⑥公的機関が発給する申請人又は扶養者の所得証明書または預金通帳及び納税証明書
詳しくは以下のリンクをご参照下さい。
「短期滞在ビザに必要な書類」
短期滞在ビザの注意点等
・短期滞在ビザが不発給となった場合、原則として6か月間は申請ができなくなります。
・原則として短期滞在ビザの延長、更新は認められません。
ただし、やむえない事情があった場合は延長・更新が認められる場合があります。
お問合せについて
お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せください!
年中無休で9時~21時まで受付しています。
TEL:03-5631-5177
携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com
お問合せフォーム
フィリピン人との結婚手続き
2013年06月16日(日)11:25 AM
■フィリピンにおいて結婚手続きをする場合(フィリピン ⇒ 日本)
※結婚手続きの代行は行っておりません。
【手続きの流れ】
1.婚姻要件具備証明書の入手(在マニラ日本総領事館)
⇓
2.婚姻許可書の入手(フィリピン人婚約者住民地の市町村役場)
⇓
3.挙式、婚姻証明書の入手(挙式挙行地の市町村役場又は国家統計局)
⇓
4.婚姻届けの提出(日本の本籍地市区町村役場又は在マニラ日本国総領事館)
婚姻要件具備証明書の入手について
申請に必要な提出書類
【日本の方が用意する書類】
1.戸籍謄本(抄本)1通 発行後3ヶ月以内のもの
2.(注)改正原戸籍又は除籍謄本 1通 発行後6ヶ月以内のもの
3.有効な日本旅券
4.法定代理人による婚姻同意書(未成年の場合)
【フィリピンの方が用意する書類】
1.出生証明書 1通
出生証明書の記載が不鮮明な場合は有効な旅券、ID又は洗礼証明書などをご用意下さい。
(注)婚姻歴のある方は本証明書にその事実を記載し、「離婚証明書」を作成しますので、
戸籍謄本(抄本)に婚姻及び婚姻解消の事実が記載されていることを確認して下さい。
記載されていない場合には、その事実の記載があるまで遡って改製原戸籍又は除籍謄本を
ご用意下さい。
初婚の方につきましても転籍などのため、提出頂いた戸籍謄本(抄本)では婚姻歴の有無が
確認できない場合には、その事実が確認出来るまで遡って改製原戸籍又は除籍謄本を
ご用意下さい。
過去の婚姻歴の有無及びその内容が確認できない場合には、婚姻具備証明書を発行
できませんのでご注意下さい。
婚姻許可書の入手方法
婚姻具備証明書を持って、婚約者が居住している地域の市町村役場に婚姻許可書を申請
して下さい。
申請の際の手続きの詳細については申請する市町村役場にお問合せ下さい。
婚姻許可申請書の名前等を10日間継続して地方民事登録官事務所に公示された後に
問題がなければ婚姻証明書が発行されます。
これは発行後120日間フィリピン国内のどこの地域において有効です。
挙式、婚姻証明書の入手方法
フィリピンにおいて結婚を挙行できる権限がある者(婚姻挙行担当官:牧師、裁判官など)
及び婚姻の場所が法律で定められており、この婚姻挙行担当官と成人2名以上の証人の
前で婚姻宣誓を行い、婚姻当事者と証人が婚姻証明書に署名し、これを婚姻挙行担当官が
認証することにより婚姻が成立します。
婚姻後15日以内に婚姻証明書が婚姻挙行担当官より挙行地のフィリピン市町村役場に送付
され、地方民事登記官により登録が行われます。
これにより、日本の婚姻届提出の際に必要な婚姻証明書の謄本を入手することが可能と
なります。
婚姻届の提出
帰国後、日本の市町村役場に提出書類を確認のうえ3か月以内に届出して下さい。
(日本に帰国しないため、在マニラ日本国総領事館に届け出る場合)
届出は婚姻後3ヶ月以内に在マニラ日本国総領事館備え付けの届出書(2通)に必要事項を
記入して、下記書類と共に提出して行います。
なお、婚姻の事実が日本の戸籍に反映されるまでには2か月程度かかります。
【届出に必要な書類等】
1.戸籍謄本(抄本) 2通
2.婚姻したフィリピンの方の出生証明書及び日本語訳文 各2通
3.婚姻証明書及び日本語訳文 2通ずつ
4.婚姻要件具備証明書写し 1通
5.婚姻許可書及び婚姻許可証申請書の写し
6.旅券(本人確認のため)
(注)ご結婚された日本人とフィリピン人のお子さんがフィリピンで誕生された場合は、
日本の国籍を留保する意志を表示して、出生の日を含めて3か月以内に届出を
しなければ出生の時に遡って日本の国籍を喪失するので、ご注意下さい。
日本において結婚手続きをする場合(日本 ⇒ フィリピン)
フィリピンの方と日本で婚姻するためには、在日フィリピン大使館にて「婚姻要件具備
証明書」を取得する必要があります。
婚姻要件具備証明書は、現在日本に居住し日本国内で婚姻手続きを希望するフィリピン
国籍者のみに発行します。 申請には、フィリピン人申請者とその外国籍婚約者の両人が
揃って窓口で申請することが条件となります。
婚姻要件具備証明書取得の取得(初婚のフィリピン国籍者)
以下は、初婚のフィリピン国籍者が婚姻要件具備証明書を取得する場合に必要な書類です。
1.申請用紙(在日フィリピン大使館のページからダウンロードできます。)
2.有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部)
3.NSO発行の出生証明書
4.在留カード又は外国人登録証明書
5.パスポート用サイズの写真(3枚)
6.NSO発行の無結婚証明書(CENOMAR)
※無結婚証明書は6か月以内に発行されたものであり、使用目的が「結婚」であること。
※NSOとはフィリピン政府機関である「National Statistics Office」国家統計局の略称です。
■追加書類
18歳から25歳の申請者
1.18歳以上20歳以下の場合-両親の同意書(両親のパスポートのコピーを添付)
2.21歳以上25歳以下の場合-両親の承諾書(両親のパスポートのコピーを添付)
※両親がフィリピンに居住している場合、両親の同意書・承諾書はフィリピン国内の
公証役場で公証し、フィリピン外務省にて認証する必要があります。
両親が日本に居住している場合は、在日フィリピン大使館に来館して作成して下さい。
両親が亡くなられている場合は、NSO発行の死亡証明書が必要です。
日本国籍者の必要書類
1.戸籍謄本(原本+コピー1部)3か月以内に発行されたもの
a.再婚の方:以前の配偶者との婚姻日、離婚日が記載された戸籍謄本、改製原戸籍、
除籍謄本のいずれかを提出。
b.死別の方:以前の配偶者の死亡日が記載された戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本の
いずれかを提出。
※戸籍抄本は受付ません。
2.有効なパスポート又は公的な写真付き身分証明書
3.パスポート用サイズの証明写真:3枚
外国籍者の必要書類
1.自国大使館発行の婚姻具備証明書またはそれに相当する書類:原本+コピー1部
※書類の言語が英語以外の場合、英訳を提出
2.在日米軍の所属する者は結婚許可書:原本+コピー1部
3.有効なパスポート又は軍人身分証明書:原本+コピー1部
4.パスポート用サイズの写真:3枚
申請期間:5営業日
婚姻届の提出
日本の役所に婚姻届を提出します。
婚姻に必要な書類の例は以下の通りです。必ず婚姻届を届出る役所に必要書類を確認して
下さい。
1.婚姻届
2.婚姻要件具備証明書(要日本語訳)
3.フィリピン人の出生証明書(要日本語訳)
4.戸籍謄本(日本人分) など
結婚報告
在日フィリピン大使館に結婚の報告を行って下さい。
なお、必要書類については在日フィリピン大使館にお尋ね下さい。
弊所の報酬額
弊所の報酬は以下の通りです。
お客様の状況により金額が変動する場合がございます。
| 業務内容 | 金額 |
| 外国から配偶者を呼ぶ場合 | 88,000円 |
| 配偶者が日本在住で結婚ビザに変更する場合 | 88,000円 |
| 申請書類のチェック及びアドバイス | 55,000円 |
※別途実費がかかります。
※ご結婚手続きは代行していませんので、ご了承下さい。
お問合せについて
お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せ下さい!
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。
ビザの取消制度
2013年06月01日(土)12:49 PM
ビザの取消制度は、ビザ制度を適切に運営するために、平成16年に施工されました。
日本に在留する外国人は、上陸または在留の許可時に決定されたビザをもって在留しており、
退去強制に該当しない限り、原則的には在留期間内は在留が認められています。
しかし、不正な手段を用いてビザを取得する例が増加しているのと、正当な理由がないのに
付与されたビザに関する活動を長期間行わないで在留する外国人が増えた為、ビザの取消
制度ができました。
ビザの取消対象になる外国人(平成16年の入管法改正)
1.上陸拒否事由に該当するにも関わらず、偽りその他不正の手段により上陸許可を
受けた者(1号)
本来上陸できないにもかかわらず、上陸拒否事由を隠したり、偽りその他不正な手段に
より上陸許可を受けた場合には、ビザの取消対象になります。
2.偽りその他不正手段により、上陸許可または在留の許可の申請の際に在留目的などを
偽って許可を受けた者(2号)
上記のような外国人は、日本において行おうとする活動が許可されたビザに該当しない
ことが判明すれば本来は許可を受けることができません。
このような事実が判明した場合、在留資格の取消対象になります。
3.上記1・2を除き、偽りその他不正の手段によりビザを受けた者(3号)
入管法22条の4第1号又は第2号に規定する事項以外の重要事項を偽って上陸許可認印など
を受けた外国人は、上陸許可手続き又は在留の諸手続きの時点でそのような不正事実が
判明していれば、ビザを受けることができなかったものです。
事後にそのような事実が判明した場合は、そのビザを認めるべきではないので、ビザの
取消対象になります。
4.上記1.2.3を除き、不実の記載のある文書又は図画の提出により、上陸許可又は
在留の許可を受けた者(4号)
上記1.2.3に掲げる事由以外でも虚偽の文書などを行使してビザを受けようとする外国人
が増えています。
各種虚偽文書等の提出は入国審査官の判断を誤らせるものであり、公正な出入国管理を
行う点から看過できないので、虚偽文書等を提出又は提示してビザを受けたことが判明
した場合は、ビザの取消対象になります。
5.適法にビザを受けている外国人が正当な理由なく、ビザに掲げる活動を継続して
3か月以上行わないで在留する者(6号)
外国人の公正な出入国管理を図るため、現に有するビザに係る活動を正当な理由なく
継続して3か月以上行っておらず、かつ、今後も行う見込みがないなど、ビザが形骸化
している場合には、ビザの取消対象になります。
ビザの取消対象になる外国人(平成21年入管法改正)
1.偽りその他不正の手段により在留特別許可を受けたこと(5号)
2.「日本人の配偶者」又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する者が、その
配偶者としての身分を有する者としての活動を正当な理由なく継続して6か月以上行わ
ないで在留していること(7号)
3.ビザを受け、新たに中長期在留者になった者が、正当な理由なく90日以内に法務大臣に
住居地の届出をしないこと(8号)
4.中長期滞在者が転居した場合に正当な理由がなく、90日以内に法務大臣に新住居地の
届出をしないこと(9号)
5.中長期滞在者が法務大臣に虚偽の住居地を届け出たこと(10号)
ビザの取消手続き
ビザの取消しは、在留資格取消通知書の送達によって行われることとなります。
在留資格取消通知書の送達は、在留資格取消しの対象者の住居地に対する送付又は当該外国人
本人に直接交付する方法によって行われます。
ビザを取消す場合には、入国審査官が当該外国人の意見を聴取します。
意見の聴取に当たっては、意見聴取の期日、場所、取消事由を通知します。
当該外国人は、期日に出頭し意見を述べ、証拠を提出します。
なお、正当な理由がなく当該外国人が意見の聴取に応じない場合は、意見の聴取を
行わないで、ビザを取消すことができます。
ビザ取り消し後の取扱いは二通りあります。
不正手段等の行使について悪質性が高い場合には、ビザを取り消された後、直ちに退去強制
の手続が執られます。
一方、不正手段等の行使について悪質性が高くない場合や、在留資格に基づく本来の活動を
継続して一定期間行っていない場合や、中長期在留者が住居地の届出を行わない場合又は
虚偽の届出をした場合には、在留資格を取り消される際に、30日を超えない範囲内で出国
するために必要な準備期間(出国猶予期間)が指定され、同期間内に自主的に出国すること
になります。
お問合せについて
問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せ下さい!
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)
TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com

LINE

WeChat
関連リンク
- ご相談について
- ご依頼までの流れ
- 当事務所に依頼するメリット
- 会社設立業務
- 建設業許可申請
- 宅建業免許申請
- 離婚協議書作成業務
- ビザ申請を依頼するメリット
- 用語集
- 提携事務所
- リンク集
- サイトマップ
- トップページ
- お問い合わせ
過去のブログを検索
携帯サイト
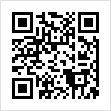
携帯電話をご利用の方は
QRコードを読み取って
モバイルサイトをご覧になれます。

当サイトは、
情報を安全に提供して頂くために、
「高度なセキュリティ」と「信頼性」で
定評のあるRapidSSLを利用しております。
プライバシーポリシー