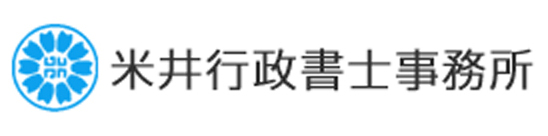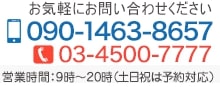資本金によって異なる主な税金
2011年10月14日(金)4:25 PM
【消費税の課税事業者の判定】
| 資本金の額 | 第1期 | 第2期 | 第3期 |
| 1,000万円未満 | 免税事業者 | 免税事業者 | 第1期の売上高による |
| 1,000万円以上 | 課税事業者 | 課税事業者 | 第1期の売上高による |
【交際費の損金不算入】
| 期末資本金の額 | 損金不算入額 |
| 1億円以下 |
交際費400万円までの部分の10%+ 交際費400万円を超えるの金額 |
| 1億円超 | 全額 |
【道府県民税】
| 資本金の額 | 従業員数 | 均等割 |
| 1,000万円以下 | 関係なし | 20,000円 |
| 1,000万円超、1億円以下 | 関係なし | 50,000円 |
【市町村民税】
| 資本金の額 | 従業員数 | 均等割 |
| 1,000万円以下 | 50人以下 | 50,000円 |
| 1,000万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
| 1,000万円超、1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
| 1,000万円超、1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
・・・【株式会社設立】についてはこちらをクリックしてください>>
お問合せ
お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法でお気軽に
お問合せください!
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。
TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com

LINE

WeChat
合同会社(LLC)の設立
2011年10月14日(金)3:51 PM
【合同会社のメリット】
1.株式会社と同じく有限責任
2.株式会社に比べると早く安く設立できる
3.決算公告義務がないので、会社設立後の手間や費用がかからない
4.自由な会社組織と運営
【合同会社のデメリット】
1.株式会社に比べると信用度・社会的認知度が下がる
合同会社の特徴
合同会社(LLC)では、社員全員が経営に参加することを前提としており、全社員が直接
合意して、会社の意思決定を行っていくのが特徴です。
合同会社の社員は原則として全員が業務を執行する権限を有しているのです。
社員が2人以上いる場合は、社員の過半数をもって業務の執行を決定していきます。
【業務執行社員を定めることができる】
業務執行社員とは、株式会社でいう取締役にあたります。
業務執行社員は、定款に定めれば社員の中から定めることができます。
全社員に業務の執行権限があり、重要事項の意思決定では全社員の合意を原則として
いるのに、あえて業務執行者定めるのは何故でしょうか?
それは、会社が大きくなり社員が増えてくると、意思統一が難しくなり、会社の意思決定や
運営に支障をきたすようになるのを見越しているからだと思われます。
定款について
合同会社(LLC)設立時に一番大切な書類は定款です。
定款作成上のルールは、株式会社とさほど変わるところはありません。
合同会社(LLC)は組織形態や運営、あるいは利益分配の割合などを定款により自由に
決められるので、それだけ定款の重要性も増してきます。
合同会社(LLC)の定款にも必ず記載しなければならない「絶対記載事項」、記載しないと
効力が生じない「相対的記載事項」、「任意的記載事項」があります。
【定款の作成部数】
最低2通です。
1通は会社保存用、もう1通は登記の際に提出します。
【定款の合意】
作成した定款は社員全員による合意が必要です。
また、定款を変更する際も同様です
定款の記載事項例
【絶対的記載事項】
1.商号
・商号の中に必ず合同会社と入れる。
・同一住所で同一商号は使えません。
・使用できる文字に制限があります。(漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字など)
・会社の一部門を表す文字は使用できません。(○○合同会社△△支店など)
・銀行や信託といった文字は使えません。
・公序良俗に反する商号はつける事ができません。
・有名企業と同じ商号は使えません。(ソニーなど)
2.目的
・「営利性」、「明確性」、「具体性」、「適法性」が必要です。
・これからやりたい業務を全て列挙した方が良いでしょう。
3.本店所在地
4.社員の氏名または名称及び住所
5.社員の全部を有限責任社員とする旨
6.社員の出資目的(金銭等に限る)およびその価額または評価の基準
【相対的記載事項】
1.社員のうち業務を執行する社員を定める
2.代表社員の定め
3.利益の配当
4.損益分配の割合
5.退社の条件
6.解散の事由
【任意的記載事項】
1.営業年度に関する規定など
設立時に必要な書類等の一例
・合同会社設立登記申請書
・登録免許税納付用台紙
・定款
・払込証明書
・資本金計上に関する証明書
・代表社員、本店所在地および資本金決定書
・代表社員の承認承諾書
・通帳のコピーまたは残高証明書
・代表者の印鑑証明書
・代表者印
・登録免許税(資本金の7/1000、最低6万円)
合同会社(LLC)設立の流れ
設立が可能となります。
合同会社は1~2週間程度あれば登記申請まで可能です。
1.会社の基本事項を決定する
↓
2.類似商号の調査
また、有名企業と同じ名前で会社を設立することはできません。
↓
3.会社の印鑑を作成
一般的には代表者印、銀行印、角印を作ります。(代表者印だけでも可)
↓
4.定款その他各種書類の作成
↓
5.出資金の払込み
出資金の払込が完了したら、通帳のコピーを取ります。(表紙、表紙の裏、出資金を
振込んだページ)
↓
6.設立登記申請に必要な書類の作成
↓
7.設立登記申請
代理人、郵送での登記申請も可能です。
※登記申請日が会社設立日となります。
↓
8.合同会社設立
会社が設立したら、税務署等に必要書類を届け出ます。
当事務所に合同会社設立を依頼するメリット
2.顧問報酬の必要がありません。
3.税理士等、各種」専門家を無料でご紹介いたします。
4.創業融資、許認可取得、経理代行とトータル的にお客様をサポートします。
6.年中無休で21時まで営業しているので、忙しい方でもご相談可能です。
合同会社の設立費用
以下は、合同会社設立手続きの全てを弊所で行った場合です。
お客様の状況により、金額が変動する場合がありますので、費用について
ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
【設立費用例(税込)】
| 項 目 | ご自身で設立 | 当事務所に依頼 |
| 収入印紙代 | 40,000円 | 0円 |
| 登録免許税 | 60,000円 | 60,000円 |
| 当事務所の報酬 | 0円 | 66,000円 |
| 設立費用合計 | 100,000円 | 126,000円 |
※当事務所では電子定款を導入しているため、収入印紙代4万円がかかりません。
※登録免許税は資本金の1,000分の7(計算した税額が6万円に満たないときは6万円)
となります。
※詳しい合同会社設立費用についてはこちらをご覧下さい。
※電子定款の作成のみ:33,000円、定款への電子署名のみ:11,000円となります。
お問合せについて
お問合せに料金は一切かかりませんので、合同会社設立について
ご不明な点がございましたら、以下の方法にてどうぞお気軽に
お問合せ下さい!
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。
TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com

LINE

WeChat
関連リンク
定款について
2011年10月14日(金)2:39 PM
■定款とは?
定款は会社の重要事項を定めた書類で、会社の憲法といえます。
会社設立時には必ず作成しなくてはならず、設立時に作成する様々な書類の中でも最も重要な
書類といえます。その重要性を示すように定款は公証人の認証を受けなければならず、認証の
ないものは登記申請の際に認められません。
定款の内容は、必ず記載しなければならない絶対的記載事項、定めないと効力が生じない
相対的記載事項、任意の内容である任意的記載事項に分けることができます。
絶対的記載事項とは?
定款の作成上、必ず記載しないといけない事項を「絶対的記載事項」といいます。
絶対的記載事項を欠くと、その定款は無効になります。
絶対的記載事項は下記の6つです。
1.商号
2.目的
3.本店所在地
4.設立に際して出資される財産の価格またはその最低額
5.発起人の氏名または名称および住所
6.発行可能株式総数
相対的記載事項とは?
定款に必ず記載する必要はないが、記載しないと効力が発生しない事項です。
主な内容は下記の通りです。
1.現物出資の内容
2.財産の引き受け
3.会社が負担すべき設立費用
4.株式譲渡制限に関する規定
5.公告の方法
任意的記載事項とは?
定款に記載するかどうかは、会社が自由に決められる事項です。
定款に記載する事により会社運営がスムーズになりますし 、会社の内容を株主に明確に
示せるメリットがあります。ただし、決め事を多くすると会社運営がスムーズにいかなく
なるので注意が必要です。
主な内容は下記の通りです。
1.事業年度に関する規定
2.取締役や監査役の人数
3.株主総会開催の時期
4.株主総会の議長
5.取締役会の組織についての規定
定款の書き方
用紙の大きさに決まりはありませんが、A4またはA3(二つ折りにする)で作成するのが
一般的です。手書きでも作成可能ですが、便利なパソコン(ワープロ)で作成した方が良い
でしょう。パソコンで作成した場合、文字の大きさや書体に決まりはありません。
なお、手書きの場合は鉛筆書きは認められません。
訂正箇所がある場合は、修正液での訂正は認められず、訂正箇所を二重線で消し、その上に
新しい文字を記入します。
さらにページ上部に「○○字削除○○字加筆」と記載し、発起人全員の捨印(実印)をします。
定款認証手続き
定款は作成しただけでは効力は生じません。
作成が終わったら、本店所在地と同じ都道府県内にある公証人役場に原則として発起人全員で
出向き、定款の認証を受けることにより法的効力が生じます。
なお、発起人全員が揃わなかったり、公証人役場に行く時間がない場合には、発起人のうち
1人を代理人とすることができます。また、代理人は発起人以外の第三者でも可能です。
代理人に委任する際に必要な委任状の住所や氏名は、印鑑証明に記載されているように書いて
ください。
※定款の認証は電子媒体でも可能です。
電子定款についてはこちらをご覧ください。
定款の作成部数は?
最低3通です。
1通は原本、1通は会社保存用、1通は法務局に設立登記申請の際に必要となります。
その他に必要な場合は、部数を増やしてください。
※電子定款の場合は2通で可
定款認証に必要なもの
1.定款3通
・すべての定款に発起人の署名(記名)押印をする。
・押印する印鑑は全て個人の実印
2.印鑑証明書
・発起人全員の個人の印鑑証明書(発行後3か月以内)
3.認証手数料
・公証人への手数料は50,000円
・定款の謄本交付手数料 1枚 250円
4.収入印紙
・40,000円の収入印紙が必要(不備があったときの事を考え、貼付はしない)
※当事務所は電子定款を導入している為、収入印紙代40,000円は不要になります。
5.委任状
・定款認証時に欠席する発起人がいる場合のみ必要。
・委任状には個人の実印を押印する。
お問合せについて
お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せ下さい!
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。
関連リンク
株式会社設立
2011年10月13日(木)9:14 PM
【株式会社のメリット】
1.有限責任
・万が一会社が倒産した時でも出資額以上の責任を負いません。
※経営者責任を負う場合がありますので、ご注意ください。
2.社会的信用・認知度が高い
・取引先からの信用度も高くなりますし、融資を受けやすくなります。
3.節税になる
・個人事業の所得税は超過累進課税なのに対し、法人税の税率は定率です。
・経費の認められる範囲が個人よりも広くなります。
【株式会社のデメリット】
1.個人事業に比べると事務処理が煩雑になる
2.組織の自由度が劣る
・個人事業や合同会社に比べると会社組織の自由度は劣ります。
株式会社の設立方法には「発起設立」と「募集設立」の2つの方法があります。
発起設立とは、定款に定められた発起人(家族や友人など)が株式全部を引受けて株式会社
を作る方法です。
一方、募集設立とは、発起人が一部の株式を引受け、残りについては広く一般の人から株式
を引受けて株式会社を設立する方法です。
以前は、募集設立で株式会社を作る人の方が多かったのですが、最近は、発起設立の方が
簡単かつスムーズに設立できるなどの理由があり主流となっています。
したがって、当サイトでは、発起設立を前提として説明しています。
出資割合について
各株主は1株につき1つの議決権を持っているのが原則です。
つまり、出資割合が多いほど会社の経営に口を出すことができます。
株主総会での重要事項の決議の大半は過半数か3分の2以上の決議が必要なので、自分の
会社の仲間が出資して会社を作る場合などは、上記の点に注意して出資割合を決めてください。
株式の譲渡制限とは?
株式の譲渡制限とは、株式を会社に無断で譲渡できないようにすることです。
譲渡制限をしている場合は、取締役会を設置しなくてもよいと会社法で定められて
いますし、監査役も必ずしも設置する必要もありません。
よって、取締役1名だけのコンパクトな会社を作ることができます。
これに対し、譲渡制限をを定めていない公開会社の場合は、取締役会は必ず設置する
必要があり、取締役も3名以上必要で監査役も置かなくてはなりません。
株式会社設立時に決めること
【商号】
会社法施行により、類似商号の規制は廃止され商号はある程度自由になりました。
従って同じ住所で同じ会社名でない限り登記は受理されるようになりましたが、
不正競争防止法や商標法に触れるような商号を付けることはできません。
|
類似商号について |
同一住所に同一商号は不可(有名会社と同じ会社名は避ける) |
|
使用文字について |
ひらがな、カタカナ、漢字、ローマ字、アラビア数字、符号(一部のみ) |
|
命名について |
会社名の前後に必ず「株式会社」とつける |
【会社の目的】
会社の目的は定款に必ず記載しなければならない事項です。
会社設立後すぐに営む事業だけではなく、現在興味を持っている事業、将来予定している
事業も入れた方が良いでしょう。
なぜならば、入れておかないと、その事業を営む際に法務局への定款変更登記申請などが
必要になり手間がかかるからです。
<目的を決める際の注意点>
| 適法性 | 法律に反するようなことをしてはならない |
| 明確性 | 第三者が見て理解できなくてはならない |
| 具体性 | 事業内容、目的を抽象的にならず具体的に |
| 営利性 | 営利目的であるということを明確に |
【資本金を決める】
資本金1円でもスタート可能ですが・・・
最低資本金規制がなくなったため、資本金は1円からでも可能ですが、現実には
1円から会社経営を始めるのは厳しいでしょう。
なぜならば、資本金は活動資金として使うことができます。
資本金1円では名刺やパンフレットの作成、事務所を借りたりすることが出来ません。
又、取引先が登記簿で資本金を確認した際に資本金が1円では、会社の信用に影響
するからです。
つまり、資本金が多い方がゆとりを持って経営に取り組めるということです。
ただし、全く計画がなく、ただ資本金が多ければ良いというものではありません。
なぜかというと、資本金の大きさが税金に関係してくるからです。
例えば、消費税の場合、基本的に設立時2年目までは申告義務はありませんが、
設立時に資本金が1,000万円以上の場合は、設立初年度から消費税の申告課税業者
になります。よって、1,000万円未満の資本金であれば、2年目までは消費税の免税
事業者となります。
【本店所在地を決める】
本店を置く場所には制限がなく、基本的にはどこにでも置くことができます。
ちなみに、定款に記載する本店所在地は2通りの方法があります。
1つは最小行政区画まで記載(東京都墨田区など)する方法と具体的に地番まで記載
(東京都墨田区3丁目×番×号など)する方法があります。
【発起人を決める】
発起設立の場合、発起人が1名以上必要になります。
発起人とは、株式会社設立の企画者として定款に署名した人のことです。
発起人は15歳未満の者でなければ、未成年などの制限行為能力者でも法定代理人の同意が
あれば発起人になることができます。
発起人が決まったら、発起人会を開催し、どのような会社にするか話し合い、発起人会議事録
を作成します。
なお、発起人が1名の場合は、発起人決定書で代用できます。
【役員を決める】
役員とは代表取締役、取締役、監査役などのことで、会社設立時は、発起人会もしくは定款で
選任します。
役員は発起人以外の人でも構いませんが、通常は発起人の中から選ばれることが多いです。
任期は取締役が2年、監査役が4年ですが、定款に株式譲渡制限を設けた場合、最大で10年
まで延長できます。
【事業年度(決算日)を決める】
事業年度(決算日)は自由に決めることができます。
一般的に4月1日~3月31日、1月1日~12月31日の会社が多いですが、基本的には
いつでも構いません。
ただ、決算日を決める際は、以下の点に注意してください。
・設立第1期目の問題
会社設立日から決算日までの期間が短くなると経理処理が慌しくなるので避けた方が賢明
です。
・仕事の繁忙期の関係
繁忙期の日常業務と決算業務が重なると両方の作業を行わなくてはいけないため、
気をつけましょう。
・資金繰りとの関係
納税は決算日から2ヶ月以内行わなければいけないので、イレギュラーな出費がある時期と
重ならないようにした方が資金繰りが楽になります。
【決算の公告方法を決める】
株式会社は決算の内容を公告しなくてはなりません。
公告方法は以下の3種類あり、いずれかを選択しなくてはなりません。
1.官報に掲載して公告
2.時事に関する事項を掲載する日刊新聞に掲載して公告
3.電子公告(自社のHP上で公告)
公告する事項は、会社の「決算」、「合併」、「会社分割」、「組織変更」、「解散」、
「資本金の減少」、「基準日」などがあり、官報に掲載して公告する方法が最も一般的です。
各種印鑑を作る
会社設立には、代表者印が必要です。
その他に銀行印、角印、社名や住所のゴム印があると便利です。
代表者印と銀行印は同一の物でも構いませんが、紛失してしまうとお金が下ろせなくなったりしますので、できれば分けた方が良いでしょう。
印鑑の作成には時間がかかりますので、商号が決まったらすぐに発注してください。
なお、個人の実印を代表者印として用いても構いません。
当事務所では会社設立に必要な印鑑セット(代表者印・銀行印・角印)をお安く販売いたします。詳しくはお問合せください。
発起人の印鑑証明書を用意する
定款の認証を受けるときや登記をするときに必要となります。
なお、発行から3ヵ月以内のものを用意してください。
会社設立に必要な書類
【必ず必要な書類】
1.定款
2.発起人の印鑑証明書
3.払込みがあったことを証する書面(通帳のコピー)
4.登記申請書
5.登録免許税納付用台紙
6.登記する事項を記載した用紙等(OCR用紙・CD-Rなど)
7.印鑑届書
【条件により必要になる書類】
1.就任承諾書
2.発起人決定書
3.設立時取締役・監査役決定書
4.設立時代表取締役決定書
5.資本金の額の計上に関する証明書
6.取締役・監査役の調査報告書
7.財産引継書
8.税理士の証明書
9.不動産鑑定評価書
※詳しくはお問合せください。
株式会社設立の流れ
て2週間~1ヵ月程度見ておいた方が良いでしょう。
↓
2.法務局で登記相談
事業目的について相談します。
※義務ではありません。
↓
3.会社の代表者印の作成
代表者印の他に銀行印、角印を作っておくと便利です。
↓
5.定款の認証
会社の所在地を管轄する公証役場で認証を受けます。
定款の認証には、53,000円程度かかります。(取得する定款数等によって変わります)
なお定款の認証地は、所在地を管轄する都道府県の公証役場でしたらどこでも可能です。
(例)会社の所在地が東京の場合、東京にある公証役場だったらどこで認証を受けても
構いません。
↓
6.資本金の振込
代表発起人の口座に資本金を振込みます。
振込む際には「預入」ではなく、必ず振込人名が出るように振込んでください。
振込みをしたら、通帳の表紙のコピー、通帳1ページ目のコピー、振込んだ事が分かる
ページのコピーを取ります。
↓
7.登記申請に必要な書類の作成
登記申請書など、会社設立登記に必要な書類を作成します。
↓
本店所在地を管轄する法務局で登記申請します。
登記申請から会社設立まで約1~2週間かかります。
なお、登記申請は代理人、または郵送でも可能です。
↓
登記申請した日が会社設立日となります。
↓
10.官公署へ必要な届出書類を提出
法人設立届、青色申告の承認申請書など官公署に提出しなければならない書類を
提出します。
外国人の会社設立について
ただし、代表取締役のうち少なくても1名は日本に住所を持った人が必要となりますので、
日本に住所を持たない外国人の方が1人で会社を作る事はできませんので、ご注意下さい。
なお、必要書類は日本人とほぼ同じですが、印鑑登録制度がない国に関しては、母国で認証
されたサイン証明書及びその日本語訳文が必要になります。
※サイン証明書には、氏名、生年月日、住所が記載されている必要があります。
弊所に依頼するメリット
2.顧問契約の必要がありません。
3. 税理士等各種専門家を無料でご紹介いたします。
4. 創業融資、許認可の取得、経理代行とトータル的にお客様をサポートいたします。
5. 会社設立に必要な印鑑セットを割安で販売いたします。
6. 年中無休で21時まで営業していますので、忙しくても安心です。
当事務所の報酬額 (税抜)
| 株式会社設立 | 60,000円 |
| 電子定款作成のみ | 30,000円 |
| 電子署名のみ | 10,000円 |
※別途、実費がかかります。
お問合せについて
お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
関連リンク
プライバシーポリシー
2011年10月08日(土)12:59 PM
米井行政書士事務所(以下「当事務所」)は、個人情報保護に関する法律、行政書士法、
その他関係法令を遵守します。
● 前項の業務の遂行を適切かつ円滑に履行するのに必要な本人確認。
● 依頼を受けたことに伴う各種リスクの把握および管理。
● 当事務所の挨拶状等の送付、講習会等のご案内。
● 当事務所の提供する各種法的サービスに関する情報のお知らせ。
【在留資格】日本人の配偶者等
2011年10月08日(土)10:23 AM
【本邦において有する身分又は地位】
日本人配偶者若しくは民法第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者
該当例
日本人の配偶者・子・特別養子
【在留期間】
6ヵ月・1年・3年・5年
【立証資料】
1.在留資格決定の場合
(1)日本人配偶者である場合
ア.当該日本人との婚姻を証する文書
戸籍謄本(戸籍謄本に婚姻事実の記載がない場合は、婚姻届受理証明書が必要です)
イ.当該日本人の住民票の写し(世帯全員の記載のあるもの)
ウ.当該外国人又はその配偶者の職業及び収入に関する証明書
①在職証明書等職業を証明するもの
②年間の収入及び納税状況を証するもの
・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
エ.本邦に居住する当該日本人の身元保証書
(2)日本人の特別養子又は子である場合
ア.当該日本人の戸籍謄本及び当該外国人の出生証明書その他の親子関係を証する文書
①当該日本人の戸籍謄本
②当該外国人の出生証明書
③その他の親子関係を証する文書
両親の婚姻に係る証明書、認知に係る証明書、養子縁組に係る証明書等
イ.当該外国人又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
①在職証明書等職業を証明するもの
②年間収入及び納税状況を証するもの
・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
ウ.本邦に居住する当該日本人又はその他の本邦に居住する身元保証人の身元保証書
2.在留期間更新の場合
(1)日本人配偶者である場合には、当該日本人の戸籍謄本及び住民票の写し
※住民票は世帯全員の記載のあるもの
(2)当該外国人、その他配偶者又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
ア.在職証明書等職業を証明するもの
イ.年間収入及び納税状況を証するもの
・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
(3)身元保証書
ア.日本人配偶者である場合には、本邦に居住する当該日本人の身元保証書
イ.日本人の特別養子又は子である場合には、本邦に居住する当該日本人又はその他
本邦に居住身元保証人の身元保証書
【ポイント】
出生の時に父又は母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合又は本人の出生前に父が
死亡し、かつ、その父が死亡のときに日本国籍を有していた場合にこれに当たる。
なお、本人の出生後父又は母が日本国籍を離脱した場合も、日本人の子として出生した
という事実に影響を与えるものではない。
【引用】
出入国管理のしおり
ひと目でわかる外国人の入国・在留案内
・・・【在留資格について】はこちらをクリックしてください>>
【在留資格】永住者の配偶者等
2011年10月08日(土)10:21 AM
【本邦において有する身分又は地位】
永住者の在留資格をもらって在留する者若しくは特別永住者(以下、永住者)の配偶者又は
永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
【該当例】
永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している子
【在留期間】
5年、3年、1年、6月
【立証資料】
1.在留資格決定の場合
(1)永住者の配偶者である場合
ア.当該永住者との身分関係を証する文書
①当該永住者の戸籍謄本
②婚姻届受理証明書
③婚姻証明書等婚姻の事実が記載されているもの
イ.当該永住者の外国人登録証明書又は旅券の写し
ウ.当該外国人又はその配偶者の職業及び収入を証する文書
①在職証明書等職業を証明するもの
②年間の収入及び納税状況を証するもの
・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
エ.本邦に居住する当該永住者の身元保証書
(2)永住者の子である場合
ア.出生証明書その他の親子関係を証する文書
①出生証明書
②戸籍謄本
③その他の親子関係を証する証明書
両親の婚姻に係る証明書、認知に係る証明書等のいずれかで親子関係を証するもの
イ.当該永住者の外国人登録証明書又は旅券の写し
ウ.当該外国人又は父若しくは母の職業及び収入等に関する証明書
①在職証明書等職業を証明するもの
②年間の収入及び納税状況を証するもの
・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
エ.本邦に居住する当該永住者又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
2.在留期間更新の場合
(1)永住者の配偶者である場合には、当該永住者との身分関係を証する文書
ア.戸籍謄本
イ.健康保険証等申請人に係る婚姻が継続していることを証するもの
(2)当該永住者の外国人登録証明書又は旅券の写し
(3)当該外国人、その配偶者又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
ア.在職証明書等職業を証明するもの
イ.年間の収入及び納税状況を証するもの
・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
(4)身元保証書
ア.永住者の配偶者である場合には、本邦に居住する当該永住者の身元保証書
イ.永住者の子である場合には、本邦に居住する当該永住者又はその他本邦に居住する
身元保証人の身元保証書
【ポイント】
出生の時に父又は母のいずれか一方が永住者の在留資格をもって在留していた場合
又は本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに永住者の在留資格を
もって在留していた場合に、これに当たる。
なお、出生後父又は母が永住者の在留資格を失っても差し支えない。
【引用】
出入国管理のしおり
ひと目でわかる外国人の入国・在留案内
・・・【在留資格について】はこちらをクリックしてください>>
【在留資格】定住者
2011年10月08日(土)10:19 AM
【本邦において有する身分又は地位】
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
【該当例】
日本人の配偶者と死別・離婚した者、第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人など
※就労関係の在留資格から定住者への変更は認められません。
【在留期間】
5年、3年、1年又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
【立証資料】
1.在留資格決定の場合
(1)戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他の当該外国人の身分関係を証する文書
次のいずれかの一又は複数の文書で、当該外国人の身分関係を明らかにするもの
ア.戸籍謄本又は除籍謄本(両親又は祖父母)
イ.婚姻証明書(両親又は祖父母)
ウ.出生証明書(両親又は祖父母)
エ.死亡証明書(両親又は祖父母)
呼寄せ人が日本人である場合は住民票の写し、呼寄せ人が外国人である場合は
外国人登録証明書又は旅券の写し
(2)在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書、当該外国人以外の
者が経費を支弁する場合には、その収入を証する文書
ア.申請人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの一又は複数の文書で、申請人が
経費を支弁することができることを証するもの
①申請人名義の銀行等における預金残高証明書等我が国において支払い可能な
資産を有することを証するもの
②雇用予定書
③①又は②に準ずる文書
イ.申請人以外の者が申請人の経費を支弁する場合は、次のいずれかの一又は複数の
文書で、申請人の経費を支弁することができることを証するもの
①住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
(3)犯罪経歴証明書
申請人の国籍又は日本に入国する前に居住していた居住国における権限のある期間が
発行した犯罪経歴証明書又は無罪犯罪証明書
(4)本邦に居住する身元保証人の身元保証書
2.日本人実子をを扶養する外国人親として在留資格の変更をする場合
(1)日本人実子との親子関係を証する文書
ア.戸籍謄本
イ.出生証明書
(2)親権を行う者であることを証する文書
(3)日本人実子の教育状況に関する文書
ア.通園証明書
イ.通学証明書
ウ.その他養育状況に関するもの
(4)扶養者の職業及び収入に関する証明書
ア.在職証明書等職業に関する証明書
イ.住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
ウ.雇用予定証明書
(5)本邦に居住する身元保証人の身元保証書
3.在留期間更新の場合
(1)戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他の当該外国人の身分関係を証する文書
次のいずれかの一又は複数の文書で、当該外国人の身分関係を証する文書
ア.戸籍謄本
イ.婚姻証明書
ウ.出生証明書
(2)収入及び納税額に関する証明書、収入のない場合には、扶養者の職業及び
収入に関する証明書
ア.申請人に収入がある場合
①在職証明書等職業を証明するもの
②年間の収入及び納税状況を証するもの
・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
イ.申請人に収入がある場合
①扶養者の在職証明書等職業を証明するもの
②年間の収入及び納税状況を証するもの
・扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
(3)犯罪経歴証明書
(4)本邦に居住する身元保証人の身元保証書
【引用】
出入国管理のしおり
ひと目でわかる外国人の入国・在留案内
・・・【在留資格について】はこちらをクリックしてください>>
【在留資格】技術
2011年10月08日(土)10:17 AM
【本邦において行うことができる活動】
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他自然科学の分野に属する
知識を要する業務に従事する活動
【該当例】
プログラマー、システムエンジニア等、情報工学・航空宇宙工学の業務に従事するもの
【在留期間】
5年、3年、1年、3月
※3月の在留期間の場合、在留カードは発行されません。
【立証資料】
1.在留資格決定の場合
(1)招へい機関の概要を明らかにする資料
ア.登記事項証明書(発行後三ヶ月以内のもの)
イ.直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後一年間の事業計画書)
ウ.案内書(公刊物等で招へい機関の概要が明らかになる場合は必要ありません)
(2)卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証する文書
ア.卒業証明書又は卒業証明書の写し
イ.申請人の履歴書
ウ.次のいずれかのもの
①従事しようとする業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻した大学等の卒業証明書又は
これと同等以上の教育を受けたことを証する文書
②在職証明書等で関連する業務に従事した期間(10年以上)を証するもの
(3)次のいずれかの一又は複数の文書で活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの
ア.招へい機関との雇用契約書の写し
イ.招へい機関からの辞令の写し
ウ.招へい機関からの採用通知書の写し
エ.アないしウに準ずる文書
2.在留期間更新の場合
(1)次のいずれかの一又は複数の文書で活動の内容、期間及び地位を証するもの
ア.在職証明書
イ.雇用契約書の写し
ウ.辞令の写し
エ.アないしウに準ずる文書
(2)次のいずれかで年間の収入及び納税額に関する証明書
ア.住民税又は所得税の納税証明書
イ.源泉徴収票
ウ.確定申告書控の写し
エ.アないしウに準ずる文書
【ポイント】
①「本邦の公私の機関」には、我が国の政府関係機関、地方公共団体関係機関、
公社、公団、会社、公益法人等のほか、本邦にある外国の政府関係機関、外国の
地方公共団体関係機関、国際機関、外国法人の支店・支社等も含まれる。
個人経営であっても、外国人が在留活動を行なうことができるに足る施設及び陣容を
有していればよい。
②「自然科学の分野に属する知識を要する」とは、学術上の素養を背景とする一定水準
以上の業務であることを示すものであり、上記の自然科学の分野のいずれかに
属する技術又は知識がなければできない業務であることを意味する。
単に上記の自然科学分野に関連するということだけでは足りない。
③「契約」には、雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれるが、特定の機関との継続的
なものでなければならない。
④国・公立の機関以外との契約に基づいて業務に従事する場合は、当該機関の事業が
適正に行なわれるものであり、かつ、安定性及び継続性の認められるものでなければならない。
⑤本邦の専修学校の専門課程を修了し、「専門士」の称号を有している者について、
その者の行なおうとする活動が「技術」の在留資格に該当し、就職先の職務内容と
専修学校における修得内容に関連性があれば、当該在留資格の変更が許可される。
【引用】
出入国管理のしおり
ひと目でわかる外国人の入国・在留資格案内
・・・【在留資格について】はこちらをクリックしてください>>
【在留資格】外交
2011年10月08日(土)10:15 AM
【本邦において行うことができる活動】
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際
慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者
又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動。
【該当例】
外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族
【在留期間】
外交活動の期間(在留期間の定めなし)
※在留期間の更新手続きはなし
【立証資料】
口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書
【引用】
出入国管理のしおり
ひと目でわかる外国人の入国・在留案内
関連リンク
- ご相談について
- ご依頼までの流れ
- 当事務所に依頼するメリット
- 会社設立業務
- 建設業許可申請
- 宅建業免許申請
- 離婚協議書作成業務
- ビザ申請を依頼するメリット
- 用語集
- 提携事務所
- リンク集
- サイトマップ
- トップページ
- お問い合わせ
過去のブログを検索
携帯サイト
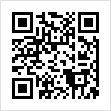
携帯電話をご利用の方は
QRコードを読み取って
モバイルサイトをご覧になれます。

当サイトは、
情報を安全に提供して頂くために、
「高度なセキュリティ」と「信頼性」で
定評のあるRapidSSLを利用しております。
プライバシーポリシー