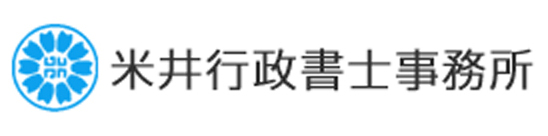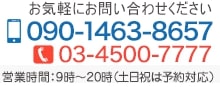外国人創業人材受入促進事業
2017年07月31日(月)2:15 PM
外国人の方が日本で起業する場合、「経営・管理ビザ」の取得が必要です。
(日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者を除く)
経営・管理ビザの取得には、日本人や永住者等を常勤で2名以上雇用するか500万円以上を
投資して起業に加え、事業所の確保が必要になります。
海外在住の外国人の方が上記要件を満たすには日本国内の協力者が不可欠であり、一人で
手続きを進めるのは極めて困難です。
今回行う、「外国人創業人材受入促進事業」は、入国管理局の審査前に東京都が事業計画等
の確認を行うことで、特例的に6か月間の在留資格が認められます。外国人の方は、この6か月
を活用することで、国内にいながら様々な準備活動を行うことができるようになります。
◎制度の概要
1.創業を志す外国人は、東京都へ事業計画書を提出し、創業活動を受けます。
⇒2週間程度で回答があり、確認後、「創業活動確認証明書」が発行されます。
2.東京入国管理局の審査後、6か月間の「経営・管理」ビザの許可を受けます。
3.6か月の期間中、「経営・管理」の要件を整え、ビザを更新します。
◎注意点
・本事業は、これから日本に上陸する外国人の方が対象です。
・ビジネスコンシェルジェ東京が、創業に向けた相談を行います。また、2か月に1度、
創業に向けた進捗状況の確認があります。
申請書類
・創業活動確認申請書
・創業活動計画書
・履歴書
・旅券の写し(写真・氏名・署名記載欄)
・上陸後6か月間の住居を明らかにする書類
(例:賃貸借契約書の写し、賃貸借の申込書の写し、など)
・その他、必要書類
(例:通帳の写しなど、現金預貯金残高がわかる書類)
外国人創業人材受入促進事業流れ
申請書類の作成
↓
↓
結果通知(東京都庁)
↓
入国管理局でビザ申請
↓
創業活動(許可の場合)
※創業活動の期間は6か月です。
↓
入国管理局でビザの更新
※事務所の確保、常勤で2名以上雇用又は500万円以上の出資が必要です。
申請先及び申請者
ビジネスコンシェルジュ東京
独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)本部7階
(東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル)
営業時間:9時30分~17時30分(土日、祝日、年末年始は休み)
◎申請者
(2)外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人の職員
で、地方入国管理局長が適当と認める者(現在、公益財団法人入管協会が該当)
管轄する地方入国管理局長に届け出た者。ただし、申請人本人が国外にいる場合には、
本邦の事業所の設置について、申請人本人から委託を受けている者(法人である場合に
あっては、その職員)であること。
お問合せ
お問合せに料金は一切かかりませんので、経営・管理ビザの件で
ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問合せ下さい。
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)
在留資格「介護」
2017年03月13日(月)6:35 PM
介護の在留資格が創設されます。
施行日は現段階で未定ですが、平成28年11月28日の交付日から1年以内に施行されます。
介護の在留資格は、介護福祉士の資格を有する外国人が介護施設等との契約に基づいて
介護(又は介護の指導)の業務に従事するための在留資格です。
対象者は、日本の介護福祉士養成施設(都道府県知事が指定する専門学校等)を卒業し、
介護福祉士の資格を取得した方です。
※ 施行日までの特例措置については、在留資格「介護」の特例措置をご覧下さい。
「介護」の在留資格で行うことができる活動
①介護に従事する活動
②介護の指導を行う業務に従事する活動
具体的な内容としては要介護者につき、食事、入浴、排泄などの身体的介護を含め、
介護全般に従事する活動及びそれらに従事する者に対しての指導業務となります。
在留資格「介護」の場合、食事、入浴、排泄などは専門知識及び技術に基づくもので
なければなりません。
在留資格「介護」の要件
①介護福祉士の資格を有する者であること
②本邦の公私の機関との契約に基づいて介護又は介護の指導を行う業務に従事する
活動を行おうとするものであること
③介護福祉士養成施設において介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したこと
④日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
◎ビザ取得までの一般的な流れ
在留資格【留学】
1.留学生として入国(在留資格留学)
↓
2.介護福祉養成施設で修学(2年以上)
↓
3.介護福祉士の国家資格取得
↓
4.在留資格変更許可申請(留学 ⇒ 介護)
↓
5.介護福祉士として業務に従事
◎注意事項
・平成29年度より、養成施設卒業者も国家試験合格が必要となります。
ただし、平成33年度までの卒業者には卒業後5年間の経過措置が設けられています。
・一旦帰国した上で「介護」の在留資格で新規入国することも可能です。
・在留状況に問題がなければ、在留期間の更新が可能であり、その更新回数に制限は
ありません。 配偶者及び子が「家族滞在」の在留資格で在留することも可能です。
お問い合わせ
在留資格「介護」の特例措置
2017年02月18日(土)1:52 PM
平成28年11月28日に出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律が公布されました。
公布の日から起算して1年以内に施行予定ですが、施行日までは下記の特例措置が適用
されます。
特例措置の内容
(1)特例措置の内容
平成29年4月から施行日までの間に、介護又は介護の指導を行う業務を開始しようと
する外国人から在留資格の申請があった場合には、「特定活動」(告示外)を許可する
ことにより、介護福祉士として就労することを認める。
(2)対象者
施行日までに社会福祉士及び介護福祉士法第39条第1号から3号までに規定する文部
科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設を
卒業する者及び既に介護福祉士養成施設等を卒業した者
申請方法
(1)在留資格変更の場合
下記必要書類を揃えて地方入国管理局へ申請(特定活動へ変更)
(2)新規に入国・在留を希望の場合
在外公館において特定活動の査証申請。
※在留資格認定証明書交付申請の対象にはなりません。
必要書類
・在留資格変更許可申請書 1通
・写真(4cm×3cm) 1葉
・パスポート及び在留カード 提示
・介護福祉士養成施設等の卒業証明書(又は卒業見込証明書)
※申請時に卒業見込証明書を提出した場合は、別途卒業証明書の提出が必要になります。
・介護福祉士登録証(写し)
・労働条件及び従事する業務内容を明らかにする文書(雇用契約書等)
※日本人が受ける報酬額と同等額以上の報酬額が必要です。
・勤務先の機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等、介護施設又は事業所の設立に
係る許可又は指定を受けた年月日が明示されたものに限る)
お問い合わせ
お問合せに料金は一切かかりませんので、ご不明な点が
ございましたらどうぞお気軽にお問合せ下さい!
契約書の作成・チェック
2017年01月01日(日)12:11 PM
日常生活を送るうえで、仕事上だけでなく、個人間でも様々な契約が発生します。
原則、契約は口約束だけでも効力が発生しますが、「言った言わない」などのトラブルに
なりやすいため、契約内容を書面にする事をおススメ致します。
弊所では、トラブルを予防する契約書の作成や、お客様の方で作成された契約書の確認業務を
行っていますので、契約書についてお悩み、ご不安な点がございましたら、どうぞお気軽に
お問合わせ下さい。 企業様だけでなく、個人の方からのご依頼も大歓迎です。
◎ご依頼までの流れ
・お問合せ
お電話、お問合せフォーム、E-mailにてお問合せ下さい。
↓
・面談
御社の業務や契約書についてのお悩みをお聞かせ下さい。
↓
・お見積
費用と納期んいついてお見積致します。
↓
・ご契約
費用やサービス内容にご納得して頂けたら、ご契約となります。
↓
・報酬額お支払い
↓
・業務開始
報酬額のお支払いを確認してから業務開始となります。
↓
・確認及び修正
お客様に作成した契約書をご確認して頂きます。
修正がある場合は、遠慮なくおっしゃって下さい。
↓
・納品
報酬額(税抜)
弊所の報酬額は以下のとおりです。
なお、お客様の状況により金額が変動する場合があります。
| 業務名 | 報酬額 |
| 各種契約書の作成 | 30,000円~ |
| 契約書の確認 | 15,000円~ |
お問合せについて
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。
TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com

LINE

WeChat
関連リンク
収容、面会・差入れ、仮放免
2016年12月29日(木)11:22 PM
◎収容
違反調査の結果、退去強制事由に該当すると疑う相当の理由がある場合は、入国管理局が発付
する収容令書により容疑者を収容することとなります。
(容疑者が出国命令対象者に該当すると認めるに足りる相当の理由があるときを除きます)
◎面会・差入れ
収容令書または退去強制令書により入国者収容所や地方入管局の収容場に収容されている外国
人(以下、「被収容者」という)との面会の手続や差入れの際の留意事項等の説明を行って
いますが、収容施設の実情により取扱時間等が異なる場合もありますので、詳細につきまし
ては、各収容施設に必ずご確認ください。
・面会案内
1.被収容者との面会または物品の授受を希望される方は、受付に申し出て必要な手続を
とってください。
2.面会を希望される方は、在留カード、特別永住者証明書また旅券その他身分を証明する
文書を提示してください。
3.面会の受付は、土曜日、日曜日及び休日を除く日の原則として9時から12時まで及び
13時から15時までですが、 収容施設により異なる場合もありますので、各収容施設
にご確認下さい。
4.面会時間は、原則として30分以内です。ただし,面会を希望される方が多い場合など
は、より多くの方が面会できるよう、それぞれの面会時間が短縮されることもあります
のでご了承下さい。
5.面会の際には、カメラ、ビデオカメラ、録音機及び携帯電話の持込みや使用はご遠慮
願います。
・面会者心得
1.面会時間を厳守すること。
2.係官に無断で物品の授受を行わないこと。
3.暗号、隠語等を使用し、又はその他の方法で通謀を図ろうとする行動をとらないこと。
4.以上のほか、すべて係官の指示に従うこと。
以上の各項目に違反した場合は、面会が中止になる場合があります。
・差入れの際の留意事項
基本的に次に該当する物については、収容居室内への持ち込みはできません。
また、飲食物についても保安上、衛生上の理由によりお断りする場合があります。
※具体的な差入れの可否につきましては各収容施設にご確認ください。
1.刃物類その他の用法により凶器や逃走に利用されるおそれがある金属製品、
ガラス製品及びひも類等
2.発火器具、引火物その他火災等の原因となるおそれのあるもの
3.劇毒物、睡眠薬、鎮静剤その他生命身体を害するおそれのある医薬品
4.酒類その他のアルコール含有飲食物
◎仮放免
収容者について、請求によりまたは職権で一時的に収容を停止し身柄の拘束を仮に解く
措置です。
収容令書による収容期間は「30日(但し、主任審査官においてやむを得ない事由があると
認めるときは、30日を限り延長することができる)」退去強制令書による収容は「送還
可能のときまで」と定められていますが、被収容者の健康上の理由、出国準備等のために
身柄の拘束をいったん解く必要が生じることもありますので、そのような場合に対応する
ために設けられた制度です。
(1)放免の請求
・仮放免を請求できる人
被収容者本人またはその代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹。
・仮放免の請求先
被収容者が入国者収容所に収容されている場合は、当該入国者収容所長に、また、地方入国
管理局の収容場に収容されている場合は、当該収容場を所管する地方入国管理局の主任審査
官に対して請求することになります。なお、仮放免の請求に当たっては、仮放免が許可され
た場合に被仮放免許可者の仮放免中の身元引き受け及び法令の遵守等の指導を確実に行って
いただくための身元保証人を決める必要があります。
・提出書類
仮放免許可申請書一通のほか、仮放免を請求する理由を証明する資料、身元保証人に関する
資料等が必要となります。
(2)仮放免の許可
仮放免の請求があった場合は、入国者収容所長又は主任審査官が、被収容者の情状及び
仮放免の請求の理由となる証拠並びにその者の性格、資産等を考慮してその者を仮放免
することができると定められています。
入国者収容所長又は主任審査官は、仮放免の許可に際して、300万円以下の保証金を
納付させ、かつ、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と
認める条件を付するものとされております。
なお、保証金については入国者収容所長または主任審査官が適当と認めたときに限り、
被収容者以外の者が差し出した保証書をもって保証金に代えることを許すことができ
ますが、保証書には、保証金額及びいつでもその保証金を納付する旨を記載しなければ
なりません。
(3)仮放免の取消し
・取消事由
仮放免許可を受けた外国人が、①逃亡した、②逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある、
③正当な理由がないのに呼出しに応じない、④仮放免に付された条件に違反したときは、
入国者収容所長または主任審査官は,仮放免を取り消すことができると定められています。
・収容
仮放免が取り消された場合、仮放免されていた者は、収容令書又は退去強制令書により、
入国者収容所、地方入国管理局の収容場その他法務大臣又はその委任を受けた主任審査
官が指定する場所に再び収容されることとなります。
・保証金の没取
仮放免が取り消されたときは、仮放免されたときに納付した保証金が没取されることに
なります。
没取には全部没取と一部没取があり、取消しの理由が前記①及び③の場合は保証金の全額、
その他の理由による取消しの場合は保証金の一部が没取され、一部没取の場合における
金額は、事情に応じて入国者収容所長又は主任審査官が決定することとなります。
(4)その他
退去強制令書により収容されていた者が仮放免中に自費出国する場合、または仮放免の許可
に期限が付されている場合であって、期間満了により再度収容されたときは、仮放免の取消
しではないので保証金は全額還付されます。
お問合せについて
お問合せに料金は一切かかりませんので、どうぞお気軽に
お問合せください!
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)
TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com
関連リンク
パスポート申請時の本人確認書類
2016年11月18日(金)10:38 PM
◎1点で良いもの
・有効な日本国旅券
・失効後6か月以内の日本国旅券(氏名及び写真で申請者が確認できるもの)
・運転免許証(国内で発行された国外運転免許証及び仮運転免許証を含む。)
・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)
・個人番号カード(マイナンバーカード)
・写真付き住民基本台帳カード
・写真付き身体障害者手帳(写真貼替え防止がなされているもの)
・船員手帳
・海技免状
・小型船舶操縦免許証
・猟銃・空気銃所持許可証
・戦傷病者手帳
・宅地建物取引士証
・電気工事士免状
・無線従事者免許証
・認定電気工事従事者認定証
・特種電気工事資格者認定証
・耐空検査員の証
・航空従事者技能証明書
・運航管理者技能検定合格証明書
・動力車操縦者運転免許証
・教習資格認定証(猟銃の射撃教習を受ける資格の認定証で都道府県公安委員会発行のもの)
・警備業法第二十三条第四項に規定する合格証明書
・官公庁(共済組合を含む。)がその職員に対して発行した写真の貼られた身分証明書
・独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人が
その職員に対して発行した写真の貼られた身分証明書
◎2点必要なもの:Aの中から2点またはAとBの中から1点づつ
【Aの確認書類】
・健康保険被保険者証
・国民健康保険被保険者証
・船員保険被保険者証
・介護保険被保険者証
・共済組合員証
・後期高齢者医療被保険者証
・国民年金手帳
・国民年金証書
・厚生年金保険年金証書
・船員保険年金証書
・共済年金証書
・恩給証書
・印鑑登録証明書と実印
【Bの確認書類】
・失効した日本国旅券(失効後6か月を越えるもの)
・学生証・生徒手帳(いずれも写真付きのもの)
・会社等の身分証明書(写真付きのもの)
・公の機関が発行した資格証明書(写真付きのもの)※
・母子手帳
お問合せ
お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せ下さい!
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。
TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com
関連リンク
建築士事務所登録
2016年10月27日(木)5:25 PM
以下に該当する方は、建築士法の定めるところにより、建築士事務所の登録が必要に
なります。
(1)他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業として行おうとする建築士。
(2)建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業として
行う方。
建築士事務所の登録には、「専任の管理建築士」が必要になります。
管理建築士になるには、建築士法第24条第 2 項により建築士として3年以上の設計等の
業務に従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了することが必要です。
管理建築士の「専任」とは、事務所に常勤し、もっぱら管理建築士の職務を行う必要があり
ます。従って、雇用契約等により、事業主と継続的な関係を有し、休業日を除いて通常の
勤務時間中は、その事務所に勤務している必要があります。
建築士事務所登録までの流れ
(1)必要書類の収集及び作成
↓
(2)申請書提出
↓
(3)仮審査
↓
(4)手数料の納付
↓
(5)受理
↓
(6)本審査
↓
(7)登録
↓
(8)登録の通知
・登録までの期間は、申請書類受理後、5~10日程度です。
・一級建築士事務所の登録費用は、18,500円となります。
・二級建築士事務所の登録費用は、13,500円となります。
・登録は建築士事務所所在地の都道府県知事宛になります。
支店が他の都道府県にある場合は、各都道府県で建築士事務所登録が必要になります。
建築士事務所登録に必要な書類
◎法人の場合
| 提出書類 | 摘要 |
| 建築士事務所登録申請書 | 法人実印に法人名が入っていない場合は、 印鑑証明書が必要 |
| 所属建築士名簿 | 管理建築士を筆頭に全員記入 |
| 役員名簿 | 代表取締役を筆頭に役員全員を記入 |
| 業務概要書 | 直近5年間の主なもの (新規申請時は不要) |
| 略歴書(登録申請者用) | 代表者について記入(要個人の印鑑) |
| 略歴書(管理建築士用) | 管理建築士個人の印鑑が必要です |
| 誓約書 | 記名捺印(法人印)するか申請者本人 が署名 |
| 定款の写し | 余白に法人の実印を押印 |
| 履歴事項全部証明書 | 発行後3か月以内のもので原本を提出 |
| 事務所の賃貸借契約書等の写し | 所在地が履歴事項全部証明書に記載されて いる場合は不要 |
| 法人事業税納税証明書 | 都税事務所発行で発行後3か月以内のもの(原本提出) |
| 住民票 | 原本提出で発行後3か月以内のもの |
| 建築士免許証(原本提示) | 新規申請のみ |
| 建築士免許証の写し | |
| 前職場の退職証明(退職後6か月以内の場合) | 個人事業をしていた場合は、直前期の確定 申告書の写し(第一面・二面) |
| 専任証明 | 登録申請者が兼任する場合は不要 |
| 管理建築士講習修了証の写し |
◎個人の場合
| 提出書類 | 摘要 |
| 建築士事務所登録申請書 | 認印で可 |
| 所属建築士名簿 | 管理建築士を筆頭に全員記入 |
| 業務概要書 | 直近5年間の主なもの (新規申請時は不要) |
| 略歴書(登録申請者用) | 申請者個人の認印を捺印 |
| 略歴書(管理建築士用) | 管理建築士個人の印鑑が必要です |
| 誓約書 | 記名捺印(認印)するか申請者本人 が署名 |
| 開設者の住民票 | 発行後3か月以内の原本提出 |
| 事務所の賃貸借契約書等の写し | 上記住民票に記載されている場合は不要 |
| 個人事業税納税証明書 | 発行後3か月以内の原本提出 |
| 管理建築士の住民票 | 発行後3か月以内の原本提出 |
| 建築士免許証(原本提示) | 新規申請のみ |
| 建築士免許証の写し | |
| 前職場の退職証明(退職後6か月以内の場合) | 個人事業をしていた場合は、直前期の確定 申告書の写し(第一面・二面) |
| 専任証明 | 登録申請者が兼任する場合は不要 |
| 管理建築士講習修了証の写し |
◎管理建築士に関する注意事項
・1人の建築士が複数の建築士事務所の管理建築士になることはできません。
・1つの建築士事務所に複数の管理建築士を置くことはできません。
・派遣労働者は管理建築士になれません。
当事務所の報酬額
当事務所の報酬額は以下のとおりです。
別途実費がかかります。
| 業 務 名 | 報 酬 額 |
| 建築士事務所登録 | 55,000円 |
| 一級建築士事務所登録手数料 | 18,500円 |
| 二級建築士事務所登録手数料 | 13,500円 |
お問い合わせ
お問合せに料金は一切かかりませんので、建築士事務所登録に
ついてご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問合せ下さい。
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。
TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com
関連リンク
上陸特別許可
2016年07月11日(月)5:00 PM
上陸特別許可とは、以下の上陸禁止期間中であっても、法務大臣の裁量により上陸が可能に
なる手続きです。
上陸を希望する理由、上陸拒否になった理由、上陸拒否事由が発生してからの期間、人道的な
配慮の必要性、その他諸般の事情を考慮して上陸可能かどうかを判断します。
◎上陸拒否事由
過去に不法残留等を理由に退去強制された者や出国命令を受けて出国した者は、原則と
して、以下の一定期間日本に上陸することはできません。
(1)過去に退去強制されたり、出国命令を受けて出国したことがない場合の上陸拒否期間
は、退去強制された日から5年
(2)過去に退去強制されたり、出国命令を受けて出国したことがある場合の上陸拒否期間
は、退去強制された日から10年
(3)出国命令により出国した場合の上陸拒否期間は、出国した日から1年
(4)日本又は日本以外の法令に違反して1年以上の懲役又は禁錮等に処せられた場合等の
上陸拒否期間は無期限(長期拒否)
上陸特別許可の要件
以下の要件を全て満たす事が必要です。
・日本人、特別永住者、永住者、定住者と婚姻が成立しており、婚姻の信憑性を立証できる
こと。
・在留資格認定証明書交付申請時において、1年以上婚姻が続いていること。
・在留資格認定証明書交付申請時において、退去強制後2年以上経過していること。
※配偶者との間に子供がいる場合は、上記期間が短くなる場合があります。
子供がいない場合は退去強制後、外国にいるの配偶者のもとを複数回訪れていること。
・執行猶予付き有罪判決を受けた後に退去強制された場合は、在留資格認定証明書交付申請
時において、執行猶予期間も経過していること
※婚姻の信憑性が高い場合や子供がいる場合は、執行猶予期間が経過していなくても許可
される場合があります。
上陸特別許可の流れ
上陸特別許可という申請手続きはなく、海外からの呼び寄せと同じく「在留資格認定証明書
交付申請」手続きをします。
・必用資料の収集、申請書の作成
日本にいる配偶者、行政書士などが必要書類の収集、申請書類の作成を行い、外国にいる
申請人に代わり入国管理局に在留資格認定証明書交付申請を行います。
通常の在留資格認定証明書交付申請手続きに比べて立証資料は多くなります。
⇓
・入国管理局の審査
標準審査期間4か月~6か月程度です。
⇓
・審査結果の通知
書留郵便で結果が届きます。
⇓
・在留資格認定証明書の郵送
入国管理局から送られてきた在留資格認定証明書を外国にいる申請人に送ります。
申請人は、在留資格認定証明書を持って自国にある日本大使館や領事館でビザの
申請をします。
ビザ発給までの期間は、一般的に一週間前後です。
⇓
・入国
在留資格認定証明書の期限は発行日から3か月となりますので、必ず3か月以内に
入国するようにしてください。
なお、在留資格認定証明書が発行されたからといって必ず入国できるとは限りま
せんので、ご注意ください。
弊所の酬額等
弊所の税込報酬額及び実費は以下のとおりです。
お客様の状況により、料金が変動する場合がございますので、ご了承下さい。
| 業 務 名 | 料 金 |
| 在留資格認定証明書交付申請(上陸特別許可) | 330,000円~ |
| 切手代 | 434円 |
| 入国管理局への申請手数料 | 無料 |
お問合せについて
TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com
お問合せフォーム

LINE

WeChat
関連リンク
医療法人設立後の届出(東京都)
2016年06月30日(木)2:07 PM
◎事業報告等提出書
医療法人は、毎会計年度終了後3か月以内に以下の必要書類を届出る必要があります。
・事業報告書
・財産目録
・貸借対照表
・損益計算書
・監事の監査報告書
※書類のダウンロードはこちら
◎役員変更届
医療法人は、役員に変更があった場合、以下の書類を遅滞なく届出る必要があります。
(重任の場合も含む)
(1)新たに役員に就任する場合
・ 役員改選を行った会議(社員総会、理事会、評議員会)の議事録(写しの場合は
原本と相違ない旨の理事長の証明があること。)
・ 新役員の履歴書(医療法第46条の2第2項の役員欠格事由に該当しない旨の誓約が
あること。)
・ 新役員の役員就任承諾書
・ 新役員の印鑑登録証明書
・ 理事長が変更になる場合は、医師(歯科医師)免許証の写し
・ 開設・経営する営利法人等の役職員を兼務する場合は、兼務する営利法人等の規模・
取引内容が確認できる書類
(2)任期途中で役員を辞任する場合
・ 辞任を承諾した会議(社員総会、理事会、評議員会)の議事録(写しの場合は原本と
相違ない旨の理事長の証明があること。)
・ 辞任届
※ 管理者たる理事が管理者の職を退いたときは、理事の職を失います。
(3)任期満了により役員を重任する場合・退任する場合
ア 重任・・・・会議(社員総会、理事会、評議員会)の議事録(写しの場合は原本と
相違ない旨の理事長の証明があること。)
・履歴書(以前の役員変更届から経歴に変更がある場合のみ)
・就任承諾書(原則は不要ですが、重任する役員が選任された会議に欠席している場合
や、内諾している場合は必要です。)
イ 退任・・・・会議(社員総会、理事会、評議員会)の議事録(写しの場合は原本と相違ない
旨の理事長の証明があること。)
(4)役員が死亡した場合
死亡を確認できる書類(該当者に係る除籍事項証明書(除籍謄抄本)等(原本)又は
死亡診断書の写し)
(5)改姓・住所変更
ア 改姓・・・・該当者に係る戸籍事項証明書(戸籍謄抄本)(原本)
イ 住所変更・・・・従前の住所の記載がある住民票(原本)
◎登記届
医療法人は、登記を行なった際に登記事項についての届出を遅滞なく東京都知事宛にする
必要があります。登記届は毎年必ずするものと、その都度するものの2種類に分かれます。
・毎年必ず登記するもの
資産総額の変更(決算終了後、資産の総額を登記します。) 登記の時期は、事業年度終了
後2か月以内です。
・その都度登記するもの
理事長の変更、 定款(寄附行為)変更認可による登記事項の変更、 事務所の所在地の
変更
※登記の時期は、主たる事務所の所在地においては変更が生じた後2週間以内、 従たる
事務所の所在地においては、変更が生じた後3週間以内です。
◎定款変更届
医療法人の事務所の所在地のみを変更した場合は、定款変更届を、東京都知事あてに提出
しなければなりません。 ただし、主たる事務所を他の道府県へ移転する場合は、認可
権者の変更も必要なため、 定款変更認可申請が必要になります。
その他定款の条文を変更する必要がある場合も、定款変更 届の提出ではなく、定款変更
認可申請を行い、東京都知事の認可を受けな ければなりません。
なお、定款変更届に必要な書類は以下のとおりです。
・ 定款の新旧条文対照表
・ 新定款
・ 定款を変更することを決議した社員総会の議事録(写しの場合は原本と相違ない旨の
理事長の証明があること。)
・変更後の事務所を登記した登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
届出先
上記届出の提出方法、原則として郵送になります。
控えの返送が必要な場合は、返送先を記入し必要額の切手を貼付した返信用封筒の同封が
必要となります。
【送付先】
〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都福祉保健局医療政策部医療安全課医療法人 係
お問合せについて
お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞおお気軽にお問合せください!
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。
TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com
お問合せフォーム
関連リンク
再婚禁止期間の短縮等について
2016年06月07日(火)10:52 PM
平成28年7月1日から法律が改正され、女性の再婚禁止期間が6か月から100日に短縮
されます。 改正の概要は以下のとおりです。
◎概要
1.女性の再婚禁止期間を前婚の解消又は取消しの日から起算して100日とする。
2.女性が前婚の解消若しくは取消しの時に懐胎(妊娠)していなかった場合又は女性が
前婚の解消もしくは取消しの後に出産した場合には再婚禁止期間の規定を適用しない。
前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過していない女性が再婚する場合の
婚姻の届出が平成28年6月7日から以下のとおりになります。
①民法第733条第2項に該当する旨の証明書について
「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」が必要になります。
この書類は、再婚をしようとしている本人である女性を特定する事項のほか、(1)本人が
前婚の解消又は取消しの日であると申し出た日より後に懐胎していること。(2)同日以後
の一定の時期において懐胎していないこと。(3)同日以後に出産したことのいずれかに
ついて診断を行った医師が記載した書面をいいます。
なお、医師の診察を受ける際は、「前婚の解消又は取消日」を申告する必要があります。
この日について誤って別の日を医師に申告した場合には、本証明書を作成してもらったと
しても、再婚禁止期間内の再婚が認められない場合がありますので、ご注意ください。
②届出の受理について
前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過していない女性を当事者とする婚姻の
届出について、上記の「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」が添付され、「女性が
前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合」又は「女性が前婚の解消又は取消し
の後に出産した場合」に該当すると認められた場合には、その他の婚姻要件を具備している
限り、その届出は受理され、婚姻することが可能となります。
③戸籍の記載について
届出が受理されると、妻の身分事項欄には婚姻事項とともに「民法第733条第2項」による
婚姻である旨が記載されることになります。
◎注意点
前婚の解消又は取消しの日から100日を経過していない女性と婚姻する際に「民法第733条
第2項に該当する旨の証明書」が添付されていない場合には、婚姻の届出は受理されません。
ただし、これまで証明書がなくても再婚禁止期間内にされた婚姻の届出について受理されて
いた類型(前婚の夫と再婚する場合など)については、今後も証明書がなくても婚姻の届出
は受理されます。
お問合せについて
お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
関連リンク
- ご相談について
- ご依頼までの流れ
- 当事務所に依頼するメリット
- 会社設立業務
- 建設業許可申請
- 宅建業免許申請
- 離婚協議書作成業務
- ビザ申請を依頼するメリット
- 用語集
- 提携事務所
- リンク集
- サイトマップ
- トップページ
- お問い合わせ
過去のブログを検索
携帯サイト
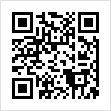
携帯電話をご利用の方は
QRコードを読み取って
モバイルサイトをご覧になれます。

当サイトは、
情報を安全に提供して頂くために、
「高度なセキュリティ」と「信頼性」で
定評のあるRapidSSLを利用しております。
プライバシーポリシー