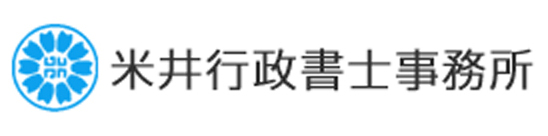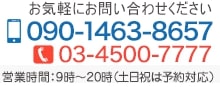ビザの受領方法
2019年11月27日(水)12:25 PM
ビザ申請が許可された場合、以下の書類が必要になります。
許可の受領期限はハガキに記載されていますので、原則その期限内に許可の受領を行って
下さい。
期限内の受領が難しい場合は、必ず担当部門にご相談下さい。
なお、許可の受領を受けず2か月を経過した場合は、日本に滞在できなくなりますので、
ご注意ください。
※在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ)の場合は除きます。
【必要書類】
・パスポート 原本
・在留カード 原本
・収入印紙(結果通知書に記載されている金額をご用意下さい)
・申請受付票(申請時にもらったもの)
※無くても許可の受領は可能です。
・結果通知書(出入国在留管理局から届いたハガキ)
・手数料納付書(ご自身の条件に合うものを下記からダウンロードして下さい)
手数料納付書(ビザ更新)
※手数料納付書右上の日付(西暦で記入)と右下の署名欄をご記入いただき、収入印紙を
貼付してください。
【受領できる者】
・申請人
・法定代理人
・申請取次者(行政書士等)
・申請人が16歳に満たない場合又は疾病その他の事由により、出頭することができない場合に
おいて、当該外国人の親族又は同居若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局が適当
と認める者(疎明資料が必要になります)
※両親が16歳未満の子の許可を受領する場合、手数料納付書の署名欄に両親のお名前を記入
を記入し、その後に署名者と申請人との関係をご記入下さい。
お問合せについて
お問合せに料金は一切かかりませんので、許可の受領について
ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問合せ下さい。

LINE

WeChat
関連リンク
子の養育のための親の呼び寄せ(高度専門職)
2019年10月18日(金)6:07 PM
通常、両親の中長期日本滞在は認められませんが、高度専門職外国人もしくは、その配偶者の
7歳未満の子(養子を含む)を養育するため、または高度専門職外国人の妊娠中の配偶者もし
くは、妊娠中の高度専門職外国人に対し、介助、家事その他の必要な支援をするため、高度
専門職外国人又はその配偶者の両親(養親を含む)の中長期日本滞在が認められます。
呼び寄せの要件
下記のいずれにも該当する事が必要です。
1.申請人の子、又は子の配偶者である高度専門職外国人と同居すること。
2.申請人の入国の時点において、高度専門職外国人の世帯年収が800万円以上であること
※世帯年収とは、高度専門職外国人+その配偶者の報酬額となります。
3.高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子の養育を行おうとするものである
こと、又は高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人
に対し介助、家事その他の必要な支援を行おうとするものであること。
4.申請人が高度専門職外国人の父又は母である場合は、高度専門職外国人の配偶者の父
又は母が特定活動告示34号の活動を指定されて在留しているものでないこと。
申請書類
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
※「特定活動」の様式、「○上記以外の目的」を選択
2.申請人の写真(縦4cm×横3cm) 1葉
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付。
3.返信用封筒 1通(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手を貼付したもの)
4.高度専門職外国人の世帯年収を証する文書1通
課税証明書、納税証明書など
5.高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育しようとする場合
(1)次のいずれかで、申請人と高度専門職外国人又はその配偶者と身分関係、及び養育
しようとする者が高度専門職外国人又はその配偶者の7歳未満の子であることを証
する文書
ア.戸籍謄本
イ.婚姻届出受理証明書
ウ.結婚証明書(写し)
エ.出生証明書(写し)
オ.上記アからエまでに準ずる文書
(2)高度専門職外国人、高度専門職外国人の配偶者及びその7歳未満の子の在留カード
又はパスポートの写し
6.高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し、
介助、家事その他の必要な支援を行おうとする場合
(1)次のいずれかで申請人と高度専門職外国人又はその配偶者との身分関係を証する文書
ア.戸籍謄本
イ.婚姻届出受理証明書
ウ.結婚証明書(写し)
エ.出生証明書(写し)
オ.上記アからエまでに準ずる文書
(2)高度専門職外国人又はその配偶者が妊娠中であることを証する文書(診断書、母子
健康手帳の写し等)
(3)高度専門職外国人及び高度専門職外国人の配偶者の在留カード又はパスポートの写し
◎備考
・日本で発行される書類は、申請日前3か月以内に発行されたものが必要になります。
・審査の過程で別途書類が必要になる場合があります。
当事務所の報酬額および実費額
当事務所の報酬額(税抜)および実費額は以下の通りです。
お客様の状況により、金額が変動する場合がございますので、その際はご了承下さい。
【在留資格認定証明書交付申請料金】
| 業 務 名 | 報 酬 額 等 | 業 務 内 容 |
| フルサポートプラン | 80,000円 | 申請書類の作成、必要書類などの 各種アドバイス、申請代行 |
| コンサルティングプラン | 45,000円 | 必要書類などの各種アドバイス、 申請書類のチェック、申請代行 |
| チェックプラン | 24,000円 | 申請書類のチェック |
| 申請書類の代理取得 | 実費+報酬額 | 代理取得をご希望される場合のみ 取得部数等によって金額が変わります |
※申請先が東京出入国在留管理局の場合、申請時の交通費はかかりません。
それ以外の出入国在留管理局に申請する場合は、別途交通費がかかります。
お問合せについて
お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せ下さい!
関連リンク
永住者及び高度専門職2号の方の在留カードの有効期間更新
2019年10月11日(金)1:06 PM
「永住者」及び「高度専門職2号」の在留資格をお持ちの方は、在留カードの有効期限までに
更新手続きが必要になります。 手続きは有効期限の2か月前から可能となりますので、早めに
お手続きするようにして下さい。
※有効期間が16歳の誕生日までとなっている方もお手続きが必要です。
◎必要書類
・在留カード有効期間更新申請書
・申請人の写真(縦4cm×横3cm) 1葉
提出日前3か月以内に撮影されたもので、無帽・無背景・鮮明であるもの
16歳未満の方は写真の提出不要です。
※在留カードの有効期間の満了日が「16歳の誕生日」とされている方が申請する場合
には、写真の提出が必要になります。
・パスポート 原本(提示)
・在留カード 原本(提示)
※申請時にパスポートの有効期限が切れていたり、有効期間内に申請できなかった際は、
別途書類が必要になります。
旅券が未取得である理由書:パスポートの有効期限が切れている場合などに必要。
陳述書:有効期間内に申請できなかった場合に必要です。
※パスポート及び在留カード両方の有効期限が切れている場合、住民票が必要になります。
【注意事項】
・一緒に住んでいる人が代わりに来る時は、3か月以内に取得した住民票が必要になります。
マイナンバーの記載がなく、それ以外の事項については省略されていないもの
・在留カードを紛失した方は、警察で在留カードを紛失したことの証明書をもらって
下さい。
◎標準処理期間
原則、即日交付
◎申請者
・申請人本人(16歳未満の者を除く)
・代理人
(1)申請人本人が16歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら出頭して申請する
ことができない場合には、申請人本人と同居する16歳以上の親族(要 診断書)
(2)申請人本人の依頼による申請人本人と同居する16歳以上の親族(要 委任状)
・取次者(行政書士や弁護士など)
◎申請先
住居地を管轄する地方出入国在留管理局
◎報酬額
16,500円(税込)
別途、実費がかかります。
お問合せについて
お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せ下さい!
関連リンク
出張のお知らせ
2019年09月09日(月)1:55 PM
9月12日(木)から9月15日(日)まで出張のため、その期間中のお問い合わせは下記メール
か、お問合せフォームにてお願い致します。
ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解の程よろしくお願い致します。
E-mail:yonei@yonei-office.com
登録支援機関の登録申請(特定技能)
2019年03月12日(火)6:15 PM
登録支援機関とは、外国人(特定技能外国人)を受け入れる機関が、特定技能外国人支援計画
の策定・実施を自身で行うことが難しい際に代わりに策定及び実施を行う機関になります。
登録支援機関の登録基準、要件、義務は以下のとおりです。
◎登録を受けるための基準
・機関自体が適切
5年以内の出入国、労働法令違反がないこと
・外国人を支援する体制があること
外国人が理解できる言語で支援できる。
◎登録の要件
・支援責任者及び1名以上の常勤の支援担当者を選任していること。
・以下のいずれかに該当すること
(1)登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期滞在者(就労資格に
限る)の受入実績があること
(2)登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業と
して、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること。
(3)選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る)の
生活相談業務に従事した経験を有すること。
(4)上記の他、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務
を適正に実施できると認められていること。
・外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有して
いること。
・1年以内に責めに帰すべき事由により、特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者
を発生させていないこと。
・支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと。
・5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し、不正又は著しく不当な行為を行って
いないこと。
◎登録支援機関の義務
・外国人への支援を適切に実施
・出入国在留管理庁への各種届出
※上記を怠ると登録支援機関の登録が取消されることがあります。
提出書類(登録支援機関の登録申請時)、提出先等
◎提出書類
・登録支援機関の登録(更新)申請に係る提出書類一覧・確認表
・手数料納付書(収入印紙貼付)
新規登録:28,400円分の収入印紙
・登録支援機関登録申請書
・登記事項証明書(法人として申請する場合)
・定款又は寄付行為の写し(法人として申請する場合)
・役員の住民票(法人として申請する場合)
・登録支援機関の役員に関する誓約書(法人として申請する場合)
住民票の提出を省略する役員がいる場合に提出が必要です。
・住民票(個人として申請する場合)
※本籍地の記載があり、マイナンバーの記載がないもの
・登録支援機関の概要書
・登録支援機関誓約書
・支援責任者の就任承諾書及び誓約書
・支援責任者の履歴書
・支援担当者の就任承諾書及び誓約書
・支援担当者の履歴書
・支援委託手数料に係る説明書
・返信用封筒(角型2号封筒) 1通
封筒に送付先を明記してください。
レターパックプラスでも可。
・簡易書留用切手(470円分)
※別途、書類が必要になる場合があります。
◎提出先
所在地又は住居地を管轄する出入国在留管理局
「出入国在留管理局の管轄」
◎提出方法
出入国在留管理局への持参又は郵送
郵送の場合は書留等(対面で届き、受領の際に署名や捺印の必要があり、信書を送れる
方式であること。)
また、封筒の表面に「登録支援機関申請書在中」と朱書きが必要です。
◎標準審査期間
2か月(東京出入国在留管理局の場合は3~4か月)
報酬額及び実費(新規登録)
| 項目 | 金額 |
| 登録支援機関登録申請報酬額 | 165,000円 |
| 収入印紙代 | 28,400円 |
| 簡易書留用切手代 | 470円 |
| 申請時送料 | 520円程度 |
お問い合わせ
お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せ下さい!
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。
TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com
関連リンク
出生による永住許可申請
2019年02月15日(金)11:51 AM
両親のいずれかが永住者で、その夫婦に子供が生まれた場合、出生から30日以内に永住許可
申請することにより、生まれた子が「永住者」の在留資格を取得できる可能性があります。
手続きまでの流れは以下のようになりますが、前述したように出生日から土日祝を含む
「30日以内」となりますので、急いで各種手続きをする必要があります。
◎永住許可申請までの流れ
・出生
↓
・市区町村役場(役所)で出生の届出(出生から14日以内)
出生届受理証明書又は出生届記載事項証明書 1通、住民票 1通を取得
住民票は、生まれた子供についても記載があり、マイナンバー及び住民票コードが省略
されていて、それ以外の事項については省略されていないものが必要になります。
↓
・子供の国籍国の駐日大使館・領事館で出生届及びパスポート取得手続き
永住許可申請時にパスポートがなくても永住許可申請は可能です。
※上記手続きは、永住許可申請後でも問題ありません。
↓
・永住許可申請(出生から30日以内)
必要書類(例)・報酬額
・永住許可申請書
・出生届受理証明書又は出生届記載事項証明書 1通
・住民票 1通
※生まれた子も含む家族全員が記載されていて、マイナンバー及び住民票コードが省略され
ているもの。
・ご両親の職業を証明する資料
(1)会社勤務の場合 : 在職証明書 1通(取締役の場合は履歴事項全部証明書でも可)
(2)自営業の場合:確定申告書の写し、許認可証の写し(ある場合のみ)
※確定申告書は税務署の受付印があるものになります。
電子申請をしている場合は、電子申請したことが分かる書面(メール詳細や受信
通知)も必要になります。
(3)その他の場合:職業に関する説明書(書式自由)及びその他の資料
・ご両親の直近1年度の所得及び納税状況が分かる資料
(1)会社員及び自営業の場合 : 住民税の課税(非課税)証明書及び納税証明書 各1通
(2)その他の場合 : 預貯金通帳の写し、左記に準ずるもの、課税(非課税)証明書及び
納税証明書 各1通
※状況により、直近年分の源泉徴収票が必要になる場合があります。
・ご両親の年金関係資料
ねんきんネットの写しや、被保険者記録照会回答票、被保険者記録照会納付Ⅰ及び納付Ⅱ
※直近年度の年金が給与天引きされていない場合は、年金納付時の領収書の写しも必要
になります。
・ご両親の健康保険証の写し
※直近年度の健康保険料が給与天引きされていない場合、国民健康保険料(税)納付証明書
及び国民健康保険料(税)の領収書の写しが必要になります。
・直近年度分のご両親の住民税納付時の領収書の写し
住民税が給与天引きされている場合は不要です。
・ご両親のパスポートの写し(身分事項のページ)
・ご両親の在留カードの写し(表裏)
・身元保証書 1通
・了解書
・質問書 1通
・旅券が未取得である理由書 1通
永住許可申請時までにお子様のパスポートの用意ができない場合のみ必要になります。
・収納年月日が明記された直近2年分の社会保険料納入確認書
扶養者が社会保険の加入義務のある事業主である場合のみ必要になります。
【報酬額】
55,000円
※上記は東京出入国在留管理局及び東京出入国在留管理局松戸出張所に申請する場合の
金額になります。
お問合せ
お問合せに料金は一切かかりませんので、お子様の永住許可申請に
ついてご不明な点がございましたら、以下の方法にてどうぞお気軽
にお問合せ下さい。
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)
TEL:03-4500-7777
在留カードの再交付申請
2018年11月08日(木)3:37 PM
紛失、盗難などによって在留カードを紛失した場合は、その事実を知った日から14日以内に
在留カードの再交付申請が必要になります。
◎必要書類
・在留カード再交付申請書
・写真 1枚(縦4cm×横3cm)
※16歳未満の方は不要です。
・紛失等を証明する資料
遺失届出証明書(在留カードの届出受理内容について)、盗難届出証明書、り災証明書等
(提出できない場合はその理由及び紛失した状況を記載した理由書)
・パスポート 原本提示
※パスポートを提示できない時はその理由書
・資格外活動許可証を提示(同許可書の交付を受けている場合のみ)
在留カードが即日交付されず、後日受領する場合は、申請受付票、パスポートなどの提出が
必要になります。
当事務所の報酬額
お客様の状況により別途費用がかかったり、金額が変動する場合があります。
| 在留カードの再交付申請(報酬額) | 22,000円 |
| 交通費(東京出入国在留管理局の場合) | 1,500円 |
※在留カードが即日交付されない場合、上記金額+5,500円がかかります。
お問合せについて
在留カード再交付についてのお問合せに料金は
一切かかりませんので、以下方法にてどうぞお気軽に
お問合せください!
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)
電気通信事業の届出
2018年10月17日(水)4:46 PM
電気通信事業を行うには、登録又は届出が必要になり、一般的に以下のような事業が該当
します。また、これらの電気通信役務の卸・再販を行う場合も、「登録」又は「届出」を
要する電気通信事業に該当します。
| 加入電話 | ISDN | 中継電話 | 国際電話 | 公衆電話 |
| FAX | 電報 | 携帯電話 | PHS | 移動端末データ |
| データ伝送 | IP電話 | ISP | インターネット関連サービス | 広域イーサネット |
| インターネット関連サービス(電子メール、インスタント・メッセンジャー、IX等 | ||||
| IP-VPN | 専用役務 | 無線呼出し | ||
◎登録又は届出を要する主な事例は以下のとおりです。
・転送電話サービス
・電話等受付自動代行サービス
・コンテンツの媒介
・電子メールマガジンの媒介
・オフィスやマンションの管理会社等が入居者に提供するインターネット
・レンタルサーバやホスティングサービス
・利用者間のメッセージの媒介(サービスの一部として提供するものを含む)
・クローズドチャット
・出会い系サイト
・機器の貸与と併せた電気通信役務の提供
・MVNO(Mobile Virtual Network Operator)
・チャンネル貸し
・リビリング
・国外サーバを用いた電子メール
・関連企業間のネットワークの運営
・Webサイト上のグリーティングカードの運営
・電子委任状の媒介サービス
・ドメイン名の名前解決サービス
◎登録及び届出を要しない事例
・放送
・企業等における内線電話やLAN
・サーバの設置場所貸し
・携帯電話等の契約の取次等を行う代理店
・ネット通販等実店舗等で提供するサービスのインターネット経由での提供
・個人や企業によるWebサイトの開設(専ら自分の情報の提供を目的とするもの)
・電子メールマガジンの発行
・メールフォーム
・ホテルインターネット
・ホテル電話
・非常災害発生時における緊急通信のための電気通信設備の利用
・日本郵便株式会社に対する鉄道運送業者の通信設備の提供
・電子メールマガジンの配信
・各種情報のオンライン提供
・Webサイトのオンライン検索
・ソフトウェアのオンライン提供
・オンラインストレージ
・インターネットカフェ
・電子掲示板
・オープンチャット
・インターネット上のショッピングモール
・個人が趣味で運営する電子メール
※登録、届出が必要な事例及び必要ない事例でも事業の内容によっては異なる判断となる
場合がありますので、ご了承ください。
必要書類
◎電気通信事業の届出(新規届出)
・電気通信事業届出書(様式第8)
・提供する役務に関する書類(様式第4)
・ネットワーク構成図(様式第3)
・定款の写し(法人のみ)
・受理通知書送付用の返信用封筒(切手(84円)を貼付し、送付先住所を記載)
◎氏名又は名称、代表者、住所の変更
・電気通信事業氏名等変更届出書(様式第6)
・変更が行われたことを証する書類
(1)登記事項証明書(法人のみ)
(2)住民票(個人のみ)
◎提供する役務の変更
・電気通信役務の変更報告書(様式第10)
・提供する役務に関する書類(様式第4)
・ネットワーク構成図(様式第3)
◎電気通信事業の全部の廃止又は休止
・ 電気通信事業全部休止(廃止)届出書(様式第12)
◎電気通信事業の一部の廃止又は休止
・電気通信事業一部休止(廃止)届出書(様式第12の3)
◎電気通信事業の承継
・電気通信事業承継届出書(様式第11)
・ネットワーク構成図(様式第3)
・合併、分割等があったことを証する書類
・登記事項証明書(法人のみ)・コピー不可、住民票(個人のみ)・コピー不可
・定款の写し(法人のみ)
◎法人の合併以外の事由による解散
・解散届出書(様式第12の5)
・清算人若しくは破産管財人であることを証する書類のコピー
◎電気通信事業の変更届出
・電気通信事業変更届出書(様式第9)
・ネットワーク構成図(様式第3)
報酬額及び実費
当事務所の報酬額は以下の通りです。
お客様の状況により金額が変動する場合がございます。
また、届出時交通費が別途かかります。
| 業務名 | 金額 |
|
電気通信事業の届出 |
33,000円 |
| 電気通信事業の届出 (インターネット異性紹介事業届出と一緒にご依頼の場合) |
22,000円 |
| 届出時送料 | 890円 |
| 各種変更届(1件あたり) | 22,000円 |
お問合せ
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。
TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com
関連リンク
監理団体の新規許可申請
2018年08月21日(火)5:02 PM
事業協同組合(以下、「組合」)が外国人技能実習生事業を行う場合、組合が監理団体の許可
を取得する必要があります。
なお、上記許可取得後に別途、実習実施機関(実習をする会社)が技能実習計画の認定申請
及び入国管理局に在留資格の申請が必要になりますので、ご注意下さい。
監理団体の法人形態
監理団体の法人形態は、原則として商工会議所、商工会、中小企業団体(事業協同組合)、
職業訓練法人、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人、公益財団法人となります。
上記以外の法人形態でも監理団体になる事は可能ですが、以下の要件を満たす必要があり
ます。
(ア)監理事業を行うことについて特別な理由があること
(イ)重要事項の決定及び業務の監査を行う適切な機関を置いていること
(ア)については、過去3年以内に以下の①又は②を行った実績があり、当該実績を資料等に
より明確に示せることが必要です。
①公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)上の
「公益目的事業」に該当する業務
②職業訓練、教育支援、我が国から外国への技能等の移転に関する業務等、人材育成の
支援に関する業務
監理団体許可申請に必要な書類
・提出は、正本1通(申請書、添付書類)、副本(申請書、添付書類)1通、副本(監理団体
許可申請書)1通となります。
※申請者に副本の返却はありませんので、組合で控えが必要な場合は上記の他に1通コピーを
取る事をおススメ致します。
・申請書及び添付書類は片面印刷となります。
| 番号 | 必要な書類 | 備考 |
| 1 | 監理団体許可申請一覧・確認表 | |
| 2 | 監理団体許可申請書 | |
| 3 | 監理事業計画書 | |
| 4 | 申請者の概要者 | |
| 5 | 登記事項証明書 | |
| 6 | 定款又は寄付行為の写し | |
| 7 | 船舶職業安定法第34条第1項の許可証の写し | 船員である団体監理型技能実習生に係る実習監理を行う場合 |
| 8 | 直近2事業年度貸借対照表の写し | |
| 9 | 直近2事業年度損益計算書又は収支計算書の写し |
| 10 | 直近2事業年度法人税の確定申告書の写し | 税務署の受付印があるもの |
| 11 | 直近2事業年度の法人税の納税証明書 | 所得金額の証明書「その2」が必要になります |
| 12 | 預金残高証明書等の現金・預金の額を証する書類 | 残高証明書や通帳の写しなど |
| 13 | 監理事業者の土地・建物に係る不動産登記事項証明書 | 事業所が複数ある場合は全ての事業所分 |
| 14 | 監理事業者の不動産賃貸借契約書の写し | 事業所が複数ある場合は全ての事業所分 |
| 15 | 個人情報の適正管理に関する規定の写し | |
| 16 | 監理団体の組織体系図 | 個人情報を取扱う部署を明示すること |
| 17 | 監理団体の業務の運営に係る規定の写し | ※監理費表の提出も必要になります |
| 18 | 申請者の誓約書 | |
| 19 | 役員の住民票 |
・役員全員分 |
| 20 | 役員の履歴書 | 役員全員分 |
| 21 | 監理責任者の住民票及び健康保険等の 被保険者証の写し |
複数の場合は全員分 |
| 22 | 監理責任者の履歴書 | 複数の場合は全員分 |
| 23 | 監理責任者講習の受講証明書の写し | ・複数の場合は全員提出 ・経過措置により当面は提出不要 |
| 24 | 監理責任者の就任承諾書及び誓約書 | |
| 25 | 外部監査人の概要書 | 指定外部役員の措置を講じない場合のみ必要 |
| 26 | 外部監査人講習の受講証明書の写し | 経過措置により当面は提出不要 |
| 27 | 外部監査人の就任承諾書及び誓約書 | |
| 28 | 指定外部役員の就任承諾書及び誓約書 | 外部監査の措置を講じない場合に必要 |
| 29 | 外国の送出し機関の概要書 | 複数ある場合は全て提出 |
| 30 | 外国政府発行の外国政府認定送出し機関の認定証の写し | ・外国政府認定送出し機関に該当 する場合は提出 ・複数ある場合は全て提出 |
| 31 | 監理団体と外国の送出し機関との団体管 理型技能実習の申込みの取次ぎに関す る契約書の写し |
複数ある場合は全て提出 |
| 32 | 外国の送出し機関の登記や登録がされて いることを証する書類 |
・複数ある場合は全て提出 ・外国政府認定送出し機関に該当す る場合は不要 |
| 33 | 送出国の技能実習制度関係法令を明らか にする書類 |
・複数ある場合は全て提出 ・外国政府認定送出し機関に該当す る場合は不要 |
| 34 | 外国の送出機関が送出国の技能実習制 度関係法令に従って技能実習に関する 事業を適法に行う能力を有する書類 |
・複数ある場合は全て提出 ・外国政府認定送出し機関に該当す る場合は不要 |
| 35 | 外国の送出機関の誓約書 | ・複数ある場合は全て提出 ・外国政府認定送出し機関に該当す る場合は不要 |
| 36 | 外国の送出機関の推薦状 | ・複数ある場合は全て提出 ・外国政府認定送出し機関に該当す る場合は不要 |
| 37 | 外国の送出機関が徴収する費用明細書 | ・複数ある場合は全て提出 ・外国政府認定送出し機関に該当す る場合は不要 |
| 38 |
技能実習計画作成指導者の履歴書 |
取扱職種全てについて作成指導者の 履歴書が必要 |
| 39 | 優良要件適合申告書 | 一般監理事業の許可を取得する際に 必要(別途、項目に応じて提出が求 められる資料があります) |
| 40 | 特定な職種を実習監理しようとする 場合に必要な書類 |
個別具体的な申請内容に応じて資料 が必要であると認められる場合に提 出が必要 |
| 41 | 委任状 | 申請書の提出や許可証の受領を委任 する場合に必要 |
| 42 | 返信用封筒 1枚 (申請受理票送付用) ※長形3号封筒 82円切手貼付 |
郵送で申請した場合のみ必要 |
| 43 | 返信用封筒 1枚 (結果の通知送付用) ※角形2号封筒 430円の切手を貼付 |
申請結果を郵送で受取る場合のみ |
| 44 | 申請手数料(収入印紙) | 基本額:1件につき2,500円 事業所が2以上の場合は、900円× (事業所-1) |
| 45 | 調査手数料払込みを証する書類 | 基本額:1件につき47,500円 事業所が2以上の場合は、17,100円 ×(事業所-1) ※申請前に払込みが必要 |
| 46 | 登録免許税納付を証する書類 | 1件につき15,000円 |
【注意点】
・事務所の写真は基本的に不要ですが、事務所面積が20㎡未満の場合は必要になる場合が
あります。 事務所の写真撮影箇所は以下になります。
1.事務所の入口(看板又は表札があること)
2.事務所全体の写真
3.デスク周辺の写真(従業員の人数分、PCや電話も撮影)
4.個人情報を管理するキャビネット等の写真(鍵付きであることが分ること)
5.応接セット
申請手数料・登録免許税について
(1)申請手数料(上記44欄)
申請書の所定の欄に必要額の収入印紙を貼付して納付となります。
なお、消印は不要です。
(2)調査手数料(上記45欄)
申請前に指定口座(三井住友銀行)へ振込
振込用紙(払込証明書)の控えを調査手数料払込申告書に貼付して提出します。
【振込先】
三井住友銀行 東京公務部 店番号:096 口座番号:0176809
口座名義:外国人技能実習機構
◎注意点等
・専用の振込用紙(外国人実習機構で配布)か、ATMもしくは各金融機関の振込用紙
にて振込となります。(専用の振込用紙で振込場合は、振込手数料がかかります)
・インターネットバンキングでの振込は認められません。
・振込人名義と申請者名義が一致すること。
・払込証明書に振込人の名義が記載されていること
(3)登録免許税(上記46欄)
申請前に「麹町税務署」宛に納付します
・納付場所
納付場所は次のどちらかになります。
①許可権者(厚生労働大臣・法務大臣)の所在地を管轄する税務署
管轄税務署:麹町税務署
②日本銀行(本店、支店、一般代理店。歳入代理店(郵便局を含む))
・納付に必要な書類
(納付書)領収済通知書 ※3枚綴りの様式
1枚目(領収済通知書)に所定の内容を記載して下さい。
3枚目(領収証書)が納付時に領収書として押印され返却されます。
※(納付書)領収済通知書の様式は、最寄りの税務署で入手可能です。
・(納付書)領収済通知書の記入例
年 度 : 該当年度をご記入
税目番号 : 221
税務署名 : コウジマチ
税務署番号 : 00031017
本 税 : 15000(右詰めで記入/円マーク)
合 計 額 : 15000(右詰めで記入/円マーク)
住所(所在地) : 申請者の住所等を記入
氏名(法人名) : 申請者の名称を記入 ※監理団体の正式名称を記入
報酬額
当事務所の報酬額(税抜)は以下の通りです。
なお、お客様の状況(事業所数)により金額が変動する場合がございますので、
ご了承下さい。
| 業務名 | 金額 |
| 監理団体の許可申請(新規取得) | 200,000円~ |
| 外部監査報酬(書類作成含む)※交通費別途 | 30,000円~ |
お問合せ
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。
TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com
関連リンク
短期滞在ビザの延長(更新)
2018年06月11日(月)7:16 PM
短期滞在ビザ(通称:観光ビザ)の延長は、「やむ得ない事情又はこれに相当する特別な
事情」がないと出来ません。上記事情は、一般的には病気や怪我の場合を指していますが、
その他の理由で延長できる場合があります。
経験上、一番多い理由は子供関係(孫の世話、子の出産)かと思いますので、その場合に
必要な書類や申請要件等について説明致します。
◎必要書類(例) ※申請人(孫の祖父母)が孫の世話をする場合
・申請人のパスポート
・その他、申請人の身分を証明できるもの(ある場合)
・申請人の出生証明書
・身元保証書
・身元保証人の出生証明書
・身元保証人の在職証明書
・身元保証人の課税証明書及び納税証明書
・身元保証人の預金通帳の写し
・住民票(世帯全員のもの)※マイナンバーが記載されていないもの
・滞在予定表
・理由書
・申請書
※出生証明書は申請人と孫との関係が分る物が必要になります。
◎申請要件 ※申請人(孫の祖父母)が孫の世話をする場合
・短期滞在ビザの滞在期間が90日であること
・子供(孫)が小学校に上がる前までであること
・申請人の滞在費を保証できること
◎報酬額
44,000円(税込)
延長(更新)が認められる際は別途、収入印紙代として4,000円かかります。
◎注意事項等 ※申請人(孫の祖父母)が孫の世話をする場合
・小さいお子様がいれば必ず延長できるという訳ではありません。
・年間の滞在日数は180日を超える事ができません。(再延長不可)
お問合せ
お問合せに料金は一切かかりませんので、短期滞在の延長に
ついてご不明な点がございましたら、 以下の方法にてどうぞ
以下の方法にてどうぞ
お気軽にお問合せください!
関連リンク
短期滞在ビザ
短期滞在ビザに必要な書類(中国)
短期滞在ビザに必要な書類(ロシア等)
短期滞在ビザに必要な書類(フィリピン)
短期滞在ビザに必要な書類(その他の国)
査証免除国一覧
- ご相談について
- ご依頼までの流れ
- 当事務所に依頼するメリット
- 会社設立業務
- 建設業許可申請
- 宅建業免許申請
- 離婚協議書作成業務
- ビザ申請を依頼するメリット
- 用語集
- 提携事務所
- リンク集
- サイトマップ
- トップページ
- お問い合わせ
過去のブログを検索
携帯サイト
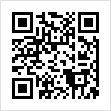
携帯電話をご利用の方は
QRコードを読み取って
モバイルサイトをご覧になれます。

当サイトは、
情報を安全に提供して頂くために、
「高度なセキュリティ」と「信頼性」で
定評のあるRapidSSLを利用しております。
プライバシーポリシー