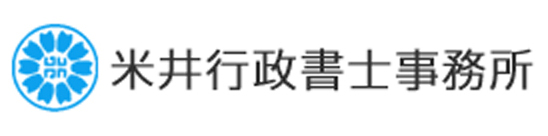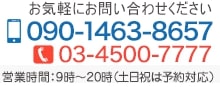国際結婚
2012年04月08日(日)2:25 PM
特定非営利活動法人(NPO法人)国際結婚協会は安心・安全な国際結婚の支援活動を基軸として
日本の国際文化活動の発展と日本の少子晩婚化対策に貢献している非営利第三者機関です。
墨田区の企業
2012年03月19日(月)9:43 PM
東京都墨田区総合印刷会社です。
冊子、ポスター、チラシ、POP等のデザイン・製作および印刷・加工。
ホームページ製作はお任せください。
浜野製作所(墨田区)は板金・レザー・プレス加工のエキスパート集団です。
墨田区 美容室 【美容室アトリエ8151】 美容院 都営浅草線、京成線押上駅、
業平橋駅から徒歩3分
東京都錦糸町駅1分の整体院です。頭痛・あごの痛みが得意
起業でのお役立ちリンク
2012年03月19日(月)9:00 PM
風俗営業や古物営業関係などの申請書類が入手できます。
国税庁
青色申告制度の説明や、各種税金の説明、税金の申請書が入手できます。
法務省
オンライン登記の説明、全国の登記所連絡先一覧があります。
中小企業庁
中小企業向けのさまざまな支援情報があります。
東京商工会議所
起業や新規事業展開に役立つ情報を得られます。
電子定款の解説、作成方法など、電子定款に関する各種情報提供、
電子定款対応行政書士の紹介。
建設業許可申請の代行業者をお探しなら建設業許可申請代行業サーチへ
出入国在留管理局のサイトです。
行政書士・その他士業検索
2012年03月19日(月)8:58 PM
行政書士は、法律に基づいて官公署に提出する書類や権利義務・事実証明に関する
書類を作成すること、提出手続代理や相談に応じることを業務とする 法律の専門家です。
行政書士事務所検索
全国の行政書士事務所検索は、事業者の所在地名はもちろん、
事業形態や対応サービスなど人気のあるキーワードでも検索が可能です。
行政書士SEO
行政書士専門のディレクトリ型検索サイト。
士業ねっと!
税理士、行政書士、社労士、弁護士などの専門家を紹介。
検索システム、動画、ブログ完備!
おねがい行政書士
日本全国から行政書士を探せるサイト
『行政書士どっとこむ』は行政書士を目指す人、行政書士、行政書士に相談したい人、
興味のある人がひとつにつながるポータルサイトです。行政書士データベースや講演会
カレンダー、コミュニティなど。
法律相談
弁護士・法律事務所・
行政書士の検索・無料紹介 まほろば
関西で活躍する士業事務所の無料紹介・一括見積・検索サービスです。
士業リンク
無料アクセスアップ支援、相互リンクサービス「士業リンク」
弁護士、司法書士、税理士、土地家屋調査士など各種専門家の検索や法律トラブルの
解決ができる検索エンジンです。
TOP行政書士
TOP行政書士は信頼と安心の行政書士検索サイトです。
全国の行政書士が都道府県別に検索できるリンク集です。
行政書士検索では、日本全国の行政書士が地域別に検索できます。
電子定款の解説、作成方法など、電子定款に関する各種情報提供、電子定款対応行政書士の紹介
行政書士事務所の案内サイト
契約書の雛形・文例・書式テンプレートなら行政書士本舗。
個人向け契約書用紙の通販!
全国の行政書士検索サイト
社会保険労務士事務所
2012年03月19日(月)8:56 PM
東京都葛飾区の行政書士・社会保険労務士事務所です。
会社設立、産業廃棄物業許可、給与計算、労働社会保険手続き、
就業規則作成などのご相談は岡崎事務所まで!
永住許可申請
2012年03月07日(水)10:02 PM
永住権(永住ビザ)は、外国人が日本国籍を所持しなくても日本に永住できる権利です。
在留期間の更新をしなくて良い、日本人と同じようにどのような仕事にも就く事ができる
などのメリットがありますが、選挙権がない、犯罪等を犯すと退去強制の対象になるという
制限もあります。
◎永住権のメリット
・在留期間が無期限になるため、在留期間の更新をしなくて良くなります。
※在留カードの更新は7年ごとにする必要があります。
・就労の制限がなくなりますので、どのような仕事にも就くことができます。
・国籍は従来のままです。
永住権と帰化の主な違い
永住権と帰化の違いはなに?
という質問をよく受けますが、永住権と帰化の主な違いは以下の通りです。
| 項 目 | 永住権 | 帰 化 |
| 国 籍 | 元の国籍 | 日本 |
| 参 政 権 | 無し | 有り |
| 退去強制 | 有り | 無し |
永住権を取得しても外国人には変わりませんので、犯罪等を犯すと退去強制の対象に
なりますし、7年ごとに在留カードの更新が必要だったり、再入国許可を取得しないで
1年以上出国すると永住権が取り消されますので、ご注意下さい。
永住権取得に必要な条件
営んでいること。
(前科がなく素行が日本社会において通常人として非難されない程度を意味します)
2.独立の生計を営むに足りる資産や技能を有すること
(生活の安定を確保できる資産があるか、日常生活を営む上で困らない報酬を確保する
技能を持っているか)
*年収の目安は、25万円×12か月=300万円と言われています。(独身者の場合)
この金額はあくまでも目安なので、300万円ないと許可が下りないという訳ではあり
ませんが、300万円程度ないと永住権の取得は厳しいかもしれません。
※配偶者や子供が1名増えるごとにプラス60万円前後が目安です。
*「独立の生計を営むに足りる資産」とは、申請人単独でなく、世帯単位で見た場合に安定
した生活が続けられると認められる場合には、要件を満たします。
3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
(ア)原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。
ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格(日本人の配偶者等、永住者の配偶
者等、定住者)をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
(イ)罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
納税義務等公的義務を履行していること。
(ウ)現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に
規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
※例えば4年間学生(留学ビザ)、その後就職4年間(就労ビザ)、その後学生に
戻り2年間学校(留学ビザ)の場合は上記要件を満たしません。
(エ)公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
※ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、上記1
及び2に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には
2に適合することを要しない。
◎在留期間の特例
①日本人、永住者および特別永住者の配偶者の場合は、実態の伴った婚姻期間が3年以上継続
し、かつ、引続き1年以上日本に在留していること。
が継続 していることが必要です。
※再婚した場合は、再婚相手との婚姻期間が3年以上継続かつ引続き1年以上日本に在留して
いることが条件となります。
して在留していること。
③「定住者」の在留資格を有する者は、定住後5年以上継続し日本に在留していること。
5年以上継続して日本に在留していること。
詳しくは下記ページをご覧下さい。
⑤難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して日本に在留していること。
⑥高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、
次のいずれかに該当するもの
(イ)3年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準と
して高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有して
いる者であると認められること。
⑦高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、
次のいずれかに該当するもの
(ア)「高度人材外国人」として1年以上継続して日本に在留していること。
(イ)1年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準と
して高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有して
いる者であると認められること。
⑧地域再生法第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の
区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の
規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動の件、第36号又は第37号のいずれ
かに該当する活動を行い、当該活動によって日本への貢献があると認められる者の場合、
3年以上継続して日本に在留していること。
永住権取得に必要な書類(例)
10年の在留で取得する場合)当事務所に依頼して頂いた場合や、審査の過程で以下の書類
以外のものが必要になる場合がありますので、ご了承下さい。
1.永住許可申請書 1通
2.写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。
写真のサイズに関しては、「提出写真の規格」のページでご確認下さい。
3.申請理由書(書式自由)
※日本語以外で記載する場合は、翻訳文が必要です。
(要翻訳者住所、氏名、捺印(署名))
4.身分関係を証明する次のいずれかの資料
(家族滞在及び配偶者系のビザを持っている方)
(2)出生証明書 1通
(3)婚姻証明書 1通
(4)認知届の記載事項証明書 1通
(5)上記(1)~(4)に準ずるもの
5.申請人を含む世帯全員の住民票
※マイナンバーの記載がなく、他の事項について省略がないもの
6.申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
a 確定申告書控えの写し 1通
b 営業許可書の写し(ある場合) 1通
※自営業の方は自ら職業等について立証していただく必要があります。
(3)その他の場合
職業に係る説明書(書式自由)及び、その立証資料
※申請人及び配偶者の方お二人とも無職の場合についても、その旨を説明書に記載。
7.直近(過去5年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を説明する
次のいずれかの資料
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が
記載されたもの) 各1通
※年間の総所得及び納税状況の両方が記載されている証明書であればいずれか一方で
構いません。
※直近5年分が発行されない場合は、発行される最長期間分を提出して下さい。
(2)直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料
(通帳の写し、領収証書等)
※直近5年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間が
ある方は、当該期間分について提出してください。
源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方
消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
上記税目が全て記載されているものが必要になります。
※住所地を管轄する税務署から発行されるものです。
※納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において
未納がないことを証明するものなので、対象期間の指定は不要です。
※取得時に個人番号カード(マイナンバーカード)又は個人番号通知カードが必要に
なります。
a次のいずれかで所得を証明するもの
(a)預金通帳の写し 適宜
(b)上記(a)に準ずるもの 適宜
b住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が
記載されたもの) 各1通
いずれか一方で構いません。
8.申請人又は申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明
する資料
(1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
次のア~ウのうち、ア又はイの資料及びウの資料を提出。
ア「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
※日本年金機構のホームページ(以下のURLを参照)から、ねんきんネットに
登録することができます。 https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
※申請時の直近2年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は、
「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の
印刷画面も併せて提出することになります。
ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
※直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書
(写し)を全て提出してください。
提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
※直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近2年間(24月
提出する必要はありません。
(2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
ア 国民健康保険被保険者証(写し)
※現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。
イ 健康保険被保険者証(写し)
※現在、健康保険に加入している方は提出してください。
ウ 国民健康保険料(税)納付証明書
※直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分
について提出してください。
エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)
※直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分
の領収証書(写し)を全て提出してください。
提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
(3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
申請時に社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の
納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資
料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所
における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア及びイのいずれかを
提出してください。
ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
※申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間に
おける、全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。
全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出して
ください。
イ社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)
9.申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
(1)預貯金通帳の写し 適宜
(2)不動産の登記事項証明書 1通
(3)上記(1)及び(2)に準ずるもの
10.パスポート 提示
11.在留カード 提示
指導です。(身元保証人になれるのは日本人もしくは永住者です)
(3)その他、各分野において貢献があることに関する資料 適宜
14.身分を証する文書等 提示
※申請人本人以外の方が申請する場合に必要です。
結果通知を送付する宛名、氏名を記載するシールで申請する出入国在留管理局でもらえ
ます。
・定住者の方は、「永住許可申請2」のページをご覧下さい。
・高度人材外国人として永住許可申請をする場合は、「永住許可申請4」のページを
◎標準審査期間:4か月程度 (現在、東京出入国在留管理局だと8か月前後かかります)
お問い合わせから永住権取得までの流れ
お客様のご契約内容により変更になる場合がありますので、ご了承下さい。
お電話、お問い合わせフォームにてお問い合わせ下さい。
↓
(2)面談の日時決定
年中無休で営業しておりますので、土日でも可能です。
また平日の19時以降といった時間でも可能です。
↓
(4)ご契約
↓
(5)報酬額のお支払い(お客様)
お振込または現金でのお支払いとなります。
↓
(6)必要書類の収集および提出(お客様)
当事務所が代理取得可能な書類もありますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
必要書類が揃いましたら、ご連絡ください。
↓
(7)申請書類の作成
↓
(8)申請書類のご確認(お客様)
↓
(9)パスポート、在留カードのお預かり、必要書類への署名(お客様)
お客様のご都合の良い場所まで伺うか、弊所でのお預かりになります。
↓
(10)出入国在留管理局へ申請
弊所が申請に行きますので、原則お客様が出入国在留管理局に行く必要は
ございません。
↓
(11)パスポート、在留カードのご返却および受付票のお渡し
お客様のご都合の良い場所か、弊所でのお渡しになります。
↓
(12)結果通知(許可)
標準審査期間は概ね4か月です。(入国管理局のHP上)
※東京出入国在留管理局の場合、現在は8か月程度かかります。
↓
(13)パスポート、在留カード、手数料納付書のお預かり
出入国在留管理局への申請手数料として8,000円の収入印紙が必要になります。
↓
(14)出入国在留管理局にて許可の受領(永住者の在留カード発行)
弊所が許可の受領に行きますので、原則お客様が出入国在留管理局に行く事は
ございません。(許可の受領代行はプランによります)
↓
(15)パスポート、在留カードのご返却
お客様のご都合の良い場所に持参するか、弊所にてお渡し致します。
永住権審査のポイント
1.原則、10年以上継続して本邦に在留していること。
「継続」とはビザが途切れる事がなく在留するしている事が必要とされます。
再入国許可を受けずに出国したり、海外滞在中に再入国許可が失効したりすると、
その人のビザは消滅し在留が継続している事にはなりません。
なお、留学生として入国した者が永住権を申請する場合、就労ビザに変更してから
5年間以上の在留及び就労が必要となります。
※一般的に年間6か月以上、日本国内に滞在していない場合は審査が厳しくなります。
2.3年もしくは5年の在留資格(ビザ)をもっていること
各ビザとも3年もしくは5年の在留資格を保有していないと申請条件を満たしません。
3.納税義務等の公的義務を履行していること
国民年金は支払っていなくても大丈夫な場合がありますが、健康保険料や住民税は支払
っていないと不許可になりますので、ご注意下さい。
※滞納分を一気に支払う、又は払っているが支払期限後に支払っている場合、状況として
あまり好ましくありません。
※収入が少ないのに扶養親族が多い、両親が若いのに扶養親族にしているなどの場合、
納税義務等の公的義務を履行していないとみなされる場合がありますので、ご注意
下さい。
4.永住権申請間近や申請中の転職・引越しはなるべく避けましょう
永住権申請の直近に転職された場合は、生活が安定していないとみなされる場合があった
り、追加書類が必要になる場合がありますので、可能ならば転職・引越しは控えるように
しましょう。
5.在留期間の更新をしましょう
永住権申請中に在留期限が到来する場合、必ず在留期間更新申請をするようにして
下さい。更新申請をしないと不法滞在(オーバーステイ)になります。
6.車の運転に注意しましょう
スピード違反や駐車違反にご注意下さい。
何度も違反を繰り返していると審査官の心証が悪くなる場合があります。
7.家族の方と一緒に永住権を申請することも可能です。
配偶者の場合は、婚姻後3年以上日本で同居している。又は海外での婚姻生活が3年以上
あり、かつ、日本で1年以上同居している事が条件になります。
子供の場合、永住権を申請しようとしている者と日本で1年以上の同居をしている事が
条件です。
8.虚偽の申請書類を提出するのは止めましょう
虚偽又は変造書類で許可を受けた事が発覚した場合、永住権が取消されますので、絶対に
やらないで下さい。
9.経営・管理ビザをお持ちの方は社会保険に加入しましょう。(経営者の場合)
自分が社員で所属している会社が社会保険に加入していない場合は、自分の意思だけでは
社会保険に加入できないので、社会保険でなくても大丈夫ですが、自分が経営者になっ
た場合加入していないと公的義務を果たしていないので、不許可になる場合があります。
※現段階では永住許可申請をするまでに加入していれば大丈夫です。
10.仕事の都合で日本を長期間離れている場合
所属機関(会社)の都合で長期間日本を離れている場合、その理由を説明した書面を
所属機関から発行してもらって下さい。(書式自由)
11.収入の見込証明書を提出する場合
収入の見込み証明書を提出(高度人材)する場合、通勤手当・扶養手当・住宅手当等の
実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものは除く。)及び超過勤務手当は含み
ません。諸手当を含まない旨を証明書に明記するようにしてください。
12.職務内容について
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で主たる業務が国際業務である場合、高度人材
のポイント制度を利用して永住許可申請はできません。
永住権を当事務所に依頼するメリット
当事務所に依頼した場合、基本的にはお客様が入国管理局に出頭する必要はありません。
2.永住権の取得確率が上がります
きをすることにより、許可の取得確率が上がります。
また、行政書士が申請した方が比較的早く許可の結果が出る傾向にあります。
当事務所が申請した中で一番早く結果が出たのが3ヶ月、遅くても4ヶ月半です。
※上記期間内に結果が出ることを保証するものではありません。
3.万全のサポート
お客様に返金いたします。 また、年中無休で21時までお問合せ可能です。
※再申請の場合、入国管理局までの交通費はいただきます。
万が一、不許可になったら
理由を聞いて再申請が可能であると判断した場合は、必要書類を揃え再申請するのが良いで
しょう。 東京入国管理局の場合、不許可通知書の発行日から10営業日が経過してから必要
書類を持って理由を聞きに行きます。
なお、受付時間は月~木の9時~12時、13時~16時までとなっています。
金曜日は受付していませんので、ご注意下さい。
弊所の報酬額および実費額(税込)
お客様の状況により、金額が変動する場合がございますので、ご了承下さい。
| 業 務 名 | 報 酬 額 等 | 業 務 内 容 |
| スタンダードプラン |
100,000円
|
申請書類の作成、申請についてのアドバイス、 申請代行、許可受領(もしくは不許可理由の 聞き取り) |
| コンサルティングプラン | 55,000円 | 申請書類のチェック、申請についてのアド バイス、申請代行(許可の受取はお客様) |
| チェックプラン | 38,500円 | 申請書類のチェックのみ |
| 収入印紙代 | 10,000円 | 許可時のみ |
詳しくはお問い合わせください。
お問合せについて
就労ビザ申請
2012年02月09日(木)3:05 PM
年々、外国人を雇用する企業が増えていますが、企業が外国人を雇用する場合は、仕事内容に応じた
ビザを取得する必要があります。
外国人を雇用したいけど、どのようなビザを取得したら良いか分からない、ビザ手続きの仕方が
分からない、現在外国人を雇用しているが、外国人が適法なビザを持っているか分からないなど、
就労ビザのことでご不明な点がございましたら、お問合せ下さい。
※外国人を雇用(離職)した場合、ハローワークに届出ることが義務になっています。
届出を怠ると30万円以下の罰金が科されますので、ご注意下さい。
(特別永住者、外交、公用のビザを持っている方は除きます。)
ビザについて
【就労可能なビザ】
【就労できないビザ】
【就労に制限がないビザ】
国外にいる外国人の雇用について
入国管理局で代理人(就職先の企業や行政書士等)が「在留資格認定証明書」の交付申請を
行ない、その証明書を国外にいる申請人に送付する事により就労ビザを取得します。
◎手続の流れ(ご依頼時)
STEP1 : 必要書類の収集(お客様・弊所)
申請人や雇用機関様が必要書類を収集します。
↓
STEP2 : 必要書類の作成(弊所)
収集していただいた必要書類を受領(郵送または手渡し)しましたら、申請書類一式を作成
致します。
↓
STEP3 : 申請書類のご確認及びご捺印(お客様)
弊所で作成した書類をご確認いただき、問題がなければご捺印をいただきます。
↓
STEP4 : 入国管理局へ申請(弊所)
弊所が代理申請しますので、原則、雇用予定企業様が出入国在留管理局に行く必要はありません。
↓
STEP5 : 審査結果の通知(出入国在留管理局)
標準審査期間は1か月~3か月です。
簡易書留郵便にて結果が届きます。(許可の場合は在留資格認定証明書が届きます)
万が一不許可の場合は、入国管理局に理由を聞きに行き、今後の対策を立てます。
↓
STEP6 : 在留資格認定証明書の送付(お客様)
雇用機関が入国管理局から送られてきた在留資格認定証明書を外国にいる申請人に送り、
申請人が在留資格認定証明書を持って自国にある日本大使館・領事館でビザの申請をします。
↓
STEP7 : 来日
在留資格認定証明書の有効期限は発効日から3か月です。
有効期限内に入国手続きをしないと失効しますのでご注意下さい。
なお、ビザが発行されたからといって必ず来日できるとは限りませんので、ご注意下さい。
◎事例別ビザ手続き
国外にいる外国人を雇用する際によく使われるビザは「技術・人文知識・国際業務」、
「技能」、「企業内転勤」です。(その他のビザで呼ぶ場合もあります)
以下は、一般的によく使われるビザの該当例と必要書類の例です。
・技術・人文知識・国際業務
【該当例】
機械工業等の技術者、SE、WEBデザイナー、通訳、デザイナー、私企業の語学教師など
【必要書類の例】
1.在留資格認定証明書交付申請書
2.写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
3.返信用封筒 1通(簡易書留用の切手貼付)
4.各カテゴリーに該当する資料(カテゴリーの詳細)
5.専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は
高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
・技能
【該当例】
調理師(コック)、スポーツ指導者、貴金属の加工職人など
【必要書類の例】
1.在留資格認定証明書交付申請書
2.写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
3.返信用封筒 1通(簡易書留用の切手貼付)
4.各カテゴリーに該当する資料(カテゴリーの詳細)
5.従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通
6.申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
※呼び寄せる人が調理人の場合と、そうでない人の場合で提出書類が異なりますので、
詳しくは、法務省の在留資格「技能」のページをご覧下さい。
・企業内転勤
【該当例】
外国の事業所からの転勤者
【必要書類の例】
1.在留資格認定証明書交付申請書
2.写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
3.返信用封筒 1通(簡易書留用の切手貼付)
4.各カテゴリーに該当する資料(カテゴリーの詳細)
※各ビザとも標準審査期間は1ヵ月~3ヵ月で、申請手数料は無料となっています。
国内にいる外国人を雇用する場合
留学生が日本で就職する場合、「留学ビザ」から「就労ビザ」に変更する必要があります。
ビザの変更申請は例年、東京入国管理局だと前年の12月 、その他の入国管理局だと、その年
の1月からできます。
(変更になる場合がありますので、必ず最寄の入国管理局でご確認ください)
また、転職で職務内容が変更になった場合、ビザの変更が必要になる場合があります。
永住者や日本人の配偶者等など、身分系のビザを取得している人はビザを変更する必要は
ありません。
※留学生が学校卒業後、本邦に滞在して就職活動をする場合は、ビザを「特定活動」に変更
しなくてはなりませんので、ご注意下さい。
※留学生が就労ビザに変更する際のガイドラインについては、以下をご覧下さい。
「留学生の就労ビザへの変更許可ガイドライン」
◎手続の流れ(依頼時)
STEP1 : 必要書類の収集(お客様・弊所)
申請人や雇用機関様が必要書類を収集します。
↓
STEP2 : 必要書類の作成(弊所)
収集していただいた必要書類を受領(郵送または手渡し)しましたら、申請書類一式を作成
致します。
↓
STEP3 : 申請書類のご確認及びご捺印(お客様)
弊所で作成した書類をご確認いただき、問題がなければご署名・ご捺印をいただきます。
↓
STEP4 : パスポート、在留カードのお預かり(弊所)
申請人のパスポート、在留カードの原本をお預かり致します。
お預かりの際には、「預かり書」を発行致しますので、ご安心下さい。
↓
STEP5 : 出入国在留管理局へ申請(弊所)
弊所が代理申請しますので、原則として申請人が出入国在留管理局に行く必要はありません。
申請後、お預かりしたパスポート、在留カードは早急にご返却致します。
↓
STEP6 : 審査結果の通知(入国管理局)
標準審査期間は2週間~1か月です。
許可の場合はハガキ、不許可または追加書類の提出の際は封筒が届きます。
※万が一不許可の場合は、出入国在留管理局に理由を聞きに行き、今後の対策を立てます。
↓
STEP7 : パスポート、在留カードのお預かり(弊所)
無事、許可が下りた場合は再度申請人のパスポート、在留カードの原本をお預かり致します。
お預かりの際には、「預かり書」を発行致しますので、ご安心下さい。
なお、許可受領時には4,000円の収入印紙と手数料納付書に必要事項のご記入及び
ご署名が必要になります。
↓
STEP7 : 許可の受領(弊所)
弊所が許可の受領に行きますので、原則申請人が入国管理局に行く必要はありません。
許可受領後は早急にパスポート、在留カードをご返却致します。
◎必要書類
【留学生が就職するのに必要な書類例】
・留学生が用意する物
1.在留資格変更許可申請書
2.写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
3.パスポート 原本提示
4.在留カード(みなし在留カード) 原本提示
5.申請人の履歴書
6.申請理由書
・就職先の会社が用意する物
1.雇用契約書の写し 1通
2.直近の決算書(損益計算書・貸借対照表) 各1通
※新設法人の場合は事業計画書
3.登記簿謄本 1通
4.会社のパンフレット
5.雇用理由書
・大学等が用意する物
1.卒業証明書又は卒業見込証明書
※在留資格変更許可の審査期間は1ヵ月~3ヵ月で、申請手数料は4,000円になります。
アルバイトを採用する場合
「留学」、「家族滞在」のビザで在留している外国人は、原則として就労活動ができません。
ただし、「資格外活動許可」を取得していれば、許可の範囲内で業務に従事させる事は可能
なので「留学」、「家族滞在」で在留している外国人をアルバイトで採用する場合は必ず
「資格外活動許可」を取得しているか確認して下さい。(在留カードの裏面をご確認下さい)
なお、就労ビザを持っている外国人であってもビザの活動範囲を超えて就労する事はでき
ません。
【資格外活動許可の就労可能時間】
| ビザの種類 | 資格外活動の時間 |
| 留学(原則) | 1週間につき28時間以内 |
|
留学(教育機関の長期休業時) |
1日について8時間以内 |
| 特定活動(就職活動をしている場合) | 1週間について28時間以内 |
| 家族滞在 | 1週間について28時間以内 |
・資格外活動許可も持っていても風俗業で働くことはできません。
・長期休業時は1日8時間の就労が可能ですが、週40時間を超えての就労はできません。
・どの曜日から1週間を起算した場合でも、常に1週について28時間以内となります。
・資格外活動許可の有効期限は、原則ビザの有効期限までとなります。
業種別雇用可能なビザの例
家族滞在、留学ビザの場合は、「資格外活動許可」の取得が必要です。
◎建設関係で雇用できるビザ
・建築現場などで作業員として雇用する場合
永住者、特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、留学、家族滞在
・事務員等として雇用する場合
永住者、特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、留学、家族滞在
※通訳や技術者として働いている人が、事務員等を兼務することは可能です。
・配送等の運転士、作業員として雇用する場合
永住者、特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、留学、家族滞在
◎飲食関係で雇用できるビザ
・ウエイトレス、ウエイター、コンビニ等の定員として雇用する場合
永住者、特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、留学、家族滞在
・調理師(コック)として雇用できるビザ
永住者、特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、技能、留学、
家族滞在
・ホスト、ホスト等の風俗店の従業員として雇用する場合
永住者、特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
※「資格外活動許可」があっても留学、家族滞在の方は雇用できません。
※興行で接客業務はできません。
◎製造業関係で雇用できるビザ
・通訳や技術者として雇用する場合
永住者、特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、技術・人文知識・
国際業務、留学、家族滞在
※通訳や技術者として働いている人が、事務員等を兼務することは可能です。
・事務員として雇用する場合
永住者、特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、留学、家族滞在
・工場等製造過程の作業員として雇用する場合
永住者、特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、留学、家族滞在
※クールジャパン分野に就労しようとする留学生の在留資格については以下サイトをご覧下さい。
クールジャパン分野の就労
就労資格証明書について
就労資格証明書とは、就労ビザを持って日本に在留している外国人からの申請に基づき、
その者が行うことができる収入を伴う活動を法務大臣が証明する文書で、主に転職の際に
利用されます。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」のビザを持っている外国人が、転職に伴い「技術・
人文知識・国際業務」以外の就労活動を行なった場合、外国人本人だけではなく、雇入れた
会社にも罰則規定が適用される場合があります。
そこで、外国人を雇用しようとする者は、その外国人が日本で就労する資格があるのか否か
についてあらかじめ確認したいと思いますし、外国人本人も就職等の手続をスムーズに行う
ためには、自分が就労できるビザを有していることを雇用主等に明らかにする手段があれば
便利です。
また、就労資格証明書を取得していないと、在留期間更新申請をした際に職務内容の不一致に
より不許可になる場合もあります。
このように雇用主、就労を希望する外国人両者の便宜を図ったのが「就労資格証明書交付
申請」制度です。なお、就労資格証明書は転職の際に必ず取得しなければいけないわけでは
なく、取得はあくまでも任意です。
※転職前に就労資格証明書を申請することも可能ですし、転職後、新しい会社に入社した後
でも就労資格証明書の申請は可能です。
◎就労資格証明書取得に必要な書類の例
1.パスポート 提示
2.在留カード 提示
3.源泉徴収票(転職前の会社が発行したもの)
4.退職証明書(転職前の会社が発行したもの)
5.雇用契約書の写し、またはこれに準ずるもので活動の内容、期間、地位及び報酬の記載が
あるもの(採用通知書の写し、辞令・給与辞令の写し など)
6.転職後の会社の概要を明らかにする資料
(1)登記事項証明書
(2)直近の決算書の写し
新設法人の場合は事業計画書
(3)会社案内
7.雇用理由書
■標準審査期間
当日(勤務先を変えた場合は1か月~3か月)
外国人留学生が学校卒業後に就職活動を行う場合
「留学」ビザから「特定活動」ビザへの変更が必要になります。
このビザは、大学を卒業した者、もしくは専修学校専門課程において専門士の称号を取得した
者について申請資格があります。
ビザの期間は6か月で、1回の在留期間更新手続きができますので、計1年間の滞在が可能
です。 なお、就職活動特中の「特定活動」ビザは、「資格外活動許可」を取ることにより、
アルバイトが可能です。
※日本語学校生は、「特定活動」ビザに変更できません。
【在留資格変更に必要な書類の例】
1.パスポート 提示
2.在留カード 提示
3.顔写真(縦4㎝×3㎝)
4.申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(通帳のコピー等)
5.就職活動を行っている事を明らかにする資料(会社の面接通知表、ハローワークの登録
証明書等)
6.経緯説明書
7.卒業校に関する証明書
【大学卒業の場合】
1.直前まで在籍していた大学の卒業証明書または卒業証書の写し
2.直前まで在籍していた大学の就職活動についての推薦状
【専門士の場合】
1.直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号証明書
2.直前まで在籍していた専修学校の卒業証書(写し)または、卒業証明書および成績証明書
3.直前まで在籍していた専修学校の就職活動についての推薦状
万が一、不許可になったら
慌てずにまずは入国管理局に行って不許可の理由を聞いて下さい(電話では聞けません)。
理由を聞いて再申請が可能であると判断した場合は、必要な書類を揃え再申請してください。
東京入国管理局の場合、不許可通知書の発行日から10日間が経過してから、必要書類を持って理由を聞きに行きます。
なお、受付時間は月~木の9時~12時・13時~16時までとなっていて、金曜日は受付して
いませんので、ご注意ください。
当事務所の報酬額
弊所の報酬額は以下の通りです。
【報酬額】
| 就労ビザの取得 | 88,000円 |
| 就労資格証明書の交付申請 | 55,000円 |
| 活動・契約機関に関する届出手続き (転職に関する届出) |
5,500 |
【入管への手数料】
| 窓口申請 | 6,000円 |
| オンライン申請 | 5,500円 |
※上記以外に実費がかかる場合があります。
※海外から呼び寄せる場合、入管への手数料は不要です。
お問合せについて
お問合せに料金は一切かかりませんので、外国人の雇用などでご不明な
点がございましたら、 どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)
TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com

LINE

WeChat
関連リンク
会社設立費用
2012年01月25日(水)10:15 AM
ご自身で全て設立手続きするより、専門家に一部を任せた方が安く設立できる場合がある事は
ご存知でしょうか?
プロのアドバイスも聞け、設立費用も安くなりますので、会社設立を考えている方は是非、
当事務所の会社設立プランをお試しください。
当事務所では会社設立だけではなく、資金調達・許認可・経理代行とトータルで御社をサポー
トいたします。
また、会社設立の際に必要となる印鑑セット(代表者印・銀行印・角印)を格安で販売いたし
ますので、詳しくはお問合せください。
会社設立費用・プラン
【株式会社設立費用】
|
項 目 |
ご自身で設立 した場合 |
Aプラン | Bプラン | Cプラン |
| 登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 |
| 公証人手数料 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
| 収入印紙代 | 40,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 謄本交付手数料 | 約2,000円 | 約2,000円 | 約2,000円 | 約2,000円 |
| 当事務所の報酬額 | 0円 | 30,000円 | 40,000円 | 70,000円 |
| 設立費用計 | 約242,000円 | 約232,000円 | 約242,000円 | 約272,000円 |
| 差額 | 0円 | 10,000円お得 | 0円 | +30,000円 |
※当事務所は電子定款を導入しているため、収入印紙代が0円になります。
※登録免許税は資本金の7/1000で、最低15万円になります。
※会社の代表者印や印鑑証明証代は別途かかります。
■電子定款とは?
電子定款というのは、今まで紙で作成し、公証役場で認証してもらっていた定款を電子媒体で認証が受けられるようになったものです。
この電子定款を使用すると印紙税法上、文書扱いではなくなる為、収入印紙代4万円が不要になり会社設立費用を節約することができます。
■株式会社設立について詳しく知りたい方はこちらをクリックしてください。
プランの説明
【Aプラン】電子定款作成プラン
定款を当事務所で作成し、電子署名と定款の認証を行なうプランです。
安く会社を設立したい方にオススメなプランです!
【Bプラン】株式会社設立書類作成プラン
株式会社設立書類の作成と電子定款の作成・認証を当事務所で行うプランです。
※登記申請は、お客様ご自身でやっていただきます。
【Cプラン】株式会社設立フルサポートプラン
株式会社設立書類の作成、電子定款の作成・認証、登記(提携司法書士)を当事務所で
行うフルサポートプランです!(登記は提携している司法書士が行います)
会社設立の手続きが分からない、本業の準備に専念したい方にオススメなプランです。
合同会社設立
【合同会社設立費用】
| 項 目 | ご自身で設立 した場合 |
Aプラン | Bプラン | Cプラン |
| 登録免許税 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
| 収入印紙代 | 40,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 当事務所の報酬額 | 0円 | 20,000円 | 30,000円 | 50,000円 |
| 設立費用計 | 100,000円 | 80,000円 | 90,000円 | 85,000円 |
| 差額 | 0円 | 20,000円お得 | 10,000円お得 | 0円 |
※当事務所は電子定款を導入しているため、収入印紙代が0円になります。
※登録免許税は資本金の7/1000で、最低6万円になります。
※会社の代表者印や印鑑証明証代は別途かかります。
■合同会社設立について詳しく知りたい方はこちらをクリックしてください。
プランの説明
【Aプラン】電子定款作成プラン
定款を当事務所で作成し、電子署名をいたします。
ご自身で会社設立手続きをするよりも安く設立できますので、大変お得でオススメなプランです!
【Bプラン】合同会社設立書類作成プラン
合同会社設立書類の作成と電子定款の作成を当事務所で行うプランです。
※登記申請は、お客様ご自身でやっていただきます。
【Cプラン】合同会社設立フルサポートプラン
合同会社設立書類の作成、電子定款の作成、登記申請(提携司法書士)を当事務所で
行うフルサポートプランです。(登記は提携している司法書士が行います)
会社設立の手続きが分からない、本業の準備に専念したい方にオススメなプランです。
電子署名プラン
【電子署名プラン利用時の会社設立費用】
| 項 目 | ご自身 (株式会社) |
当事務所 (株式会社) |
ご自身 (合同会社) |
当事務所 (合同会社) |
| 登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
| 公証人手数料 | 50,000円 | 50,000円 | 0円 | 0円 |
| 収入印紙代 | 40,000円 | 0円 | 40,000円 | 0円 |
| 謄本交付手数料 | 約2,000円 | 約2,000円 | 0円 | 0円 |
| 当事務所の報酬額 | 0円 | 10,000円 | 0円 | 10,000円 |
| 設立費用計 | 約242,000円 | 約212,000円 | 100,000円 | 70,000円 |
| 差額 | - | 30,000円お得 | - | 30,000円お得 |
プランの説明
会社設立に必要な書類の作成や登記申請は、お客ご自身でやっていただき、定款の電子署名だけを当事務所で行なうプランです。
ご自身で設立するよりも大変お安く設立ができるお得なプランとなっております。
少しでも安く会社を設立したい方は、当事務所の電子署名プランを是非、お試しください。
※定款認証業務はお客様ご自身となります。
※別途、郵送料がかかります。
お客様にやっていただく事
株式・合同会社共通
| 項 目 | Aプラン | Bプラン | Cプラン |
| 会社の基本事項決定 | ○ | ○ | ○ |
| 会社実印の作成 | ○ | ○ | ○ |
| 印鑑証明書の取得 | ○ | ○ | ○ |
| 会社設立書類の作成 | ○ | - | - |
| 出資金(資本金)の払込 | ○ | ○ | ○ |
| 電子定款の作成 | - | - | - |
| 登記申請(提携司法書士) | ○ | ○ | - |
○:お客様でやっていただくこと
-:当事務所等で行なうこと
・会社の基本事項については当事務所でアドバイスいたします。
・印鑑の作成、印鑑証明書の取得は当事務所でも可能です。
当事務所に会社設立を依頼するメリット
(別途費用がかかります)。
お問合せについて
お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。
関連リンク
事業協同組合
電子定款について
資金調達(融資)
経理代行業務
プログラム著作物
2011年12月31日(土)9:33 PM
【定義】
電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるように
これに対する指令を 組み合わせたものとして表現したもの。
組み合わせたものとして表現したもの。
【プログラム言語の例】
Excelのマクロや関数、FORTRAN、COBOL、C、C++、Basic、
アセンブラ、VBAなど
【プログラム著作物ではないもの】
・設計書
・仕様書
・マニュアル
・フローチャート
・画面レイアウト
・出力帳票など
プログラム登録のメリット
・社会的信用度の拡大
・権利移転等の場合の第三者対抗要件の取得
・取引や契約における円滑化
プログラム登録の種類
1.創作年月日の登録
プログラムを創作した日を登録できる。
著作者のみが登録でき、創作後6ヶ月以内に申請しなければならない。
2.第一発行年月日の登録
発行された年月日を登録する。
古いプログラムでも発行されていれば、著作権者または無名、変名で公表された
著作物の発行者が申請できる。
3.実名の登録
無名または変名で公表されたプログラムの著作者の実名を登録することができる。
なお、登録することにより、保護期間が50年まで延長される。
4.著作権(譲渡)の登録
著作権の権利の変動を登録する。
登録することにより第三者対抗要件が得られる。
申請に必要なもの
・登録申請書
・著作物の明細書
・複製物(マイクロフィッシュ・CD-R・DVD-R)
・登録手数料納付書
・委任状(代理人がいる場合)
・その他(契約書の写しなど)
登録手数料及び登録免許税
| 登録の種類 | 登録手数料 | 登録免許税 | 合計 |
| 創作年月日の登録 | 47,100円 | 3,000円 | 50,100円 |
| 第一発行年月日の登録 | 47,100円 | 3,000円 | 50,100円 |
| 実名の登録 | 47,100円 | 9,000円 | 56,100円 |
| 著作権(譲渡)の登録 | 47,100円 | 18,000円 | 65,100円 |
※上記の他に当事務所への申請手数料がかかります。
お問合せ
お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せ下さい!
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。
関連リンク
産業廃棄物の種類
2011年12月23日(金)12:20 PM
| 種類 | 具体例 |
| 燃え殻 | 活性炭、焼却炉などの各種焼却かす |
| 汚泥 | 排水処理の汚泥、建設汚泥などの各種泥状物 |
| 廃油 | 潤滑油、大豆油など、鉱物性動植物性を問わず全ての酸性廃液 |
| 廃酸 | 廃写真定着液など、有機性無機性を問わず全ての酸性廃液 |
| 廃アルカリ | 廃写真現像液、廃金属石けん液など、有機性無機性を問わず 全てのアルカリ性廃液 |
| 廃プラスチック類 | 発泡スチロールのくず、合成繊維くずなど、固形状液状を問わず全ての 合成高分子系化合物(合成ゴムを含む) |
| ゴムくず | 天然ゴムくず(注:合成ゴムは廃プラスチック類) |
| 金属くず | 鉄くず、アルミくずなど、不要になった金属、金属の研磨くず、 切削くずなど |
| ガラス・コンクリート・陶磁器くず | 板ガラス、耐火レンガくず、石膏ボードなどコンクリート 製品製造工程からのコンクリートくず等 |
| 鉱さい | サンドブラストの廃砂、不良石炭、各種溶鉱炉かすなど |
| がれき類 | 工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリートの破片、 レンガの破片など |
| ばいじん | 大気汚染防止法のばい煙発生施設、または産業廃棄物焼却施設の 集じん施設によって集められたばいじん |
| 紙くず | 以下の業種から発生する紙くずに限る ・建設業(工作物の新築、改築、除去により生じたもの)、 パルプ製造業、製紙業、紙加 工品製造業、新聞業、 出版業、製本業、印刷物加工業 (注:これ以外の業種から発生するコピー用紙などは事務系 一般廃棄物) |
| 木くず | ①以下の業種から発生する木くず、おがくず、バーク類など ・建設業(工作物の新築、改築、除去により生じたもの)、 木材又は木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ 製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業 (注:これ以外の業種から発生した②以外のものは、 事務系一般廃棄物) ②貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの 貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む) (注:木製パレットは排出事業者の業種限定はありません) |
| 繊維くず | 以下の業種から発生する天然繊維くずに限る 建設業(工作物の新築、改築、除去により生じたもの)、衣服その他繊維製品 製造業以外の繊維工業 (注:これ以外の業種から発生する不要な天然繊維製の 衣服などは事務系 一般廃棄物) |
| 動物系固形 不要物 |
と畜場で解体等した獣畜や食品処理場で処理した食鳥に係る 固形状の不要物 |
| 動植物性残さ |
食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で原料として使用した |
| 動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどのふん尿 |
| 動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどの死体 |
| 汚泥コンクリート の固形物など |
上記の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記に該当しないもの |
- ご相談について
- ご依頼までの流れ
- 当事務所に依頼するメリット
- 会社設立業務
- 建設業許可申請
- 宅建業免許申請
- 離婚協議書作成業務
- ビザ申請を依頼するメリット
- 用語集
- 提携事務所
- リンク集
- サイトマップ
- トップページ
- お問い合わせ
過去のブログを検索
携帯サイト
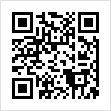
携帯電話をご利用の方は
QRコードを読み取って
モバイルサイトをご覧になれます。

当サイトは、
情報を安全に提供して頂くために、
「高度なセキュリティ」と「信頼性」で
定評のあるRapidSSLを利用しております。
プライバシーポリシー